|
トランジスタの実験 入力特性(IB-VBE特性・IC-VBE特性) |
|
|
|
|
| |
▼説明・・・ |
|
|
ベース・エミッタ間電圧VBEを変化させた時のベース電流IBとコレクタ電流ICの変化を見ます。
|
|
|
▼実験回路です・・・ |
|
|
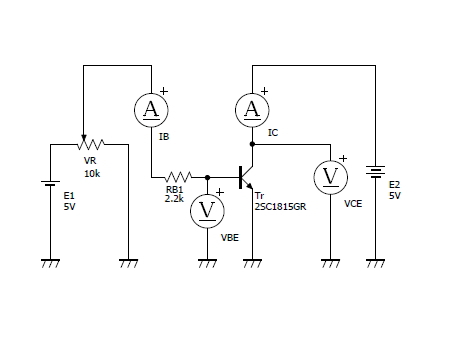
ベース・エミッタ間電圧VBEをVRで変化させて、その時のベース電流IB、コレクタ電流IC、ベース・エミッタ間電圧VBE、コレクタ・エミッタ間電圧VCEを測定します。RB1は、2.2kΩ固定です。VRは、0.1V単位で微調整が出来る様にポテンシャルメータを使用しました。これで0〜5Vに変化させています。
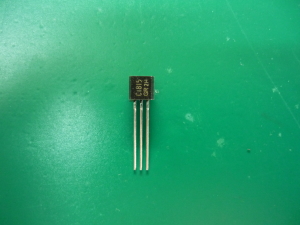 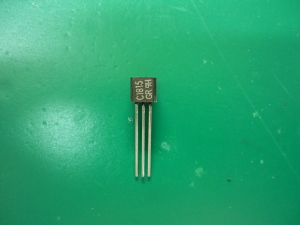
これが今回使用するトランジスタ2SC1815の外観です。今までは、右の物だったのですが、最近購入すると左の物になっています。文字の感じが違います。中国製の模造品かと思いましたが、実は文字をレーザーで焼いて書き込んであるそうです。そういえば最近の東芝のICもこんな感じの文字が入っています。”GR”と書いてあるのはhFEのランクでGR=200〜400になります。
| 2SC1815(東芝)【株式会社東芝データシートより】 |
| 項目 |
記号 |
定格 |
単位 |
| コレクタ・ベース間電圧 |
VCBO |
60 |
V |
| コレクタ・エミッタ間電圧 |
VCEO |
50 |
V |
| エミッタ・ベース間電圧 |
VEBO |
5 |
V |
| コレクタ電流 |
IC |
150 |
mA |
| ベース電流 |
IB |
50 |
mA |
| コレクタ損失 |
PC |
400 |
mW |
| 接合温度 |
Tj |
125 |
℃ |
| 保存温度 |
Tstg |
-55〜125 |
℃ |
| 上記データーは2002年01月29日現在 |
上の表が、今回使用するトランジスタ東芝の2SC1815の最大定格です。最大定格とは、絶対に超えてはいけない定格の事で、超えると壊れると言うことです。実際に使用する時は、この最大定格の半分ぐらいに成るように設計します。
|
|
|
▼実験です・・・ |
|
|
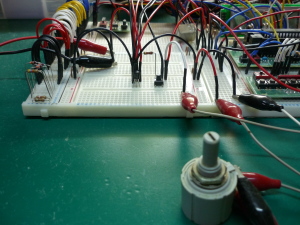 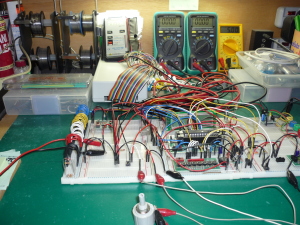
左の写真が全体の様子です。奥にあるカード型テスター(カイセKU-1133)でベース・エミッタ間電圧VBE、左側の緑色のテスター(共立電気計器KEW1011)でベース電流IB、右側の緑色のテスター(共立電気計器KEW1011)でコレクタ電流IC、、黄色のテスター(メーカー?型番?ホームセンターで\1,000で購入)でコレクタ・エミッタ間電圧VCEを測定します。 手前にあるネズミ色の丸いものがポテンシャルメータです。
|
|
|
▼結果です・・・ |
|
|
| 実験結果 |
| ベース・エミッタ間電圧(VBE) |
ベース電流(IB) |
コレクタ・エミッタ間電圧(VCE) |
コレクタ電流(IC) |
| V |
mA |
V |
mA |
| 0.0000 |
0.0000 |
5.0000 |
0.0000 |
| 0.1000 |
0.0000 |
5.0000 |
0.0000 |
| 0.2000 |
0.0000 |
5.0000 |
0.0000 |
| 0.3000 |
0.0000 |
5.0000 |
0.0000 |
| 0.4000 |
0.0000 |
5.0000 |
0.0000 |
| 0.5000 |
0.0001 |
5.0000 |
0.0109 |
| 0.6000 |
0.0013 |
4.9900 |
0.3175 |
| 0.7000 |
0.0604 |
4.9700 |
14.5500 |
| 0.7500 |
1.7610 |
4.6300 |
135.4000 |
| 気温 28.0℃ 上記データーは2008年09月26日現在 |
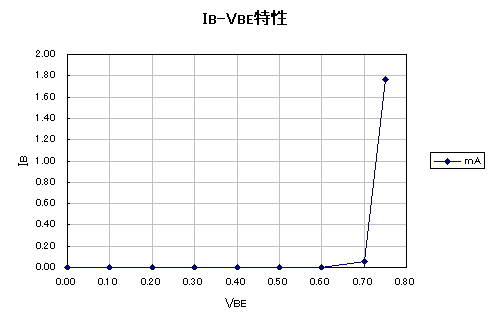
ベース電流(IB)とベース・エミッタ間電圧(VBE)の関係のグラフです。ベース・エミッタ間電圧(VBE)が0.6V以下の時、ベース電流(IB)はほとんど流れません。0.6V以上になると急に流れる様になります。
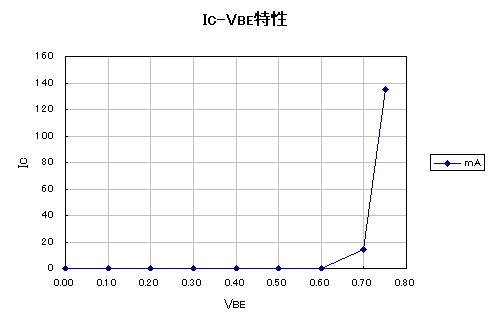
コレクタ電流(IC)とベース・エミッタ間電圧(VBE)の関係のグラフです。 やはり0.6V以下の時は、ベース電流(IB)が流れない為、コレクタ電流(IC)も流れません。0.6V以上になると、ベース電流(IB)が流れるので、コレクタ電流(IC)も流れる様になります。上のグラフと下のグラフはとても似たような形になります。
|
|
|
▼修正履歴 |
|
|
2008年(平成20年)09月28日 完成
2008年(平成20年)10月12日 デザインを修正
2008年(平成20年)10月19日 回路図を修正 |
|
| Copyright (c)2001-2008 T.S FT-SYSTEM All Rights Reserved. |