発泡スチロール製生ごみコンポストの使い方

(C)Yoko Oonaka
生ごみはゴミではなく資源です。以下は、あくまでも我が家流の方法です。
いろいろな工夫で個々違った方法ができると思います。
 生ごみはためると腐敗してしまいます。
生ごみはためると腐敗してしまいます。
腐って腐敗臭を出す前に土に還すようにしましょう。
水分は軽く切ってから入れます。水分過多は悪臭の原因になります。
神経質になる必要はないと思いますが、あまりビショビショにしないほうが良。
我が家では三角コーナーはなく、金属製のザルをシンクの上のほうに置いて、シンクに水を流しても生ごみに水がかからないようにしています。シンク内に置くと、きれいな水を流しても生ごみを1回通過することによって、水を汚して、下水に落としていることになるからです。
 生ごみは大きいものは細かく切ってから入れたほうが早く分解されます。
生ごみは大きいものは細かく切ってから入れたほうが早く分解されます。
火の通った生ゴミはより早く分解されます。
▼そのままではなかなか分解しにくい鶏手羽の骨やアサリなどの貝殻などは出刃包丁や肉たたきなどで叩き割って入れると、その他の野菜くずと同じスピードで土に返ります。
▼少しなら、そんなに神経質になることはありませんが、塩気の多いものは大量には入れないほうがいいでしょう。
▼バーベキューの後に出た炭の粉なを入れると土の中に程よい空気の穴が出来て分解がスムーズになります。
▼米ぬかが余っていれば生ごみを入れるときにパラパラと振りかけると、中の温度が上がり、分解されやすくなります。
▼ただ、イカや魚の生のワタ(火の通っているのならばOK)はかなり臭くなり、ニオイがします。これだけは我が家は土に埋めることにしています。
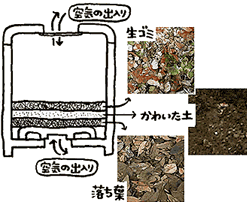 落ち葉→乾いた土→生ごみの順番に入れていきます。生ごみを入れたら、またその上に落ち葉&乾いた土を敷いていきます。だいたい分量は三種類とも同じくらい。
落ち葉→乾いた土→生ごみの順番に入れていきます。生ごみを入れたら、またその上に落ち葉&乾いた土を敷いていきます。だいたい分量は三種類とも同じくらい。
これの繰り返しで口いっぱいになるまで続けます。しばらく置くと全体のカサが減り、生ごみの形はなくなっています。
 今度は四隅に順々に生ごみを入れていきます。軽く穴を掘るように土をかき混ぜ、生ごみを入れて土をかぶせます。必ず土の下に生ゴミをしまい込むようにして入れます。
今度は四隅に順々に生ごみを入れていきます。軽く穴を掘るように土をかき混ぜ、生ごみを入れて土をかぶせます。必ず土の下に生ゴミをしまい込むようにして入れます。
四隅の4ケ所と真ん中の計5ケ所で5日間サイクル。
生ごみが消えて土に還ったあとに再び生ごみを入れる際は軽くでもまわりの土と混ぜ合わせるように、攪拌して空気を入れるようにすると分解もうまくすすみます。
 これを繰り返していくと、どんどん微生物が増えて、たった1日で生ごみが姿を消してしまうようになります。後で土や落ち葉を足す必要はありません。
これを繰り返していくと、どんどん微生物が増えて、たった1日で生ごみが姿を消してしまうようになります。後で土や落ち葉を足す必要はありません。
生ごみだった食べ物のカタチがなんとなくわかるものもありますが、手でさわるとポロッとカタチがくずれてしまいます。
こうなると生ごみにたかる虫も生きていけません。ウジムシは未熟な堆肥でしか生きていけないからです。
(注)生ごみ処理の初期段階の際にどこから入ってくるのか?虫がわく場合もありますが、そんなときは「見なかったことに…」とフタを閉めて、夏なら1週間、秋冬は2週間くらいでも生ごみを入れるのを中断してそっとしておくと分解がすすみ、ふたたびコンポスターを開けたときには虫の姿はなくなっていますので、再開するといいでしょう。
 ある程度分解が進んだら中の堆肥を少し袋に移して、数ヶ月熟成させれば肥料として使うこともできます。すぐに未熟なまま使うと植物の根が焼けて障害が出ることもあるので注意。
ある程度分解が進んだら中の堆肥を少し袋に移して、数ヶ月熟成させれば肥料として使うこともできます。すぐに未熟なまま使うと植物の根が焼けて障害が出ることもあるので注意。
植物日誌


 生ごみはためると腐敗してしまいます。
生ごみはためると腐敗してしまいます。 生ごみは大きいものは細かく切ってから入れたほうが早く分解されます。
生ごみは大きいものは細かく切ってから入れたほうが早く分解されます。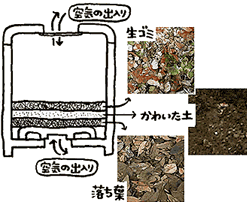 落ち葉→乾いた土→生ごみの順番に入れていきます。生ごみを入れたら、またその上に落ち葉&乾いた土を敷いていきます。だいたい分量は三種類とも同じくらい。
落ち葉→乾いた土→生ごみの順番に入れていきます。生ごみを入れたら、またその上に落ち葉&乾いた土を敷いていきます。だいたい分量は三種類とも同じくらい。 今度は四隅に順々に生ごみを入れていきます。軽く穴を掘るように土をかき混ぜ、生ごみを入れて土をかぶせます。必ず土の下に生ゴミをしまい込むようにして入れます。
今度は四隅に順々に生ごみを入れていきます。軽く穴を掘るように土をかき混ぜ、生ごみを入れて土をかぶせます。必ず土の下に生ゴミをしまい込むようにして入れます。 これを繰り返していくと、どんどん微生物が増えて、たった1日で生ごみが姿を消してしまうようになります。後で土や落ち葉を足す必要はありません。
これを繰り返していくと、どんどん微生物が増えて、たった1日で生ごみが姿を消してしまうようになります。後で土や落ち葉を足す必要はありません。 ある程度分解が進んだら中の堆肥を少し袋に移して、数ヶ月熟成させれば肥料として使うこともできます。すぐに未熟なまま使うと植物の根が焼けて障害が出ることもあるので注意。
ある程度分解が進んだら中の堆肥を少し袋に移して、数ヶ月熟成させれば肥料として使うこともできます。すぐに未熟なまま使うと植物の根が焼けて障害が出ることもあるので注意。