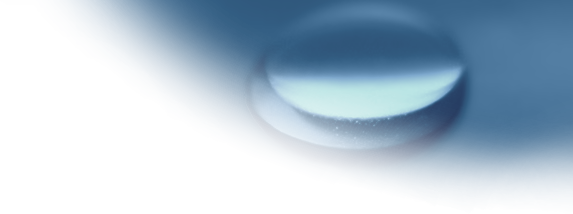 夢の狭間
夢の狭間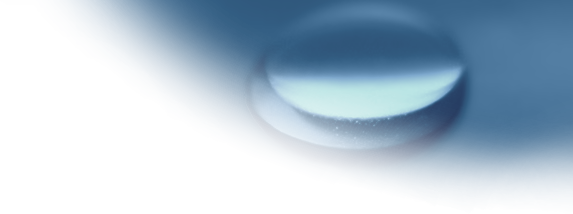 夢の狭間
夢の狭間
アーケード商店街の中ほどにあるソバ屋で、いつもの通り、煮凝りを肴に2合の酒を飲んでいた。いつもなら頃合いを見てざるそばを出してくるのだが、なぜか今日は親父が厨房から出てきて、ぼくに一瞥もくれずに、店の外を見てる。その動作が尋常ではなかった。
「旦那、ちょっとちょっと」と顔を振り返って、手招きした。目が光り散っていた。
ぼくは立ち上がってゆっくり移動し、親父にかぶさるようにして外を見た。
広い商店街を薄く水が流れ、何やら黒いものが無数にのたうちまわっている。
「ウナギかい?」
「違うですよ。ナマズでさ」
「いやだね」
「そんなことねえですよ、かば焼きにするとうめえですよ、旦那......」と、親父は体をこわばらせて言った。
と、親父はバケツを手に外に飛び出した。そして目をギラギラさせてナマズを見繕っている。
やがて急いで店に戻り、厨房に飛び込んで、いきなりナマズのでかい頭にぐいっと包丁を入れた。
「泥抜きしないと泥臭くないかい?」
「なあに、真水をのたくって商店街までやってきたんだからとうに泥はぬけてまさあ」と意に介さない。
串刺しにされたナマズの白身が出来上がり、おやじは壺の中にそれを突っ込みたれをたっぷり付けた。やがて香ばしい匂いが......。
おっと、もう昼近い。カーテンを開くと真夏の光が眩しい。
サングラスをかけて外に出る。足は当然、そば処「萬太郎」に向く。湿度が低いせいか汗はかかない。意外と気持ちいい。
店に入るといきなり親父が厨房から顔をのぞかせ、「ホイ、旦那、今日いいのが入ってますぜ」と叫ぶ。
「たのむよ」と答えて席に着く。
おかみさんがガラスの2合徳利で酒を素早くだす。薄いブルーのガラスぐい飲みに注ぎちびりちびりと飲み始める。
そのうち店内にいい匂いが漂い始め、親父自ら皿を持ってきた。
「へいおまち!」
「オッ蒲焼か...う、な、ぎ......」
そこでぼくは絶句した。頭がもやもやしてきた。な、ま、ず、う、な、ぎ......頭がぐるぐるしてきた。落ち着け落ち着け、うまいじゃないか。酒はいつもの日本名門酒会の大山、いい心持でぐいぐい飲む。
今日はそばはよした。急にせわしない気持ちがせりあがってきたのだ。あたふたと店を出た。足早になるなる、どんどん加速する。
商店街は水が流れ、買い物客と黒いナマズで溢れている。僕はその中に入っていった。かき分けて前へ進むが感触がない。ただただ前進を続ける他ない......ぐいぐい進むが果てしがない、不安が全身に降りかかり、怖くなってきた。