
200�U�N�V��
�Q�O�O�U�N�V���R�P���i���j�j ����
���A���{�S���S�V�s���{���̂����A
���ݓ��ꂽ���Ƃ��Ȃ�����������������B
����́A���{�ŗB��A�S�����������E����B
�k�C������B���A���߂ĖK�ꂽ���́A
�u�t�P�W�����Ձv���g���āA�e�w��ԂŖK�ꂽ�����ɁA
�S�����Ȃ���A�w�ق��Ȃ��A��������Ȃ��c�B
����ɂ́A���܂薣�͂������Ă��Ȃ������̂������B
���Ƃ��A�ǂ�Ȃɔ������C��A���������H�ו��������Ă��A
�u�s���Ă݂����v�Ƃ����C�����ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ł���B
�������A���N�̔~�J�́A���̋C��������ς������B
�S�[���f���E�B�[�N�ȍ~�A�܂Ƃ��ɐ��ꂽ�L���̂Ȃ������B
�Q�������ܓV�̉��ŕ�炷�̂́A�����E���U���c�B
���̓��A���ɂ���C�ۋ���̓V�C�\��̒[����`���A
����}�[�N���t���Ă���̂́c�A����̂݁I
���͂�B�Ă͑҂��Ă�����̂ł͂Ȃ��A�������狁�߂Ă������̂��B
�v���A�Q�O�O�R�N�A����ɊJ�Ƃ����u�䂢���[���v��
���n��ނ����Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����I
����ɁA���̉Ă���́A�X�J�C�}�[�N�̐[��ւ��A�q�B
������ł��A�Q���~�`���b�g�ʼn���ɍs����B
�����͐������B����͍s�������Ȃ��I
�v�����ŏo����������A�w�ق͂�����B
�䂢���[���E���w�̉w�قł���B

�Q�O�O�R�N�ɊJ�Ƃ����u�䂢���[���v�́A
�ߔe��`�`�Ԃ��Q�V���Ō��ԁA�S��12.9�L���̃��m���[���B
����B��́g�S�����ۂ��h��蕨�ł���B
�s�s�̌�ʋ@�ւł��邽�߁A���R�A�w�قȂǐH�����Ƃ��o����
��蕨�ł͂Ȃ��̂����A�ό��p�ɉw�ق�����Ă���B

�w�ق�̔����Ă���̂́A���i�ڂ���j�w�B
�ߔe�����X�ǂ̍Ŋ�̉w���B
�g�����X�ǁh�Ƃ����̂́A���̓s�s���\����w��
�w�̋߂��ɂ���̂����ʁB
�s�s�̑�\�w�ɂ́A�����Ă��w�ق����邩��A
���R�ł͂��邪�A���Ɂu�w�فv������̂́A���R�ł�����B

�����A�w�̍\���ɂ͔��X����Ȃ��B
����䂵�V���c�p�̏����w���ɐu���A
���X�́A�w����T���قǕ��������Ƃ̂��ƁB
���ꂪ�w�قł͂Ȃ��u�w�O�ٓ��v�Ɩ���鏊�Ȃ��B
�̔����Ă���̂́A�߂��̋����������u�����ȁv�ł���B
���Ԃ������ɁA��̂��ꂽ�}�O���B
�������Ƃ������A��������̍�Ə�Ƃ��������B
�i�c�Ǝ��ԁF���X���`�[���U���j

���ꂪ���{�œ�[�́u�w�فv�A�w�ّ��Ȃǂł����Ȃ��݂�
�u�C�l(���݂�)�������w�O�ٓ��v(800�~)�ł���B
�d�P���Ԃ̂ɂ���W�J���ɁA�C�Ԃǂ��Ƃ����ɂ߂ăV���v���ȍ\���B
���O�ɗ\�Ă������A�K���̂������������A
�����K��Ă���A�܂��Ɂu�C�̒j�v�Ƃ��������̕������n�߂��B
�܂��Ɂu�C�l�������w�O�ٓ��v�ł���B
����̎����́u�Â��v����{�Ƃ̂��ƁB
�u���̎������Ԃˁ`�v�ƌ����āA�Ԃ̂ɂ��������Ă����B
�T��������ƂŁA�T�b�Ɗ����B
�����A�w�̃x���`�ł��������ƁA
����ς蒼�����̋��͐V�N�A�������I
�����u����H�O�ɐH�ׂ����̂ƈႤ�c�v�Ǝv��ꂽ�������邾�낤���B
�����A�Q�N�O�̓~�A�����S�ݓX�Ŕ����Ă������̂Ɣ�r���Ă݂�B

��I���炩�ɉw�ّ��d�l�̕����A���Ă���͂����B
�ԂƊC�Ԃǂ����x�[�V�b�N�ŁA���Ƃ͑S���Ⴄ�B
�����A�{����o���Ă͂����Ȃ��B
���ꂪ�u����̕����v�Ȃ̂��B
���鉫��{�ɏ����Ă������B
����̃��j���[�́u�����ϓ����v�ł���ƁB
���̎��̏{�̂��̂��g���āA�ٓ������̂�����ٓ̕��Ȃ̂��B
�l���Ă݂�A��������������O�̂��ƁB
���ɍ����I�ł͂Ȃ����B
�ł��A���ۂɌ��n�ł��ٓ̕������Ƃ���l�͂���̂��H
�u���Ă݂�Ɓu�قƂ�ǂ͊ό��q�A���܂ɒn���q�v�Ƃ̂��ƁB
�������̕��H���A����ŕٓ��Ƃ�������u�S�O�O�~�v������Ƃ̂��ƁB
�킴�킴�{�̋��z���o���āA�����悤�Ȓn���̐l�͂��Ȃ��Ƃ����킯���B
���������̒������ɂ́A���ɂ��}�O���ȂǐV�N�ȋ���ނ�����A
�ԈႢ�Ȃ��A������ɖڈڂ肷��B
�Ƃ͂����A���{�œ�[�́u�w�فv�ł��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��B
���̃l�^�Ƃ��āA��x�͐H�ׂĂ݂�̂������Ȃ��B

�����̃����|�C���g�c�Ă�҂�����Ȃ��āA����

����̃��]�|�g�ȕ��͋C�́A�q���Ђ̃L�����y�[���\���O�ɂ����
��������Ă����悤�ȋC������B
�P�X�X�O�N�̂i�`�k�̉���L�����y�[���\���O�A
�ĕĂb�k�t�a�́u�Q����s�v�ł́A
�g�g�����N������Ł`�h�ƉS���Ă������A
�P�X�X�R�N�̂`�m�`�̉���L�����y�[���\���O�A
�X���痢�́u���̉āv�ɂ������ẮA
�g���߂��I����̊C�ɂ��悤�h�Ǝ��ɃX�g���[�g���B
���̂�������ƁA�m���Ɂu����A�s���Ă݂悤���ȁv�Ƃ���
�C���ɂȂ��Ă��邩��s�v�c���B
�������A���̏㐟�݂����������悤�ȃ��]�[�g���o�́A
��s�@����~�藧�����u�ԁA��C�ɑł��̂߂����B
�����b�Ƃ������ʂ̎��C�B
����ɂ̓��]�[�g�ȏ�̉���������Ɨ\�������Ă����u�Ԃ��B
���䂢���[���ōs���u�Ő��[�̉w�v�Ɓu�œ�[�̉w�v
��O�A����ɂ́A�������̓S�������������A
�푈�Ŕj�ꂽ��A���[�^���[�[�V�����̐i�W�ɔ����āA
���A�V���ɓS�����~����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�������A�ߔe�s�����͂��߂Ƃ����ʏa�͌������A
���b�V�����A�o�X�͒莞�ʼn^�s�����̂͂܂�B
���̑Ώ���Ƃ��āA�R�N�O�̂Q�O�O�R�N�W���A
����s�s���m���[���A�ʏ́u�䂢���[���v���J�ƁB
�����͂P�O���Ԋu�A���b�V�����͂V�`�W���Ԋu�ŁA
�^�s����A�s���̑��Ƃ��Ē蒅���n�߂Ă���B

����܂ōŐ��[�̉w�Ƃ����̂́A
�i�q�ł́A2005�N2���ɏЉ���u�����ہv�B
���S�i�R�Z�N�j�ł́A���Y�S���́u���т畽�ˌ��v�ł������B
���̗��w�̋L�^����C�ɓh��ւ����̂��A
�䂢���[���́u�ߔe��`�w�v�B
�ߔe��`�ɍ~�藧���āA�䂢���[���ɏ�荞�߂�
��C�ɍŐ��[�̉w�ɓ��B�B
����ɗ������Ƃ����C�����̕��������A
�Ő��[���B�̊��S�͂��܂�Ȃ��B
����ł����D���e�ɂ́A���m���[���̌`�Ɣ�s�@�̗���
�卪�����`�[�t�ɂ����Ƃ����Ő��[�̉w�̃��j�������g������B
���ł��A���̏ꏊ�͂��āA�卪���������������B

�ߔe��`����P�w�́u�ԗ�w�v�́A�u���{�œ�[�̉w�v�ł���B
�ߔe�s�X�̂��x�O�Ƃ��������ŁA
����͎w�h������̐���R�ɂ͓G��Ȃ����A
�w�O�ɂ͂����Ƃ����Δ肪�����Ă���B
�������ʂɌ������ꍇ�́A�����ŏ�芷�������������B
���܂��͗��j���w�т����A�`����
�������{�̈�n���ƌ������邱�Ƃ́A�܂��ł��Ȃ��B
�u���������v�Ƃ���������������B
���t�����y���H�ו����Ɠ����B
�u�����Ȃ�[�v�u��܂Ƃ�[�v�Ƃ������t������B
�������A����ɂ͂��̂U���܂Łu����v���Ȃ������B
���̂Ȃ������̂��A�����ł���ł��낤���B
���߂ĉ����K�ꂽ�̂ł���A
�܂��́u���j�v��m��Ƃ��납��n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����̗��j�I��Ղ̖ڋʂƌ����A���ƌ����Ă��u��v�B
���E��Y�ɂ��w�肳��Ă���B
�P�S�`�P�X���I�ɂ����đ��݂����u���������v�̒��S�������B
�u���������v�ɂ��Ă����炢���Ă����ƁA
�P�T���I�ɏ����ɂ���ē��ꂳ��A�o���������ł���B
�����̍����i���v�j���x�ɑg�ݍ��܂�A
�����́A���A�W�A�`����A�W�A�̒��p�f�Ղʼnh�������A
��̕ω��ɔ����āA�]�ˎ���̏��߂ɂ͎F���˂̑����ɂȂ�A
���{�ƒ����i���`���j�̗����ɏ�������W�ƂȂ�B
�����ېV��̂P�W�V�X�N�A������u���������v�ɂ���āA
���͓����ւ̈ڏZ��]�V�Ȃ�����u���������v�͋����I���B
�u���ꌧ�v�Ƃ��ē��{�ɕғ����ꂽ�̂ł���B
���̌��ւɓ�����̂��A���~�D�ɂ��`����Ă���u����v�B
���ۂɍs���Ă݂�ƁA�ӊO�Ə�����܂�Ƃ��Ă���B

�P�X�X�Q�N�ɕ������ꂽ��́u���a�v�B
�P�V�P�Q�N�ɍ���A���������ő�̖ؑ����z���������B
�������̂���́A�������痈���l�Ԃɂ́A
�u�ٍ��v�̊��o����A����������B
��O�ɂ́u����v�ɂ��w�肳��Ă������A
��ɓ��{�R�̎i�ߕ����u����Ă������Ƃ������āA
�P�X�S�T�N�R������̉����ŁA�قڔj��Ă��܂����̂ł���B

��߂��ɂ��问�������̕揊�u�ʗˁi���܂��ǂ���j�v�́A
���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B
�����������ő傫�Ȕ�Q�����̂ł��邪�A
�R�N���܂�̍Ό��������āA���Ƃ��C�����ꂽ���̂��B
����̕������ɂ́A�������ꂽ���̂������B
���R�́A�����ɂ���Ĕj��Ă��܂������߁B
�����������邾���ł��A�ۉ��Ȃ��ɐ푈�ɂ��čl����������B

���̐��h�����ĖƂꂽ�̂��u���钬�̐Ώ�v�̕ӂ肾�B
���^���̎���i1477�`1526�j�ɐ������ꂽ�A���悻300���̐Ώ�B
���ĕ��f���ꂽ�A���̃h���}�u����炳��v�ɂ��A
���̕ӂ�̏Z��g��ꂽ�B
�z�Ɋ����ēo��A��������Ƀ^�C���X���b�v�����悤�Ȋ���!?
���₩�ȍ��ےʂ���������A�o������̓��������Ă��������B

����̓��{�R�́A�P�X�S�T�N�T���ɂ͎邩��암�֓P�ނ��Ă����B
�A�����J�R���o���邾������ɓB�t���ɂ��Ă����āA
�{�y����܂ł̎��ԉ҂������邽�߂������Ƃ����B
�u����͎̂Đɂ��ꂽ�v
����ł͂�������ƌ��p����Ă���B
�����ōł��ߎS�Ȑ킢���s��ꂽ�암�ւ́A
�䂢���[���u�����w�v���̓ߔe�o�X�^�[�~�i������
�u�W�X�v�n���̎����s���ŁB�i�p�ɂɉ^�s�j
����̃o�X�́A�n�������G�ŕ�����ɂ����̂ŁA
�u�n���ԍ��v���o���Ă����̂��A��肱�Ȃ��R�c�̂P�B
����ł��s���Ȃ�A�^�]�肳��ɐu���ċ����Ă��炨���B

�u�Ђ߂��̓��v�ւ́A�����o�X�^�[�~�i����
����ɏ�芷���u�W�Q�n���v�̃o�X�ŁB�i�P���ԂP�{���x�j
�S���Ȃ������w�����M�̎莆�ȂǓǂ�ł���ƁA
�������܂�Ȃ��C�����ɂȂ��Ă���B
�n���̃^�N�V�[�̉^�]�肳��H���A
�u�H�����ς܂��Ă���s���ׂ��v�Ƃ̂��ƁB
�s���Ă���ł́A���炭�͐H�ו����A��ʂ�Ȃ��B
����t�͊w�Z���q���A���ꌧ�������ꍂ�����w�Z�̋��t�E���k�A
�Q�S�O�l���P�R�U�l���S���Ȃ�Ƃ����ߌ��B
�搶�ɂȂ낤�Ƃ������炢������A�^�ʖڂȖ������������̂��낤���A
����Ƃ������̂̋��낵�����B
�F�X�l���Ȃ��玑���ق����Ă����ƁA
�����Ƃ����ԂɂQ���Ԃ͌o���Ă���B

�߂��́u�쉮���i�����j���v�ɑ����^�ԁB
���̍��������m�A�E�͓��V�i�C���B
�����Ȃ���A���ɕ������Z�Ȍi�F�����A
���̒m�́A�ǂ��l�߂�ꂽ�Ђ߂��̏��w�����A
�A�����J����|��āA���疽�����Ă������n�ł���B
�u�Ђ߂��̓��v�̋L�O�قɂ��A
�߂��́u���ꌧ���a�F�O�فv�ɂ��A�u�s�q����ʂ��āA
����̗���ŁA�������̐푈�̌�������Ă���B
�����������茩��A����͂�����B
����ł����߂ĉ����K�ꂽ�̂ł���A�K���K�ꂽ���ꏊ�B
�X���[�������Ă��A���Ă͂����Ȃ��ꏊ���B
������̊C�֍s�����I

�h���v�������邪�A�܊p�A����ɍs�����̂Ȃ�A
�I�[�V�����u���[�̊C�����i���Ă��������B
����ɂ́A�����ȃr�[�`�����邪�A
���R���A�����̃^�N�V�[�̉^�]�肳��ɑE�߂�ꂽ�̂�
�ʏ鑺���ߓ��s�́u�V���i�݂��ς�j�r�[�`�v�B
�i�ߔe�o�X�^�[�~�i������́u�R�X�n���v�̃o�X�j
�R�R�͖����Ńm���r���ł��邩�炢���Ƃ̂��ƁB
�߂��ɂ́A�{�{���厁�̂��������B

�r�[�`����́A�C��̂��ʂ�������
�u�O���X�{�[�g�v(1500�~)���o����B
�����A�a���܂��ƁA�����̋�������Ă���B
�j���ŗL���ɂȂ����N�}�m�~�Ȃǂ�����A
���т��q�B���u�j���I�j���I�v�Ɗ�ԃV�[�����B

�Ȃ�����̊C�́A�����܂ŃI�[�V�����u���[���o��̂��H
�u���Ă݂�ƁA��͂萅���Y��Ȃ��Ƃɐs���邻�����B
����ɁA���ꂢ�Ȕ������l�̃r�[�`�͉����������邪�A
�V�R���l�H�����������@�́A�X��̌��Ђ̗L���ȂƂ��B
���R�̃r�[�`�ɂ́A�K���X��̌��Ђ������āA
�E���āA�Ƃ̕Y���܂ŐA�y�Y���ƕς��Ȃ��悤��
���u���o�����肷��Ƃ����B
���Ȃ݂ɉ���̎q���B�́A�C�����v�[���̕����D���ȂƂ��B
�C�ʼnj���̂́A������O�߂��Ă܂�Ȃ��A�v�[���ɍs���Ƃ����B
�q���̂T�l�ɂR�l���A�C���ʼnj�������Ƃ������Ƃ�������A
���Ƃ��A�ґ�ł͂Ȃ����I
������́u��O�H���v�������I
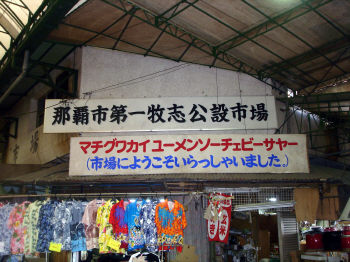

��ԃX�|�b�g�ł͂��邪�A�ߔe�̖q�u���ݎs��͖K�ꂽ���B
�썑�Ȃ�ł͂̐F�N�₩�ȋ��A�����ē̊�ʂɂ͖ʐH�炤�B
������ɐςݏd�˂�ꂽ���A���A��̐��X�B
�s��̊��C�́A�ƂĂ��u�A�W�A�I�v�ł���B
�s��Ŕ��������̂����̂܂ܒ������Ă��炤���悵�A
�����łȂ��Ă��A�Q�K�̐H���ŃI���I���r�[����A���Ў�ɁA
����̖��𖡂킢�������̂ł���B


�����āA����ł��y���������̂��u��O�H���v�B
�����������̂́A�^�N�V�[�̉^�]�肳���
�u�ߔe�ŐH�ׂ��肢���v�ƑE�߂�ꂽ�A
�����o�X�^�[�~�i���e�ɂ���u�Z���^�[�H���v�B
�g�����h����l�Ő萷�肵�Ă���悤���B
���j���[�����ăr�b�N���I
�قƂ�ǂ��T�O�O�~�ȉ��B
�u�S�[���[�`�����v���[�v�𗊂߂A
�R����̂��тƃX�[�v�܂ňꏏ�ɏo�Ă����ł͂Ȃ����I
���ɉ^�ׂA����ς�{��͈Ⴄ�I
�S�[���[�̋ꖡ����肭���a����Ĕ������I
����Ⴀ�A�N���W�O�O�~�̉w�قȂ�Ĕ���Ȃ��͂����B

�푈���m��Ȃ����A����܂łP�X�V�Q�N�̒i�K��
�u�Ȃ��A����͓��{�ɖ߂����̂��v�A�悭����Ȃ������B
�u���������v�Ƃ��ēƗ����Ă�������������B
���Â̐N���ŁA�F���˂ɍ�悳��Ă�������������B
�F���̍������āA����H��u�����v���B
���������Ŗ�������{�ɑg�ݍ��܂ꂽ�ߋ�������B
�{�Ó������̔��d�R���A���Ɋ������悤�Ƃ������Ƃ�����B
���{�R�ɏ]���āA���ǁA�����̂S�l�ɂP�l���]���ɂȂ����B
�����č����Ȃ��A���{�͍��h���A�����J�ɔC���āA
���_�̂S���̂R������ɕ��S���Ă�����Ă���B
�ČR�̌R�������������Ƃ͂����A����̑����̐l�́u���A�v��]�݁A
���A���Ă悩�����ƌ����Ă���B
�܂��A�悭����Ȃ��B
�P��s���Ĕ��邭�炢��������A��n�����o�ϓI�Ȗ���
�ȒP�ɃN���A�ł���̂�������Ȃ��B
�����炭�A������s���āA�����Ƃ����Ȑl�Ƙb�����Ă݂�ƁA
���������������̂�������Ȃ��B
���Ȃ��Ƃ��A�S�̂Ȃ����Ƃ���ԗǂ��Ȃ��B
���{�Ȃ��ǁA������ƈႤ����c�B
�܂��A�s�������Ȃ����B
�Q�O�O�U�N�V���Q�Q���i�y�j�j ���˕҇B

����ǂA�x�䌛��Y����́u��ҎE���̎���v�ɂ́A
�����̓��{�l�Ɍg�ѓd�b�����y�����̂͂P�X�X�V�N�Ƃ������B
�����A���͂܂��w���ł��������A�������������āA
�ƂĂ����C�ɂȂꂸ�A�������̂́A�m���Q�O�O�O�N����B
������A���͂̈��͂ɋ�����`�Ŏ�ɂ������Ƃ��L�����Ă���B
�����Ȃ��A���̌g�ѓd�b�́A�o��Ō��e�𑗂邽�߂�
�o�b�Ɍq������A�x���̘A���ɂ����g���Ă��Ȃ����A
���܂ɂ́A�d�g�̓͂��Ȃ����ŁA�q����Ȃ���т𖡂킢�����Ȃ�B
����(6��)���A�f�B���N�^�[�̊�F���f���Ȃ���A
�u�˔��I�Ȏd���͓���Ȃ��v�Ɠ���ŁA���A�����������ӁB
���[���h�J�b�v�̌����ƟT�������~�J�瓦��āA
�k���k�̔铒��ڎw�����Ƃɂ����B

�k���k�̌��ցE�i�q���k�V�����̔��ˉw�B
03.3���A04.9���ɑ����ĂR��ڂ̓o��ł���B
�V�����J�Ƃ܂ł́A��x���~�肽���Ƃ̖��������w�����A
�J�ƈȗ��A���x���g���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA
�����ɖk���k���g�߂ȑ��݂ɂȂ��������f����B

����������x���Ȃ��݁A���D�e�̔��X�B
�ŋ߁A�i�q�̃c�A�[�ł́u�w�ٕt���v�̂��̂��l�C�Ƃ��B
���ˌo�R�̏ꍇ�A���̔��X�ŃN�[�|�����ƈ���������B
�N�[�|���ň�����������̂́A��ԏ��i���肾���A
�c�A�[�̒��ɉw�ق��t���Ă���̂́A�L�����B
�����O���[�v���A���������Ă���p���ڗ��B

���A���˂ōł��H�ׂ����w�قƂ����R���I
�u��Ԃ̃}�O���Â��t�蘥�v(1680�~�E�g�c��)�B
���̑�Ԃ̃}�O�����A���ɉw�قɂȂ����B
�g��Ԃ̃}�O���́A�݂�Ȓz�n�ɍs�����Ⴄ�̂ł́H�h��
�v�����������A�z�n�֍s���̂͂����܂ł��u�啨�v�B
���̋K�i����O�ꂽ�u��Ԃ̃}�O���v�́A
�n���ł��������Ȃ��痬�ʂ��Ă���A
������t����`�ŁA�w�ى������������Ƃ����B
���͂������A�ؔ��ɓ������������i�i������A
���ʂ̉w�قɔ�ׂ�A���߂̉��i�ݒ肾���A
����ł������x�́A���ނ肪����B
�����w�́u�|�͖�v�ɂ��A�����̗ʂ����ׂ���̂ŁA
���˂܂ōs���@��̏��Ȃ����́A�����w�ł��Ђ��������c�B

�u�L�Ă��ɂ̑務�l�߂��v(1400�~)���A���АH�ׂ����B
�E�j���u�W�v���g�����w�ق́A����܂ŋL���ɂȂ��B
���A�̂́u�E�j�v��H�ׂ��Ȃ������̂ł��邪�A
�k�C���ŔZ���Ȗ��̃G�]�o�t���E�j��H���āA
���l�ς���ρA����Ȃɔ��������̂͂Ȃ��Ǝv���悤�ɁB
��͂�A�{��̂��͔̂������̂��B
���k�̑����m�݂́A�u�����T�L�E�j�v�̖{��B
�o�t���E�j�Ɣ�ׂ�A�������肵�����킢�ł��邪�A
�w�قł����܂ł���Ă����Ƃ͌����I
�ЂƂ܂����˂̉w�ق́A�}�O�����E�j�̓���Łc�B

�u�C���e�������v(1050�~)�́A���̐e�q���J�j�̈�i�B
���̏��i�ɖO�����炱��ȉw�ق������A�Ƃ��������B

�ŋ߁A�����i�H���������Ȕ��ˉw�قɂ����āA
��r�I�����ȁu����܂̗M�������v(630�~)�͋~�����B
���̂̂����T���}�ƗM�̍���́A�ӊO�ƃN�Z�ɂȂ�B
�����������Ȃ�A���킸�R���I

������f�ނ��X�g���[�g�Ɏg��ꂽ�w�ق��������A
�u�암�̉��߂��v(820�~)�́A
�C�N�w�ْ�Ԃ̂��Ɂ��ق��Ă��сB
���܂ɂ���ȉw�قɈ����ƁA�z�b�Ƃ�����c�B

�e�����Ŕ��ˉw�قɎQ�������u�j���[���v����́A
�u�����������O���v(850�~)�B
�����A���J���r�A���߂��̎O�_�Z�b�g�́A���M������̂Ȃ��B
���������w�قɖO���āA���ɓ���H�ׂ������́A
�I�����ɓ����Ă��邩���B
���̈���ŁA���ˁE�g�c���̉w�ق���A
���g�o�ł��A03�N3���Ɏ��グ���u���킵�̊��Ă��ٓ��v�Ƃ���
��ԉw�ق��A��N���������Ďp�������Ă���B
�g�c������Ɏf�����Ƃ���A��N�H�̏��i�������̌��ʂɉ����A
�C���V�̕s���ɔ������i���������R���������B
�����Ĕ������w�ق����������ɁA��ώc�O�ł��邪�A
�C���V�Ƃ������́A����g�������h�B
���ˉw�O�ʼnc�Ƃ��Ă���g�c���̐H���ł́A
���j���[�̈�Ƃ��Ďc���Ă���Ƃ������ƂȂ̂ŁA
���̓����A������]�݂����B
�����̃����|�C���g�`�������k���Ɣ��b�c�̔铒�߂���

���b�c�`�������`�\�a�c�̏d�v�ȑ��E�i�q�o�X�B
���ẮA�X�w����\�a�c���o�āA
�ԗ��̏\�a�c��w�܂ł̃��[�g�����������A
���͖k�����̐X�w�`�\�a�c�ΊԂ��u�݂����ݍ��v�Ƃ��Ďc��B
�܂��V�����̊J�Ƃɔ����A���˂���́u�����点���v���^�s�B
�X�w�`�\�a�c�ΊԂɂ͂Q���ԗL����
�u�X�E�\�a�c�t���[�����Ձv(4600�~)������̂ŁA
��~���J��Ԃ��̂ł���A���p�������Ƃ��낾�B
���u�i�q�o�X���k�v�z�[���y�[�W
http://www.jrbustohoku.co.jp/
�����R�Ƃ̈�̊��`�������k��
���������ŏ�����u�����点�v�Ɠǂ߂�l�͏��Ȃ����낤�B
�ł��A��x�����^�ׂA�����ēǂݕ���Y��邱�Ƃ͂���܂��B
����قǂ܂łɁA��X�̐S��ł厩�R�A���ꂪ�������ł���B

��ʂɁu�������k���v�Ƃ́A�\�a�c�̎q�m���i�˂̂����j����
���q���A���C���̗���A���ˁi�������ǁj���o�āA
�ĎR�i�₯��܁j�܂ł̖�P�S�L�����w���B
���ɐ��˂��璶�q���ɂ����ẮA����ɉ����āA
�V��������������Ă���A�E�H�[�L���O�R�[�X�Ƃ��Ē����N�ɐl�C�B
���s���鍑�������]�Ԃő���̂��u�����B
�����̂ł���A�����Ɗɂ₩�ȓo��ł͂��邪�A
����𐳖ʂɌ�����A���˂���q�m�������āB
�T�C�N�����O�ł���A�����Ɗɂ₩�ȉ���ƂȂ�悤��
�q�m������ĎR�����āA���点��̂����E�߁B
�i�����^�T�C�N���́A�lj������ŏ��̂ĉ\�j
���Ȃ݂ɍ���A���͎q�m������ĎR�������āA
�X�̒������]�Ԃŋ삯�����Ă݂��B

�q�m�����瑖�点��ƁA�ŏ��̃X�|�b�g�͒��q���B
���Q�Om�A�����Vm�̉������k���E�ő�̑�ɂ��āA
��������{���ɂ�����B��̑�ł���B
���̑ꂪ���邽�߂ɁA���͏\�a�c�ɑk�邱�Ƃ��o�����A
�\�a�c���_��ɕ�܂ꂽ�ɂȂ����B
��������͂ق�̏����������A�ƃ}�C�i�X�C�I����
�����Ղ�Ɨ��т�ƁA���̒��̌��Ȃ��Ƃ݂͂�ȖY�ꂻ�����B

�����Ō����̂��Ȃ��A���A���܂萫�i���悭�Ȃ��̂ŁA
�p���t���b�g��ό��ē��ƁA�����Ƃ̃M���b�v�ׂ�̂́A
�R��\���Ă銴�������āA���\�y�����B
�ł��A�������͂����Ӗ��Ŋ��҂𗠐��Ă��ꂽ�B
�������̏ꍇ�A�悭�얶�ɂ�錶�z�I�ȕ��i���f�ڂ���Ă��邪�A
�s���Ċςăr�b�N���A�R����Ȃ��A�z���g�Ɋς���B

�����l�ʼn������ɍs�������A�D�~�����|�C���g�́A
�u�������͂P�N��ʂ��āA�قڐ��ʂ��ς��Ȃ��v�Ƃ������ƁB
�u�k���̐^�ɂ�����ςĂ����B�ۂނ��Ă���ł���B
���̗ʂ��ς��Ȃ�����A��̐^�ł��ۂ��������v
�Ȃ�Ă��ƌ����A���Ԃ��犽�����オ�邩�A��ȓz�Ǝv���邩�B
�܂��A���ǂ̓P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�c�B
���Ȃ݂ɉ摜�́A�������k���̃n�C���C�g�u���C���̗���v�B
���A���́u�w�ٕG�I�сv�̎�ނŕ����Ă���ƁA
�P�Q�`�����l���̗��ԑg�̃N���[�ƁA���\�o���킷�B
���͂��̉摜�̒��O�܂ŁA�قړ����A���O���ŃJ�������Ă����B
�ŋ߂́A����ɂ���Ċς邱�Ƃ��o���Ȃ��A
�^����ҋ��Z�̃R�}�[�V�����ł��Ȃ��݂̒j�D�T�����A
������Ǝv����Ⴂ�����Ɠ�l���Ƃ����ݒ�̗l�q�B
���Ƀ`�����͘A��Ă��Ȃ������B
�������N�o�̂ʂ铒�ɂ�������Z���肽���`�J�n����

�i�q�����{�́u�тイ�v���U�v���A�悤�₭�P�l������
�u���܂ɂ́A�ЂƂ肽�сv�Ƃ������i���o���Ă��ꂽ�B
http://www.travel.eki-net.com/hitoritabi/index.asp
���͍���A���̃c�A�[���g���čs���Ă݂��̂����A
���̂����̈ꔑ���A�J���S�O�O�N�́u�J�n����v���B
�O��w�O�ɂ���Öq����n��̏h�ł��邪�A
�V������{�h��œs�������R���T��~���̂͊������B
�u�тイ�c�v�̃c�A�[�́A�ŏ��̂P�������Œ�ŁA
�A��̓��͂P�S����܂Ŏ��R�ɑI�ׂ�̂������B
���˂܂ŗ��āA�P���ŋA��ܑ͖̖̂������낤�B

�J�n����́A�����̍���Y���A�����̂����������I�B
������̕���Y���A�Â��悫�����̕��C���B
��O���R�W�x�̂ʂ铒�ŁA�������������S�Q�x�̂����B
�K�����肽���̂́A��O�̂ʂ铒�B
���ƌ����Ă��A�����N�o�̂����Ȃ̂��B
�����N�o�Ƃ������Ƃ́A�������ɂ���A
�N�����Ă̐V�N�Ȃ������n��������Ƃ������ƁB
�����Ɋ�肩�����Ă���ƁA���܁A�|�R�b�Ɖ��𗧂āA
�����Ƌ��ɔ�яo������C���A�w�ł�B
�����A���܂��I
�i���������A���ɏ����p���C������̂ŁA������͒j���p�B
�[���ɂ͈ꉞ�A�����p�^�C�����݂����Ă���j
���L�x�ȓ��ʂ̏����ꂢ�ȏh�`���q����

���̓����܂��A�i�q�o�X�Ń`�����̒j�D�T���ƈꏏ�Ɂc�B
�s�u�ǂ������ȃg�R�ŗ��ԑg������Ă��邪
����ς�A��Ԍ�����������̂͂P�Q�`�����l�����낤�B
�Ă��Ƃ́A���̘A�ڂ��g����ȃZ���X�����Ȃ��Ȃ��h�Ȃ��
����Ɏ���������Ȃ���A����ė����̂́u���q����v�B
�����̂����A�ĎR�̕ӂ�ɂ���u�������k������v�Ȃǂ�
��������Ă���قǁA�L�x�ȓ��ʂ��E���B
�h�̒��������ꂢ�ŁA�s��̐l�ɂ����܂�₷���B

�{���A�I�V���C�Ƃ������̂́A�L�x�ȓ��ʂ̏h������
�������ݔ��ł���Ǝv���B
�ŋ߂́u�Ƃ肠��������Ă݂܂����c�v�Ƃ������A
�I�V���C���ڗ������ɁA�C���C�����̂邱�Ƃ����邪
���ʂ������āA���A���R�ƈ�̉��ł���I�V���C�͑劽�}�B
���q�̐́A�J�n�����p���`�������邨���ł��邪�A
�������ƖX�̗̃R���g���X�g�������Ȃ���A���͋C�i�������B
�����͐^�����Ԃ���A����߂ĐS��S�J�ɂ��悤�B

��Ă�����Ύv���o���`��ƉS��ꂽ�̂́A
�����̃~�Y�o�V���E�ł��邪�A
�����~�Y�o�V���E�͔��������̂��̂���Ȃ��B
���b�c�̃~�Y�o�V���E���������B
�������牎�q����܂ŕ����ƁA�P�O���قǂ����邪�A
�r���A�E��Ƀ~�Y�o�V���E���Q�����Ă���G���A������B
����͂T�`�U���ɖK�ꂽ�҂��������\�ł���������B
�����b�c�ŋ��I�労���̓��`�Ӊ���

����A�Q���ڂɑI�̂́u�Ӊ���v�B
���A���̘A�ځA�ʂɕٓ�����h���炨�������Ă��Ȃ����A
��Ђ̂����ł��Ȃ��̂ŁA
�����s��������A�o���邾�������Ă���肾���A
���́u�Ӊ���v�����͍������c�A������^���邵���Ȃ��B
�吳���㌚�z�̕��i�̂��錚���A�ō��̂����A�����Ĕ������āI
�Q���ł�����Ȃ��A��T�Ԃ��炢�A���������h���B

�Ӊ������̂́A�S�Ă̕��C���q�o�E�u�i�ŏo���Ă��āA
�����̒ꂩ��{�R�b�ƗN���o�������N�o�̕��C�ł���Ƃ������ƁB
���Ɂu�v���̓��v�́A���ꂼ����Ƃ����A�܂�₩�ȋɏ�̓��I
�قڒ�����ph7�A�����܂Ŋ�тɐZ�邱�Ƃ��o���镗�C�͂Ȃ��B
��������吳�ɂ����Ă̍�ƁE�咬�j����
���̒ӂ̓����C�ɓ����đS���ɏЉ�B
�Ŋ��͖{�Ђ܂ňڂ����Ƃ������ꂱ�ݗl�������Ƃ����B
����悤�ȋC������B

�q�o�̗����ɐg���ς˂�ƁA���܁A�畆���`�N�b�Ǝh�������B
���̃`�N�b�Ɗ�����M�������A�����N�o�̏؍��B
�Ƃ߂ǂȂ��A�|��������铧���ʂ������B
����ł��Ȃ���A��ɓ��[�ɐQ�]���肽���Ȃ�B
�M�߂̊|�������̓��ɁA�Ђ��肵����C�������āA
�����V��߂Ă���A�g���S�������B
���ėǂ������A�������̂Ȃ�A���܂ł������ɋ������B
���[�����肪�����C�����ɂ����Ă���镗�C���B

�Ӊ���̋߂��́A�ӏ����͂��߂Ƃ��鏬���ȌΏ����_�݂��Ă���B
�V��������������Ă���A�����̉ΏƂ����̂��₷�̂��悵�A
���C�O�ɂЂƊ������̂��悵�A�X�̍����ԂɌ���鏬���ȏ���
���z�I�ȕ��͋C���������o���B


�����Ƃ����Ԃ̂Q���R���B
�A��Ȃ���Ȃ�Ȃ����������B
�u�J�n����v�̃c�A�[�ɂ́A���˂���̑��}���t���Ă��邪�A
�I�v�V�����ŐX�o�R�ɂ��邱�Ƃ��\�B
�i�q�o�X�́u�݂����ݍ��v�́A�����P�O�R���̃u�i�т��A
���b�c�̎R�X�߂Ȃ���X�w��ڎw���B
�r���A�u��l���C�v�ŗL���ȁu�_��������v�ŏ��x�~�B
�u��l���C�v�����ڂ���邪�u�܂イ�������v�Ƃ����������B
���́u�܂イ�������v�̂������ŁA
���̒n��̏����ɂ́A���킪���������Ƃ��H�H�H
������ɂ���A���b�c�ɂ͖��������ł��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��B

�X�`���ˊԂ́A�i�q�k�C�����������Ă���
�V�s�V�W�X�n�̓��}�u�X�[�p�[�����v�������[�B
���˂Őڑ����铌�k�V�����u�͂�āv�ɏ�荞�߂A
�R���Ԍ�ɂ́A�����ɂ���Ƃ����Z�i���B
�g�т̓d�g���͂��Ȃ��A�X�̒��̔铒�ʼn߂����Q���R���B
��������Ȃ�A���Ѓ`�������W���I
Copyright(C) 2005 Nippon Broading System,Inc,All Reserved.