
200�U�N�U��
�Q�O�O�U�N�U���R�O���i���j�j �����s��
���{���\����ό��n�E�����ɂ́u��ꃖ���v�Ƃ�����������B
��́A���́g���h�������̂��H
�����Ƃ���ɂ��A���Ɓu�_�l�v�̐킢�������Ƃ��B
�j�̎R�̐_�l�Ɛԏ�R�̐_�l���A���������T����
�����̗̓y�ɂ��悤�ƁA��ւƑ僀�J�f�Ɏp��ς��A
���������D����J��Ђ낰���̂��������B
���̓����ɍĂсu�킢�v���u������̂́A
�����Ǝ��オ���������a�R�O�N��B
�ΐ푊��́u���S�v�Ɓu�����S���v�������B
���S���i���ȏ��}�����ŏ�����}���̎ԗ��E�P�T�V�n�𓊓����A
���}�u�����v���𑖂点��A
�����S���́A���}�u������v�Ƀf���b�N�X���}���X�J�[�𑖂点�A
�݂��ɏ���ʁA����Ȑ킢���J��L�����̂ł���B
�����A�`���͂ǂ��炩�Ƃ������S�s���B
�F�s�{�ŃX�C�b�`�o�b�N���������邱�Ƃ��l�b�N�ƂȂ����B
���ǂ��̐킢�A���S���A�����N�����Ă����V�����J�ƑO�̓��C�����ɁA
�u�������v�̎ԗ���]�����������Ƃŏ�������B
�ȗ��A�����ւ̊ό��́A������u�����S���v�̓ƒd��ƂȂ����B
���������̏t�A���̓����ւ̃��[�g�ɁA
�u���j�I�ȕω��v���N�������̂ł���B

�Q�O�O�U�N�R���P�W���A�i�q�V�h�w�B
�����ł��������R�E�S�ԃz�[���ɂ́A�������̐l�B
�ړ��Ă͂��̓�����n�߂��A���}�u�X�y�[�V�A���ʂ���v���������B
�u�X�y�[�V�A�v�Ƃ́A�����S�����X�O�N����`���������A
�S�{�쉷��̊Ԃɑ��点�Ă��鎩���̓��}�d�ԁB
���S���g�����̐킢�h����P�ނɒǂ�����
�f���b�N�X���}���X�J�[�̌�p�ԗ��ł���B
���́u�X�y�[�V�A�v���A�Ȃ�ƍ��S�������p�����i�q�ɁA
�������A�i�q�����{�̖{�Ђ�����V�h�ɁA
���������āA��荞��ł����̂ł���B
�����ƓG���Ă����A�i�q�Ɠ����̎ԗ������Ԍ��i�́A
���̗��j��m��҂ɂƂ��ẮA���Ɋ��S�[��
��́u����̓]���_�v�ł��邱�Ƃ������������B
��������g�����h�ցB
�����ɁA�V���ȁu�i�q�E���S���ʓ��}�v���a�������B
�w�ٕG�I�сu�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����v�̃��X�g�́A
�����������E�����s�w�̉w�ق����Љ�B

����A�i�q�`�������ʂ̓��}�d�Ԃ́A�P���S��������B
�����A�P�������A�V�h�`���������Ԃ����ԁu�����v���B
�c��R�����́A�V�h�`�S�{�쉷��Ԃ𑖂�u���ʂ���v���B
�i�����Ԃ̏ꍇ�́u�X�y�[�V�A���ʂ���v���ƂȂ�j
���̂��߁A�������ʂ������ꍇ�́A
����́u�����v���������A���́u�����s�v�ŏ抷���ƂȂ�B
�������瓌�������܂ł́A���悻�P�O���B
�܂��ɁA�����̎�O�g���s�h�ł���B

�w���͍��s�ł��A�w�ٓI�ɂ́g�C�}�C�`�h�ǂ��납�A
�ō��ɋ����[���w�ł���B
����Ƃ����̂��A���́u�����s�v�̉w�ɂ́A
�����A�w�ق́u������v�����݂Ȃ̂ł���B
�����s�ɓd�Ԃ������ƁA�������̕�����
�u�ׂ�Ɓ`�A�ׂ�Ɓ`�v�̏a�����������B
���X��������[���T����̓d�Ԃ܂ŁB
��{�I�ɐ�(�V�h)���ʂ̓��}�E����������ė���
�z�[���ŗ�����������Ă���B
��Õ��ʂ̒��ʓd�Ԃ����鎞�ɂ́A����z�[���ɂ��o�v�B
���̉�Õ��ʂւ̒��ʓd�ԂƂ����̂́A
�����S���E���(�₪��)�S���E��ÓS���̂R�Ђɂ܂�������
���ʉ^�]�����u����(��ԉ���)�v�̂��ƁB
�����s�ŁA�������ʂƉ�Õ��ʂ̎ԗ���(����)����̂ŁA
�����ɂ킽���Ē�Ԃ���̂��B
���S�ɂ͒������A�ԗ��͂Q���̃{�b�N�X�V�[�g��
�́A���S�ő����Ă����}�s�d�Ԃ̂悤�Ȃ��肪�����B
�w�ق�����̊���C�ɂ��邱�ƂȂ��A���ɂ��邱�Ƃ��o����B
�ԓ��ɂ������̕��������Ă��āA�c�ɂ̏����ȉw�����C�t���u�ԁB
���ƂȂ��ẮA�ƂĂ��M�d�ȃV�[���B
���Ƃ�������t�ł��A���̐������甃�킸�ɂ͂����Ȃ��B

������Ŕ����Ă���w�ق́A�Q��ނ���B
�P�́u�����R������ƒn�{�ٓ̕��v(900�~)�B
�n�{�̏ƏĂ����R�̂ق��A���Y�̓�������������A
�n��F�L���ȕٓ��ł���B
�|�������O�����u�ԁA�Y���H�ނ̍���ɋ����B
�|�����Ƃ����̂́A���Ƃ����ʂ̐H�ނ������Ƃ��Ă��A
�ꗬ�H�ނɕς��閂�͂������Ă���B

������́A�u���̓��ٓ��v(900�~)�B
���̎d�o���ٓ��I�Ȏ��芴�Ɂu������v���i�i��^���Ă���B
����ɂ��Ă��A�ǂ�����u�X�O�O�~�v�Ƃ������i�ݒ肪�j�N�C�B
��~�D���o���āu���肪�Ƃ��v�̌��t�ƈꏏ�ɕԂ��Ă���S�~�ʈꖇ�B
�S��������Ɖ������Ȃ��u�B
�����͗����肩��w�ق����Ƃ����������y���݂����B
�l���Ă݂�ƁA�����s�ɂ͑f���炵�������������Ă���B
�@�u���̊J���d�ԂŁA�����肩��w�ق��v
�A�u���ѕR�������āA�|�������O���v
�B�u�{�b�N�X�V�[�g�ɑ��𓊂��o���ĐH�ׂ�v
���̎O�ʈ�̂����A�܂��ɉw�ق̐H�ו��́u�����v�B
�ł��w�ق��u���킦����v�������Ă���B
���a�̍��ɂ́A������O�ɑS���e�n�Ō����Ă������i�B
�����s�ɂ́A�܂�����B

���i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����V�u�������X�y�[�V�A���ʂ���v
�V�h����������������Ă����̂́A�����S���Ƃ����Ă���B
�Ȗ͑�����s�̔j�����A���Ɍ������o�ϏƂȂ����B
���̂�����A�ł��y�̂��S�{�쉷��B
�p�ЂƂȂ�������z�e�������ꂽ�B
����܂ŁA�����Ƃ����u����v�Ƃ����̂����ꂾ�����B
�������ڑ�����̂́A������Ɠs�c���̒n���S�̂݁B
�����̕��ɂ͍D�s�������A���������̐l�ɂ͍s���ɂ����ꏊ�������B
���̒��A�����������d�����ĂO�R�N�A�V�����E�i��w�������B
�܂��A�����S���ɂ́A�r�܂��N�_�Ƃ��铌��������������A
�������ʂƂ̗L�@�I�ȊW�͊F���B
�i�]�k�����A���̃��W�I�ŒʋΓd�Ԃ̏��`������ہA
�ɐ�����Ɠ�����̗A���w�߂��Ⴄ���߂Q�����̎�ނ���������B
�����������ł���Ȃ���A���̂��炢�W�͔����j
����A�i�q�͖��c������A���������̓d�Ԃ����x�����点�A
�ɓ��Ő��������u���߰�ޭ��x��q�v�̎ԗ��������������A
�قƂ�ǁA���݊����������Ƃ͏o���Ȃ������B
������A�����Ƃ����u�}�C�J�[�v�̈�l�����B
�Q�ЂőΗ����Ă���ԂɃp�C�̓h���h���������Ȃ��Ă����̂ł���B
���{���\����ό��n�E����������铌���S�����A
�����Ƃ��Ă����Ȃ��Ȃ����B
�����ŁA�����I�ɋy�ԑΗ��̊W�ɏI�~����ł��A
���ʓ��}�����点�邱�ƂŁA�i�q�Ɠ����͍��ӂ��݂邱�ƂƂȂ����B
�����}�u�����P���v��ԑ̌��L

�O��́u��������P���v�ɑ����āA�������̐V�h�B
�V���߂��̐V�h�́A�܂��{�i�I�ȃ��b�V���ł͂Ȃ��B
�u�����P���v�́A�V���P�Q���ɐV�h�w�̂R�Ԑ��Ԃ���B
�قڎ��������āA��Ɩk�ƕ������Ⴄ�Ƃ͂����A
�����V�h���u�i�q�E���S���ʂ̓��}��ԁv�����Ԃ���̂͋����[���B
�����\�ׂĂ݂�Ɓu��������v�́u7:15.10:15.13:50.17:44�v�B
����́u�����E���ʂ���v���u7:12.10:35.13:05.17:35�v��
�V�h�w�̔��Ԏ������߂����ԑтŁA�i�q�Ǝ��S�̎ԗ����A
�S������ܔ����ĉ^�s���Ă���_�����ʂ��B

�u�����P���v�ɂ́A�i�q�̂S�W�T�n�d�Ԃ��[�������B
�S�W�T�n�Ƃ����A���Ă̍��S���\������}�d�ԁB
�����傫�������A�����E�X�y�[�V�A���ӎ������h�����{���āA
����̒��ʓ��}�̐�p�ԂƂ����B
�ӋC����łR�Ԑ��ɍs���Ă݂���A
�܂�7:07���́u���c�G�N�X�v���X�v����Ԓ��B
�u�����P���v�͔��Ԓ��O��7:10���A�a�J������������Ă����B

�h�A���J���āA���Ȃ������قǖ��܂������Ŕ��ԁB
�T���قǂ̒r�܂ŁA�悤�₭�U�`�V���Ƃ������Ƃ��납�B
�����̑������������ڎw���l�́A�����đ����Ȃ��B
�����N�̃n�C�J�[�Ǝv����A�R�̎p�������l���ڗ����A
���ɂ́A�X�[�c�p�̃r�W�l�X�}��������ق�c�B
�Ȗ⎭���ȂǓȖ،����̓s�s�ւ̗p���q�̎��v�����肻�����B
������m�q�d�ɂ��ԓ��̔�������A�����ł��ǂ݂Ȃ���A
�R�[�q�[�ł��T���Ă���A�d���o�̋C���B
�����l�߂̏���Ԃ����ڂɁA�z���̏����D�z���ɐZ��邾�낤�B
�����ɂ��A�X�y�[�V�A�̍��Ȑ��ɍ��킹�����������āA
��l�̒j���ł��A�\���ɑ���L�����Ƃ��o����B
�����A���g�����Ȃ̕��ƍ����Ă��Ȃ��̂ŁA
�܊p�A�i�F���������Ă��A���g�ɓ�����g�n�Y���̐ȁh������B
�ŋ߂́A���Ȃ̎w��������@�ŏo����悤�ɂȂ������A
�@�B�Ɂu���g�v�̕\���͂Ȃ��B
���C���V�����Ȃǂł́A�P���ȂɂP�̑��ƌ��܂��Ă��邪�A
�ݗ������܂߁A�����̗�Ԃ͂Q�̍��ȂłP�̑��B
�ƂȂ�ƁA���E�̍L���ȂƁA�����łȂ��Ȃ����܂�Ă���B
�o���邱�ƂȂ�A���g�̏��J�������Ă�����
�w�����鎞�ɗL��̂����c�B
�u�����P���v�́A��{����F�s�{���i���k�{���j��ʂ�A
�r���̌I������A�V���ɐ݂���ꂽ�A������n���āA
�����������ɓ���A����������ڎw���B
�S�W�T�n�d�Ԃ͂��āu�Ђ�E��܂т��E�͂���v�Ȃǂ�
���̂ŁA���k�{���𑖂��Ă������}�p�ԗ��B
�i�q�ɂȂ��Ă�����A�H�c�s�́u���v��A
��Îᏼ�s�́u�����Áv�Ȃǂł��ڂɂ����邱�Ƃ��o�������A
�X�O�N�㏉���܂łɁA�����̗�Ԃ���삩����ŁB
��������A�ߋ��̘b�ƂȂ��Ă������A
����A��{�`�I���̂��悻�Q�O���قǂł͂��邪�A
�v��ʌ`�ŌÑ��ɋA���Ă��邱�ƂƂȂ����B


�u�����P���v�͒��W���O�A���E�w�́u�I���v�ɓ����B
�u�x��q�v�͈ɓ��A�u��������v�͏��c�Ƃ���
�u��ԉw�v�ŏ斱������サ�����A
�u�����E���ʂ���v�́A�����\�̏�ł͒�Ԃ��Ȃ�
�I���łi�q�Ɠ����̏斱������シ��B
���p��ł́u�^�]��ԁv�ƌĂ����̂ł���B
�A�����ɂ̓z�[�����Ȃ��A�h�A���J���Ȃ����߁A
���̗l�q���f�����Ƃ͏o���Ȃ����A�������Ă���ƁA
���斱�����������āA�d�Ԃ�҂���B

�斱���̌�オ�I����āA��Ԃ������o���ƁA
��u�A�ԓ�����퓔�����ɂȂ��āA
�������ɓ��������Ƃ�������B
�b���s���ƁA�E�ɑ傫���J�[�u���đ傫�ȓS�������ꂽ�B
�����������B��̃n�C���C�g�A������̓S���ł���B
���̋���n��ƁA���悢��k�֓��ɓ��������Ƃ���������B

�����A��������̂P���Ԃ́A������Ƒދ������B
�F�s�{���ɂ�������̂����A�c�����i�̒��𑖂邾���ŁA
�C���Ȃ���A����Ȃ��B
�����ӂ�ɗ���A�̂Ȃ���́u���~�X�v�̂���Ƃ�
�����邪�A�S�̓I�Ɋɂ���C�ɂ܂��B
���͉��x���A�X�y�[�V�A�ł��̋�Ԃ���������Ƃ����邪�A
�����Ԃ���K�ŁA���A������̓S������ƁA
�����Ă��A�������薰�肱���Ă��܂��̂��B
�������A���̃X�y�[�V�A�̂قƂ�ǂ́A
�S�{�쉷��Ɍ������u����(���ʂ���)�v���B
���̂悤�ȓ����D���ɂƂ��ẮA�����s�ł̏抷�����h���B
�X�y�[�V�A�́A���\�������́A���܂�ɐÂ��߂��āA
�����s�ɒ�Ԃ����̂ɋC�Â����A�C���t�������ɂ́A
�����s�̉w���o�Ă��܂��āA�S�{����ʂɌ������Ă���̂��B
���̏��߂����A�o�����邱�Ǝ��ɂR��B
�i�܁A���ʂ̕��́A�����ƒ��ӂ��ď抷����̂��낤���c�j
�o����A�����s�ƋS�{��s�ɕ������Ă����ƗL����A
�����I�Ɍ�������A�u�����s�N�����T�[�r�X�v�݂����̂�
����Ɗ��������̂��B

�K���u�����P���v�́A�������ʁB
�d�����[�^�[���ƁA���S�̐��H�𑖂�i�q�̎ԗ��Ƃ���
��������`���āA���܂薰�C���P���Ă��Ȃ��B
���������́A�i�q�����w�����ڂɌ��Ȃ��班�������ʒu�ɓ�������B
�i�q�̉w�����S�̐��H����A�i�q�̎ԗ��ɏ���Ē��߂�̂ɁA
�`���b�g���Ȋ��o���o�����̂́A�������ł��낤���B
�X���W���A�i�q�S�W�T�n�d�Ԃ́u�����P���v�́A
���������̍s���~�܂莮�̃z�[���ɂ������Ɠ����B
��芷���v�炸�A���悻�Q���Ԃ̗��́A�喞���ł������B
���ꑫ�����u���v�����߂ā`�����E��߂���
�����Ƃ����A���E��Y�Ɏw�肳��Ă���
���Ƌ{���͂��߂Ƃ���_�Е��t���߂���̂���Ԃ����A
���́A�����̎��R�𖡂키�ق����D���ł���B
�āA���ɑ��������̂́A�������߂āu��߂���v�B
���͓����ɂ́A�P�O�O�ȏ�̑ꂪ����Ƃ����B
���̒��ł��s���₷�������A�������Љ�悤�B

�g�b�v�o�b�^�[�́u���~(����ӂ�)�̑�v�B
���~�����֍s���r���ɂ����āA���e�䂩�璭�߂邱�Ƃ��o����B
�����̔������́A���ƌ����Ă��������o���B
�����܂ŊG�ɕ`�����l�Ȑ������o����́A�����Ȃ��B
���~�����s�̃o�X�́A�{�������Ȃ����߁A
�v��I�ɗ\��𗧂Ă��ق����������A�w����^�N�V�[�ʼn������āA
��߂鎞�Ԃ��Ƃ��Ă��A�R��~�ł��ނ肪����B
�d�Ԃ̑҂����킹���ԂɁA�`���R���ƍs���̂������Ȃ��B


�����Ă͓��Ƌ{���߂��āA����̎�O�ɂ���u�����̑�v�B
��̗����ɂ܂�肱��ŁA���������邱�Ƃ���A
���̖��O���t�����Ƃ������A���͊�̕���̂��߂ɁA
���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ��B
����ł��g���{��ɏo�Ă���悤�ȑ�h�ƕ]���B
�ƃ}�C�i�X�C�I����̒��Ŋ����āA
�����̑̂��A���R�̒��ɗn������ł����悤��
���o���o�����ł���B


�����āA���킸�ƒm�ꂽ�u�،��̑�v�B
���~�̑�A�����̑�ƁA���̉،��̑�����킹�āA
�u�����O���e�v�ƌĂԂ������B
�ł��u�،��̑�v�́A�ߒq�̑�A�ܓc�̑�Ƃ��킹�āA
�u���{�O���e�v�̈�ł�����B
�Ƃɂ����u�����v�̈��ɐs����B


���T�����o�āA���ɖK�ꂽ�̂́A
����͍�ƕ��ԍg�t�̖����u����(��イ��)�̑�v�B
�����̂����ԉ��̏������A������Ə�̕����������B
���炾��Ɨ��ꗎ�����Ȃ̂ŁA
��ꃖ�����������ɗ�����邩�A�o�X�̏ꍇ�́A
��Ɂu���v�o�X��܂ŏ���āA�ォ�牺��̂����E�߁B

�u��ꃖ�����������Ɂc�v�Ɛ\���グ�����A
��ꃖ��������Ă���ƁA���X�V�J(�j�z���W�J)�ɏo���킷�B
�����ł��A�V�J�������Ă��܂��đ�ς������ŁA
�A������邽�߂ɁA������ȂǗl�X�ȑ���Ă���B
�ړ��������ŖK��Ă��鏬�w���B�́A�쐶�̃V�J�ɑ�͂��Ⴌ�B
�ǂ��|���đ�ڋʂ�H����Ă��邿�т��q�������B
����A�����ɏo�v�����V�J���A�ǂ�������ꂽ�̂��X�g���X�ŁA
�����Ɏ���ł��܂����B
�쐶����������������A��͂�Â��Ɍ����̂��}�i�[�B
�摜�̃V�J�A���̌�A��ɓ����Đ����т��y����ł���A
�Ăтǂ����ɏ����Ă������B

���āA��͂�����̑�̐^�ł��́u����v�ł͂Ȃ��낤���B
������A���А�̓��ɖK�ꂽ���B
�����Ȃ܂Łu���̎��v�ɗ��ꗎ�����ɁA���������`������B
���̔��Ƌ�̐A�����ĐV�̃R���g���X�g�������I�B
�������̒��ɂ���@�ׂ��B
�����̖��͂́u���v�܂ŗ��Ȃ��ƕ�����Ȃ��B
����͂艷��́u���������v�I

���~�̑�܂ŏ悹�Ă�������^�]�肳��ɁA�킴�Ɛu���Ă݂��B
�u�����A�S�{��E�G�ň�Ԃ��������̓h�R�ł��傤�ˁH�v
�u����Ⴀ�A���������Ȃ��ł��傤�v
�����A�^���]�n�Ȃ��B
��͂�A�����ɗ�����u��������v�Ȃ̂ł���B
�����L�����Ղ�̔����̓��B
���̏�A��_���̏_�炩�������˔����A
������̔��̂��ׂ����́A�Ȃ��Ȃ����킦����̂ł͂Ȃ��B
�ꂾ������Ȃ��A�������ԉ��܂ŗ��Ȃ��ƁA
��Ԃ��������ɏo��Ȃ��̂ł���B

���������ɂ��A�����̏h������B
�ΔȂ�����߂��u�x�ɑ����������v�B
�X�S�N�̃I�[�v���ŁA���������ꂢ�Ő����B
�x�ɑ��̒��ł��l�C�������A��]�̓��ɗ\��ł��Ȃ����Ƃ��c�B
���������߂���A���₩�ɗ\�����ꂽ���B
�u��������v�̃o�X�₩��͑�������������̂ŁA
�`�F�b�N�C�����ԑтɂ́A���}�p�o�X���ҋ@���Ă���B
�܂����̂Ƃ���AFOMA�̌g�ѓd�b�͓���Ȃ��̂ŁA
���ӂ��Ă��������B�i��ꃖ���Ȗk�͌��O�j

���������̔����̓��������I�ȁu�x�ɑ��E���������v�B
�V�C���ǂ���A���V�̐���߂Ȃ���A�I�V���C���y���߂�B
��ɂȂ�Εӂ��сA���̉��ȊO�A�S���������Ȃ��B
���a�̍��A�l�͂܂���ɑ��āu�|��v�������Ă����C������B
���������̖�́A����Ȗ�ɑ���u�|��v���v���N�������Ă����B

���ʓ��}�̉^�s�J�n�ɍ��킹�A�����Ȃ����Ղ��o�ꂵ�Ă���B
�܂����u�i�q�E�����@�����E�S�{��t���[�������v
�����s�������V�W�O�O�~�Ƃ������i�́A
�V�h�`���������Ԃ𐳋K�̒l�i�ʼn����������z�ƂȂ�B
�܂�o�X�ɏ��A��������Ƃ������Ƃ��B
�����A�������ʂŎc�O�Ȃ̂��A�����o�X�̃t���[��Ԃ�
���T������i�،��̑�j�܂łƂ������Ƃł���B
�o�X�����~�肵�����G���A�́A���T�������ɑ����B
�u�i�q�E�����@�����E�S�{����������v������B
�O���܂ł̍w���ŁA�����s�������͂U�O�O�~�����ƂȂ�B
�Г������ł������Ƃ����̂͒������B
���āA�ȑO���Љ�����Ƃ����铌���́u�t���[�p�X�v�ł��邪
���N����A��������������Ȃ����B
�u���܂܂ɓ����@�����t���[�p�X�v�́A�Q���ԗL���A
����S�S�O�O�~�ŁA��������܂ł��J�o�[���Ă���B
���Ƃ��ẮA�����܂ŏ����܂ň����s�������̂ƁA
�ς킵�����K�̎x��������������v���ŁA
������Ɨ��Z���g���Ă݂邱�Ƃɂ����B
�����E�S�{��Г�������(3300�~)�œ����āA
���O�w�����Ă����������̃t���[�p�X(4400�~)�����p�B
�V�h�`���������`��������`�Ɖ��̂��B
�A��́A�x�����ԑсi�銄�j�̃X�y�[�V�A���g���A
1000�~�̒lj��ŁA�A�邱�Ƃ��o����8700�~�ŏオ��B
���T�����瓒������܂ŁA�o�X��840�~�����艝��1680�~�B
���~����J��Ԃ��A����ɍ����Ȃ�͓̂��R�B
��~���X���[�Y�ɐi�ށB
�i�A���A�i�q�E�����̕Г������Ղ́A�V�����Έȍ~�̐ݒ肪
���\����Ă��Ȃ��B�J�ʋL�O�̓��ʃf�B�X�J�E���g�Ƃ����Ӗ��ŁA
���̂܂ܔ������I���\��������j

�����E�S�{��ɐV���ȕ������J�����u�i�q�E�����̒��ʓ��}�v�B
���ꂩ��A�܂��܂��̃u���b�V���A�b�v�����҂���邪�A
�܂��́A����ďo�����Ă݂����B
�Q�O�O�U�N�U���Q�R���i���j�j ����
���{�ōł���~�q�������w�E�V�h�B
�i�q�ɉ����A�����E���c�}�E�n���S�e����������A
���b�V�����݂̂Ȃ炸�A�펞�l�ł��ӂ�Ă���B
���̂����i�q���́A�P�Ԑ��`�P�S�Ԑ��܂Ŕ������Ă��邪�A
�R����O���ƒ������e�w��Ԃ̉���z�[���ł���
�P�R�E�P�S�ԃz�[���́A�ǂP�u�Ă�������́A
���c�}�d�S�������̃��}���X�J�[���������Ă���B
�������P���Q��A���c�}���̃z�[���̂͂��Ȃ̂ɁA
�u�i�q�}�[�N�v���f�����ԗ�������̂������邱�Ƃ�����B

�u���}���X�J�[�v�Ȃ̂Ɂu�i�q�v�c�B
���͂���A�u��������v���ƌĂ����}���}���X�J�[�B
���c�}���͌��X�A�V�h�Ə��c��������ł��邪�A
�r���A�V���c�̎�O�ɂi�q��a����Ƃ̘A����������B
���̐��H���g���ĐV�h�`���ÊԂɂP���S�����^�s����Ă��āA
�����u�Q�E�R�E�U�E�V���v�̂Q�����ɂi�q�ԗ����[�������B
�������A���́u�i�q�v�́A�����i�q�ł��u�i�q���C�v�B
���c�}�ƃ^�b�O��g�ނ��ƂŁA�i�q���C���Ǝ���
�ɓ��ւ̐V���[�g���J���A����I�ȓ��}�Ƃ�������B
�����Łu�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����v�̑�Q�e�́A
���c�}�`�i�q��a����ʂ���u��������v���ŁA
���ɓ��̌��ցE���Â�ڎw���B
�܂��́A�i�q���C���{���E���Éw�̉w�ق����Љ�B

���ẤA�É����������\����X�B
�w�͐̂���@�悪�u����Ă����A�S���̗v�Ղł�����B
���݂��A��a����E�g�����̎ԗ��̐������s���Ă���ق��A
���[�𒆐S�ɁA��������O���[���ԕt�̒����Ґ���������A
���Â�Q����ɂ��Ă���B

���C�����E���{�Á`���ÊԁB
�����m�̕��������Ǝv�����A���a�X�N�̒O�߃g���l���̊J�Ƃ܂ł́A
���̌�a������A���C�����������B
���C�������̂܂ܒH��A�����̎R���z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�ł��A�����̋Z�p�ł́A�ƂĂ������Ȃ��ƁB
�i���ł��A�����o�R�S���ɂ̓X�C�b�`�o�b�N�����邭�炢�c�j
�����ŁA�����͌��z����邢��a����̃��[�g���̗p�B
�����Ƒ������ԑ哮���E���C�����̊J�ƂɎ������̂ł���B
����ł��A���̋�Ԃ̑��s�ɂ́A���C�@�֎Ԃ������P���K�v�������B
�����̂��߂ɁA��Ԃ̒�Ԏ��Ԃ͕K�R�I�ɐL�т��B
��Ԏ��Ԃ�������A�w�ٔ�����ɐ��B
���̔����z�������A���Âʼnw�ق����W�������R�Ƃ�����B
�V�����J�ƈȍ~�́A�O���w��������̒��S�ƂȂ������A
���Ȃ��A�{���n�E���Âɂ����Ă��u�������v�͌��݁I
���V�������V���܂ŁA���D���o�ĉE�̔��X�ŁA
�O���ƕς��ʃ��C���i�b�v����葵���A�w�ق������Ă���B

���C���e�w�̉w�ٓ��l�A��̂ł�Ԃ��g�����u��߂��v�ł��邪�A
���M���ׂ��́A�ł�Ԃ��ʐ��ƂȂ��Ă��邱�ƁB
�܂�A�D�݂ɍ��킹�āA�ł�Ԃ̗ʂ߂ł���̂��B
�V���v���Ȓ��ɁA�����₩�ȐS�����B
���C���������̒��ł́A�ł��D���ȁu��߂��v�ł���B

���āA���{�ōł������S�����Ƃ����A
�x�m��̉͌��ɂ����铌�C���V�����̕x�m�싴���������B
���̋��̋߂��̉͌��́A�t���珉�Ăɂ����āA�Ԃ����܂�B
���͂����ŏx�͘p�Ő��g�����ꂽ�u�����сv�̓V��������
�s���Ă���̂ł���B
���́u�����сv���ӂ�Ɏg�����w�ق��u�����т߂��v(1000�~)�B
���т݂̂Ȃ炸�A�����g���ɂ��u�����сv�͂����Ղ�B
�����т̖��͂��A�w�قŖ��i�ł���Ƃ����̂͊��������肾�B

�É��ł��Ȃ��Ƃ����ƁA�l���̂��Ȃ����v�������ׂ�����������A
���́A�O�����u���Ȃ��v�������ł���B
���j�I�ɂ��A�]�ˎ��ォ��u�O���̂��Ȃ��v�͒m���Ă��āA
�x�m�R�̗N�����ň�������Ȃ��́A��i���Ƃ��B
���̂������A�w�ق́u�������Ȃ��v���u�P�T�O�O�~�v�ƁA
���Ȃ��w�قƂ��Ă͌��\�A�l���͂������́B
����ł��A��x���키���l�͂��肻�����B

�u���Ƃ�܂̂����v(850�~)�́A���Âł͐V�����w�فB
���X�ł́u���āi����܂��j�ٓ��v�ƕW�L����A
�ɓ��E�C�P���́u���Ă̗��v�ɂ����āA���_��ō͔|���ꂽ
���Ă��g�p���Ă��邱�Ƃ��A���͂ɃA�s�[�����Ă���B
���������u���āv�Ƃ́A�I���O�A�����E���̎���ɔ������ꂽ�āB
���̒����c��Ɍ��コ��A���N�ɂ������Ƃ��B
����Ȃ��Ƃf���āA�w�َ��̂��w���V�[�Ȃ���B
�����݂̂Ȃ炸�A�����܂�肪�C�ɂȂ�j���ɂ��s�b�^����!?

���Âɂ́A�����Ŗ��킦��w�ق��Q��ނ����āA
�P�́A�O�S�N�R���Ɂu�O���ҁv�Ƃ��ďЉ���u�邿�炵�v�B
�ŁA�����P���A���́u�n�{�ǂ�v(680�~)�B
�ȑO(04�N)�A�w���������́A���Z�싅�̒n��\�I��
����(��������)����ɂĔ̔�����Ă������̂��������A
���̌�A�{���ڂ낪������ꂽ�͗l�B
�J�W���A���Ȋ��o�ŐH�ׂ���w�قł���B
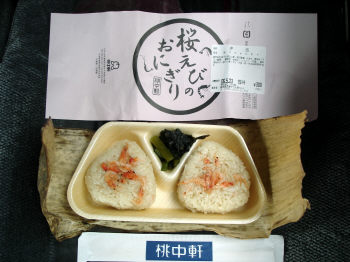
�J�W���A���Ƃ������A�����͂o�ł��������Ȃ̂�
�u�����т̂��ɂ���v(300�~)�B
�R���r�j���ɂ���Ƃقړ����l�i�ł���Ȃ���A
���I���ꂽ�����т��������ǎ��̂����ŁA
�����グ�Ă���Ƃ̂��ƁB
�u��������P���v�ŁA�X���߂��ɏ��Âɒ�������A
���̂��ɂ���ŏ��������āA�ɓ��Ɍ����������B

���Ȃ݂ɁA����A���ÁE�O���̊Ŕw�قɂ��āA
���c�}���}���X�J�[�ł��ԓ��̔����s���Ă���u�`����齁v�B
���́A�S���`�U�����{�ɂ����āu�t����Łv�������Ă���B
�������قǏЉ��A���ɓ��E����́A
���{�ɂ�����u���̗t���ρv�̐��Y�̂��悻�W�����߂�B
�I�I�V�}�U�N���ƌĂ���ނ̍��ŁA���݂̑����ɂ�
����Y�̗t���g���Ă���Ƃ����̂����A
���̍��̗t���g���āu�`����齁v������Ă���̂��B
�ʏ�o�[�W�����Ƃ͈ꖡ������u�Â��v�Ɓu����v���A
�t�̃E�L�E�L�����C�������������Ă�B
�c�O�Ȃ���A���N�̔̔��͏I�����Ă��܂������A
�t���珉�Ăɂ����ĖK���ۂ́A���Ѝw�����ꂽ���B

�����w����́A�ɂ��܂�R���ň��ނ��Ă��܂���
�݂���F�̓d��(113�n or 115�n)�ł��邪�A
���C�����E�M�C�`�L���Ԃł́A���������Ŋ������ł���B
���̋�ԁA�w�ǂ��e�w��Ԃł��邪�A�P�O�`�Q�O���Ԋu�ʼn^�s����A
���C���̊X�������ɂ��A�����\�͂܂�����Ȃ��B
�����A�����ɂ��߂������A�V�^�ԗ��̓������v�悳��Ă���̂ŁA
�w�ق�H�ׂȂ���A�̂Ȃ���̋D�ԗ����y���݂������́A
�ǂ����A�����ڂ̌v����c�B
�����̃����|�C���g�c�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����U�u��������v
���}�u��������v�����^�s���J�n���āA�������̂łP�T�N�B
�������A���c�}�ƌ�a����̏�����ƂȂ�Ǝ��ɔ����I�̗��j������B
�P�X�T�T(���a�R�O)�N�A�u���v�Ɓu���u�v�Ƃ����f�B�[�[���J�[���A
�^�s���J�n�A�P�X�U�W(���a�S�R)�N�̌�a����d���ɔ����d�ԉ��ŁA
�V�h�`��a��ԂɁu��������v�Ƃ����}�s��Ԃ��a�������B
���̍��A���c�}�́A��a��Ɂu���c�}��a��t�@�~���[�����h�v�A
��Ԗ��̗R���ƂȂ����A�x�m�R�[�̒��������ɂ�
�u���c�}�Ԓ��R���v�Ƃ������W���[�{�݂��I�[�v�������Ă���A
�����ւ̃A�N�Z�X��i�̂P�Ƃ��āA
��Ԃ̉^�s���s��ꂽ�ƍl����̂��A���ʂ�������Ȃ��B
���̌�A�[������Ă������}���X�J�[���V�����������Ƃ�A
�܂���a������A�i�q���C�̘H���ƂȂ������Ƃ��A
�u��������v�̏��É��L�ƁA�V�Ԃɂ����}�i�グ�A
���c�}�E�i�q���C�̑��ݏ����ꂪ�����B
�P�X�X�P(�����R)�N�R���̃_�C����������A
���}(���}���X�J�[)�u��������v�Ƃ��āA�V�h�`���ÊԂ��A
�P���S�����A�ő��P���ԂT�P��(�y�x��7��)�Ō���ł���B
����u�t�@�~���[�����h�v�́u��a��v���~�A���A�E�g���b�g�v�ɁA
�u�Ԓ��R���v�́A���{��w�̌����{�݂ɂȂ������A
�u��������v���́A�A�E�g���b�g�A�x�m�R�ւ̃A�N�Z�X�A
�����āA���ɓ��ւ̃A�N�Z�X��ԂƂ��Ă̖�����S���Ă���B
���V�h�`���ÁE�Q���Ԃ̗�

���V���߂��̏��c�}�V�h�w�B
�u��������P���v�́A�V�h���V���P�T��(�y�x��7:20)�̔��ԁB
�V���̔������{�s���ɑ����A����Ԏ�̃��}���X�J�[�ł���B
���̃��b�V���ɂ����邱�̗�Ԃ́A���Ò����X���Q�R����
���v���Ԃ���������A�g�[�^���ł͏��Â܂ł��悻�Q���ԁB
�����`�Ђ��荆�`�O���抷���ł́A�P���Ԃ�邱�Ƃ����邵�A
�V�h����i�q�̏Ó�V�h���C���̓��ʉ��������p���ł��A
�P�T�����x�����������x�����A���K�Ȏԗ��Ŋ����A
�������A�抷�s�v�Ƃ����̂������b�g�ł͂Ȃ����B

����Ԃ́u��������P���v�ɂ́A
���c�}�E�Q�O�O�O�O�n���}���X�J�[���[�������B
���̎ԗ��A��{�I�ɂ́u��������v����p�ł��邪�A
�����A�������{�s�ɂ��g�p����Ă���A
�����ւ̃A�N�Z�X�ł����ڂɂ����邱�Ƃ��o����B
�ԗ��́A�V���Ґ��̃n�C�f�b�J�[�B
�܂�˂̔������ƁA�P�i�̊K�i������B
�J�[�y�b�g���~���ꂽ�Â��ȋq�����֓����Ă�����
���N���C�j���O�͂������A�����S�n�̂������Ȃ����R�ƕ��ԁB
��͂葼�Ђ֏�����Ă����Ŕ��i�̃O���[�h�͍����B
�܂��A�R�E�S���Ԃ͂Q�K���āB
�Q�K�����́A�i�q�ɕ���ĉ��R��́u�O���[���ԁv�ƂȂ��Ă���B

����ɑ��Ăi�q���C����́A�R�V�P�n���}�d�Ԃ�������Ă���B
�ԓ��͋��ʂŁA�R�E�S���Ԃ͓������Q�K���Ăł��邪�A
�n�C�f�b�J�[�ł͂Ȃ��A�i�q���C�炵���u���C�h�r���[�v�ȍ��B
���ʂɍ��|���Ă��A�ڂƉ��̑��g�����s�ɂȂ鑋�̑傫���B
�V�C�̂������ɁA���̍L��������x�m�R�߂邱�Ƃ��o������A
�����A�s�ςł��낤�B
�����A�i�q���C�̊Ŕ������P�O�O�n�V�����̍ݗ����łƂ������A
��͂葊�ݒ��ʉ^�]�ɂ�����ӋC���݂��A�Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���ԗ��B
�O�b�h�f�U�C����܂��[���B
�����c�O�Ȃ��ƂɁA�P�Ґ������Ȃ��B
�����ȂǂŁA��قǂ̏��c�}�Q�O�O�O�O�n���㑖���邱�Ƃ�����B
�u��������P���v�́A�V�h���o�Ē��c�E�{���ƒ�Ԃ���B
�����̋q�w�́A���ɗl�X���B
���c�E�{���܂ŁA�t���ʂ̒ʋE�ʊw�Ƀ��}���X�J�[�𗘗p����l�B
�O��A�����փn�C�L���O�ړI�̐l�B
�����ɂ����K�͗쉀�֕�Q�Ɍ������l�B
���R�A�A�E�g���b�g�ړI�̎�҂�����A
���������̍H��֏o���Ɍ������l�B
�����āA���̂悤�ɁA�ɓ����ŏI�ړI�n�̐l�B
�������ǂ̐l���A���b�V���ɝ��܂����ʋΓd�Ԃ����ڂɁA
�ԓ��̔��Œ����R�[�q�[�ȂǕЎ�ɁA
�����ɖڂ�ʂ�����ƁA�Ȃ�ƒ��̗D��ɂ��ėL�Ӌ`�ȂЂƎ��B
���̉��胍�}���X�J�[�́A�N�Z�ɂȂ肻���ł���B

���āA���}���X�J�[�ł���̂ŁA�E���͉��ƌ����Ă��O�ʓW�]�B
�W�]���͂Ȃ��܂ł��A�擪�ԗ�����͌i�F���h���h����э���ł���B
�V�h���o�ĂP���ԂP�O�����܂�B
�u��������v���́A�V���c�̎�O�ŏ��c�}���ɕʂ�������A
�������������A�����Č�a����̘A�����ւƓ����Ă����B
���̋}���z�̐��H���g����̂́A��{�I�ɂP���ɂW��B
�u��������v�������鎞�����ł���B
�X�s�[�h�͂��Ȃ�������ŁA�����邨���鑖���Ă��������B
�O��̂i�q�ɓ����E�ɓ��}�s���̒��ʉ^�]�Ƃ͈���āA
�����ł͒��ʉ^�]�ő̊��ł��銴�����B

�E�}�J�[�u���ĘA������n���ƁA��u�A�ԓ��̋��~�܂�A
���c�}������i�q���ɓ��������Ƃ��킩��B
�Ԃ��Ȃ��A��a������c�w�̂P�Ԑ��ɒ�Ԃ��āA
���c�}����i�q���C�ɏ斱�������B
���ẮA���c�}�̏斱�������̂܂斱���Ă������A
���ݏ�����ƂȂ����P�T�N�O����́A���̌��i������ɂȂ����B
�݂��Ɍh�炵�Ĉ����p���l�q�́A���Ȑ��X�������o����B

��a����ɓ���Ɓu��������v���̓��[�^�[�����グ�ĎR�o��B
�ԑ��͎R�Ԃ̃��[�J�����Ƃ���������B
���H����������P���ƂȂ����B
���̂��߁A�w�ɓ��邽�тɌ����Ɖ������J��Ԃ��B
���͂��̉����������A��̐푈�̏��Ղł���B
��ɐ\���グ���ʂ�A��a����͂��Ă̓��C�����B
�����́A��������ł������B
��������a����ƂȂ��Ă���A�틵�������B
�Е��̐��H�́A�s�v�s�}�Ƃ������Ƃł͂�����A
�푈�p�̎��ނƂ��āA���o����Ă��܂����̂ł���B
�u��������v���̎ԑ�������A
���܁A��������̋���g���l���̐Ղ����邱�Ƃ��o����B

�u��������v���́A��a��܂łɂ��q����̑��������낵�A
�I�_�̏��Â�ڎw����q�́A�����đ����Ƃ͂����Ȃ��B
����ł��A��a�ꂩ�玩�R�ȂƂ��ĊJ�����ꂽ�U���Ԃɂ́A
�R�P�O�~�Ƃ��������Ȓlj���������`���āA����Ȃ�̏�ԁB
��������́A���S�ȎR����B
�W���S�T�O���[�g���̌�a�ꂩ��A�O���[�g���߂����Â܂ŁA
�W�]�Ȃ���́A�R�������Ă���l�q����ڗđR�B
���[�^�[��X�点�邱�Ƃ��Ȃ��A�y�₩�ȃ��X�g�X�p�[�g���B
�x�m�R�̕��������W�߂�������̓S����n��A
�Ԃ��Ȃ��I�_�E���Â̓��C�����z�[���Ɋ��荞�ށB
�Q���Ԃ̗����A�ЂƂ܂������Ŋ����B
�����ɓ��ʼn���O���E�H�O��
�ɓ������́A���Ɛ��ł����ԕ��͋C���Ⴄ�B
���S�Ɋό��n�̓��ɓ��B
����ɔ�ׂāA�܂������̕��͋C���₷���ɓ��B
翂т����͋C�𖡂킢������A�ԈႢ�Ȃ����ɓ������E�߂��B

���ɓ��ɂ������ʎ�i�̓o�X�B
�u��������1�3�v���ɐڑ����āA���Éw�o�X�^�[�~�i��(4��)����
���C�o�X�́u���ɓ����}�o�X�v�i�\��s�v�j���������Ă���B
�P������́A9:40���́u����E�������p�فv�s���ڑ��B
�o�X�͎O���w�ŐV�����̏�q���E���āA
���悢��A���ɓ��̃o�X�����X�^�[�g���B

���ɓ��̊����E�����P�R�U�����B
�O������A�ɓ��̍��s��ɓ��s�ȂǁA�悭������Ȃ����O��
�Ȃ��Ă��܂����B�R�E�C�P�����o�āA����������D�����z���B
���̓����z����ƁA���悢�搼�ɓ��B
���}�o�X�Ƃ͂����A�O���`�y��Ԃ͂P���Ԕ��߂��B
���\�A������Ȃ��Ƃ������o�ɂȂ�B

����́A���ɓ��̋�������������Ă����B
�g�b�v�o�b�^�[�́A�y��(�Ƃ�)����́u�ٓV�̓��v(500�~)�B
�n��̏W��̂Q�K�ɍ��ꂽ��������ŁA
�������Y��Ȍ����������I�ł���B(��Q��S�Ηj�x��)
���ʂ̃o�X�Ȃ�u�y�싙���v���Ŋ�̃o�X��B
���}�o�X�ł́A�y��̂P��O�u���l�v�ō~�肽�����߂������B

���ʂ̗����ƁA�����蔲���ꂽ�`�������I�V���C�̂Q��ށB
�ǂ�����A�����đ傫�ȕ��C�ł͂Ȃ����A
��̍��肪�Y�����ł̓����݂͊i�ʁB
���ɂ��������̘I�V�͖��͓I�ł���B

�u�ٓV�̓��v���ǂ��炩�Ƃ����A�ό��q���ӎ�����
���C�ł���̂ɑ��u��������v(300�~)�́A
�n���q�D��Ƃ��������̋�������B
����߂��̏��X�œ��������ē�������ȂǁA
�T�^�I�ȉ����̕��͋C�𖡂킦�A���R�Ɨ�������܂��Ă���B

�y��̉���́A�c�O�Ȃ���W���Ǘ��ɂȂ��Ă��܂��Ă��邽�߁A
�������ꂲ�Ƃ̐̈Ⴂ�𖡂키���Ƃ͏o���Ȃ����A
�V�N�Ȃ������A��ɗ������炠�ӂ�Ă���̂��������B
�Ƃ�킯�u��������v�́A�ƂĂ��M��������������Ă���B
���P�Q���̈�ԕ��C��_���Ă����ƁA�K���ɂ�����l�B
�u���ł��߂Ȃ��Ɠ���Ȃ���v�ƊǗ��l�Ɏw������đ��������B
�o����A�������Ȃ��œ��肽�����̂����A����͖������B
���悢�M���ɂ��āA�C���̂����������������\�B
���R�̌b�݂��A���̔M����ʂ��āA�̂ɐ��ݓn�銴��������B

�y��̃o�X����o��ƁA���R����l���Ƃ������ό��n�������B
���l���Ȃ�Ă̂́A�W�O�N��܂Łu����v�Ƃ������ʂ̖��������B
�����̂���̓`�����g���A�m�g�j�̒��̘A�h���ʼn����A
�ό��n�������̂����A�܂��A�悭����オ���Ă�����̂��B
���̓X���[���āA���E��Α��̃G���A��ڎw���B
�y��`�������Ԃ́A���Њe�w��Ԃ̃o�X��I�т����B
���̋�ԁA�����P�R�U���̃o�C�p�X����������Ă��邪�A
�e�w��Ԃ̃o�X�́A��Ԑ��̋������o�R���čs���B
���ɉF�v�{�E���Ǘ��E�c�q�̕ӂ�́A�̂̋����̕���c��A
�Â��ȓ��]�ɉ����đ���ȂǁA���[�J�����[�h���ځB
�����́A�R�O�`�S�O���ɂP�{���x����ė���̂ŁA
�C�ɓ������X�|�b�g������A�C�y�ɓr�����ԏo����B


�����́u�F�v�{(������)�v�̃o�X��̋߂���
�m��l���m��u�O���H���v�Ƃ����L���X������B
�����̖����́u���c�E������齁v(10�J���E1300�~)�B
�܂����J�ɁA�������H�ו��܂Ŏw��B
�����̂��̖̂����E���Ȃ��悤�ɁA�l�M�Ɛ��I������
���傤��Ɍy������̂��|�C���g�Ƃ��B
����A���I
����́A���̎������Â����H
�j�Ȃ�A�P�O�J���ł͕�����Ȃ��������邭�炢�����A
�R�R�͊����ĕ������ځA�H���̗]�C�𖡂킢�����B
�����Ă��u�������̖��X�`�v(800�~)���A
�ꏏ�ɑE�߂��邪�A����͌����ʂ�ɂ��đ��͂Ȃ��B
�Q��~������ƂŁA�����т͑喞�����B

�c�q�̋��������߂���ƁA����(�ӂƂ�)�Ƃ����n��ɓ���B
�����ɈȑO�A����҂̕��ɋ����Ă����������̂����A
�u���������̓��v(500�~)�Ƃ����������ꂪ����Ƃ����̂ŁA
���������s���Ă݂��B

�C�ӂ̉���ɂ͒������A�̍��Y���w���C�I
��͂�̕��C�́A���Ƃ悭�����B
�o���邱�ƂȂ�A�����ƃm���r�����Ă��������̂��B
�Ǘ��l�̕��ɒ����A��������̌���̗N�o�ʂ͌����đ����Ȃ��A
��������ɕ��������̂́A�����U���b�g�����x�B
���̂��߁A�`�����`�����ƔM������͕⋋����Ă��邪�A
�唼�̂����͏z����Ă���B�i���͈����Ȃ��j
�����A�����̐����𖡂킢������A
���������������āA�����̂܂ܒ����ꂽ
�ؗj���E���j���̒��C�`�����E�߂Ƃ̂��ƁB
���������S���Ⴄ�������B
�܂��A�n���ł͊��̏o�邨���Ƃ��Ēm���Ă��邻���ŁA
�����ɏZ��ł��Ă��A�킴�킴���̕��C��_���Ă���l������Ƃ��B
���ɓ��̉B�ꂽ�����ł���B

�������琼�ɓ��̌i���n�E�������܂ł͂T���قǁB
�V���D�œV��������������A�m���������ł�̂������Ȃ����A
����ڎw���̂́A�����܂ł�����B
��������������ĂP�O���قǂ̏��ɁA��i�̘I�V���C������B


���̖��́u��c�����I�V���C�v(500�~)�B
�������̓����݂߂Ȃ���A�C�����悭�ЂƂ����C�B
�n���̑傫���A�l�Ԃ̏�������̊��ł��镗�C���B
�o���邱�ƂȂ�A�[��ꎞ�ɖK�ꂽ�����A
�����͂��܂�傫���Ȃ��̂ō��G�͕K���B
�o���邾���A�Ă��鎞�ԑт�_���������̂��B
���A�����܂ł��i�F���y���ނ��߂̕��C�ł���B


�u��c�����c�v�̉A�ɉB��Č���ƂȂ��Ă���̂��A
�߂��̐m�Ȓn��ɂ���u�Ȃ����̓��v(500�~)�B
�ډB���������A���C�ɓ���Ȃ���i�F�͊��\�c�Ƃ͂����Ȃ����A
�g�̉����Ȃ�����镗�C�͍ō��I
���ꂾ���ɁA���f�L��������̂��ʂɃL�Y�B


�����ꂢ�ȋ�������ɖ����ł��Ȃ��Ƃ������ɂ́A
����ɓ�։����āA���蒬���̘I�V���C�����_�B
���ɐΕ��n��̊C�݂ɂ���u���Z�n���I�V���C�v(�����E����)�́A
���n���l�Ɍ�����Ȃ���̓����݁B
�V��ɂ���ẮA�������ꂪ�ڗ����Ƃ����邪�A
�V�[�Y���ɂ́A�n���̕��ɂ���ĊȒP�ȒE�ߏ������������B
�Ε��E�_���܂ʼn����ė���ƁA�܂��ɐ��ɓ��̐^�����B
�����P�R�U����������Z���^�[���C���������A
�W�����ƂɃA�b�v�_�E�����J��Ԃ��B
���̕��i�́A�܂��ɋ������̂��́B
�����������ɓ���K�ꂽ�̂ł���A
���ЁA���̕ӂ��翂т�����𖡂킢�����B
����������
�u��������P���v�Ő��ɓ��ɓ����Ă��A
��蓹���J��Ԃ��Ă���ƁA����ɒH�蒅�����ɂ́A
���z�����ɌX���n�߂Ă���B
�����œ����Ɉ����Ԃ��Ă��܂��ܑ͖̖̂����B
��͂�ꔑ�͂��������̂��B
����ɂ́A�P�l�ł����܂邱�Ƃ��o���邨���ȏh������B

���X�A���c�̍����h�ɂŐl�C�����������u�ɓ��܂������v�B
���͂��̏t�A���j���[�A���I�[�v����������Ƃ̂��ƁB
�����h�ɂƂ͎v���Ȃ��悤���Y��ȑ���ŁA�P���~���x��
���[�Y�i�u���Ȓl�i�łŏh���ł���͖̂��͓I�ł���B
���u�ɓ��܂������v�z�[���y�[�W
http://www.izu-matsuzaki.com/matsuzakisou/h/matsuzakisou.htm

�q������͐��C����]�B
���̉��i�ł��̒��]�́A�Ȃ��Ȃ��Ȃ��B
�����č���̓c�C���̗m���ɂP�l�Œʂ��ꂽ���Ƃ�����A
�܂��I�L�����C���������B
�������A�\��̒i�K�Řa�����I���ł���B
�[��ꎞ�A�G�߂������A�Ԃ����܂�x�͘p�߂邱�Ƃ��o���悤�B
��ɓ��̋x�ɑ����ǂ��������A�����������I
��ʂɈɓ������̌����̏h�͐l�C���������A�[���ł���B

����͂U�K�ɂ����āA��������������I�V���C������B
�����͎�O���ʂ铒�A���������B
�ߌ�Q�����璩�W���܂œ������\�Ƃ̂��ƁB
�u���W���͑������܂��H�v�ƈӒn���Ȏ�������Ă݂�ƁA
�������āA�|�������čĂт����𗭂߂�ƂȂ�ƁA
���W���Ɏn�߂Ȃ��ƊԂɍ���Ȃ��̂��Ƃ��B
���C�́A�I�[�o�[�t���[�����Ă��邨�����r�����ɗ��ꍞ�މ����A
���X�ς������ۂ߂Ȃ����A�܂�������������Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA���т����\������̂ŁA�����̏h�ɂ��Ă͂ƂĂ����K�I
���s�[�^�[�����������ȋC�z������B

����̖��͂́A���ƌ����Ă��f�p�Ȓ����݂ɐs����B
���̒��ł��u�Ȃ܂��ǁv���������������A
�������킢�����������Ă���B
�u�Ȃ܂��ǁv�Ƃ́A���ƍ��̌�Ֆڂ��߂Ɍ�������O�ǂŁA
�C�����̕��������n��Ȃǂɂ悭������B
�|�ō��g������āA���̏ォ��y�����w�ɂ��d�ˁA������A
���̐N����h�����߂ɁA�����グ�đ���Ƃ����B
���̐���オ������u�Ȃ܂��v�Ɏ��Ă���Ƃ��납��A
�u�Ȃ܂��ǁv�ƌ�����悤�ɂȂ����B
����͋ߔN�A�s�u�h���}�g�Z�J�`���[�h�̃��P���s��ꂽ���ƂŁA
�����N�݂̂Ȃ炸�A��҂̖K��������Ă���Ƃ��B
����̗��������������݂́A�V��j���A�ǂ̐���ɂƂ��Ă��A
�C���������炮�ɈႢ�Ȃ��B
����H�������[�g���A�I�g�N�ɉ��ɂ́A
���c�}�d�S���̔����Ă���u���ɓ��t���[�p�X�v�����E�߂ł���B
http://www.odakyu.jp/train/ticket/couponpass/izu.html#01
�s�����u�������荆�v����ƂȂ邪�A
���ÁE�O�����珼��E�_���܂ł̃o�X���R���ԏ�����B
�A��̂����Ղ͕t���Ă��Ȃ����́A�O������V�����Ƃ����̂�
�ł������B�i�O���`�����F�V�������R��3890�~�j
�܂��A�O�Љ���u�x��q��ɓ��t���[�p�X�v�ł�
����E�������G���A�̓J�o�[���Ă���̂ŐS�����B

�����P�̂i�q�E���S���ʓ��}�u��������v�B
��������Ƃ��Ȃ��Ƃ������́A��x����������B
����́A�ł��V�����u�i�q�E���S���ʓ��}�v�����グ��B
�Q�O�O�U�N�U���P�W���i���j�j �ɓ��}���c�҂Q
���}��ԂƂ����A�S����Ђ̊Ŕ��i�B
�Ŕ����ɁA���}�𑖂点�Ă����Г��Ŋ�������̂���{���B
�������A���́g�ǁh��ł��j���āA���Ђ̘H���ɏ�����Ă���
���}��Ԃ��킸���Ȃ��瑶�݂���B
�����ō����́A���}��ԂƂ��Ă͋H�L�ȑ��݂ł���
�u�i�q�E���S���ʓ��}�v�ɃX�|�b�g�ĂȂ���w�ق��Љ��B
�g�b�v�͂i�q�ƈɓ��}�s�A�ɓ������S���ʂ���u�x��q�v���B
�w�ق́A�ɓ��}�s���E�ɓ��}���c�w�����グ��B

�i�q�ƈɓ��}�s�A�ɓ������S���Ƃ̒��ʉ^�]�̗��j�́A
�ɓ��}�s�����J�Ƃ����P�X�U�P(���a�R�U)�N�ɂ����̂ڂ�B
�����A�ɓ��܂ł͉���s�y�q�����̏��}��Ԃ��^�]����Ă����B
���̗�Ԃ��A�ɓ��}�J�ƂƓ����ɓ������������邱�ƂɂȂ�
�P�X�U�X(���a�S�S)�N�A�V�����O���w�J�Ǝ��ɁA
�ꕔ�̋}�s�u�ɓ��v���u���܂��v�Ƃ��āu���}�v�Ɋi�グ�B
�����Ɂu�i�q�E���S���ʓ��}�v���a�������̂ł���B
�P�X�W�P(���a�T�U)�N�ɂ́A���̓��}�u���܂��v�Ƌ}�s�u�ɓ��v��
���}�u�x��q�v�Ƃ��ē����A�l�����I�ɂ킽���Ċ���𑱂��Ă���B
���݁A�����`�ɓ��}���c�Ԃ́A�Q���ԂS�O�����܂�B
�^�s�������炷��A���������X�s�[�h�A�b�v���]�܂�邪�A
�ɓ������̓��H����̈����ɋ~���Ă���_���c�B
�܂��A����ɒ����܂ŋC���������߂Ă����ɂ́A���x�������Ԃ�!?

�ɓ��}���c�̉w�ق��Љ��̂́A�Q�O�O�R�N�Q���ȗ��A��x�ځB
�����͍\���H��������Ă���A�ɓ��}���Y�u���X�g�����Ղ�݂��v�B
���X�͉��D���E���̔��X�A���D������Đ��ʂ̂Q�����B
�i�����́A���D�O�̔��X�̕��������B
�i�Ȃ��A�ɓ��}���c�ł͗�Ԃ��Ƃɉ��D���s����B
���̂��߁A���R�Ƀz�[���ɓ��邱�Ƃ͕s�\�j
�c�Ǝ��Ԃ́A���X���`��W���܂ł����A�ߌ�S�����Ԃ̒���֍ŏI�A
�u���߰�ޭ��x��q52���E�r�܍s�v���o��Ǝ�����̓X���܂��B
���̎��_�ŕٓ����]���Ă���A���z�Z�[���ƂȂ�͗l�B

�܂��́A���N�̐V��w�فu�ɓ��Â����v(1700�~)����B
�C�Z�G�r�������A�h�[���Ə�����������Ȃ���B
�܁A�k�������͎̂��������A�R�R�͕��͋C���y���݂����B
�Q��~��鉿�i�ŁA�����܂ł�����̂͌����ł͂Ȃ����B
���͂��̉w�فA���N�W�O���N���}�����i�s�a�̎����\��
�ɓ��}�������ŊJ�������w�قŁA
�ɓ��}���c�ł́A�P���P�O��(����)�̌���̔��Ƃ̂��ƁB
�U���ȍ~�A�ď�̓C�Z�G�r�̋����Ԃɓ����Ă��܂�������
�����͎b���x�ނ��A�H�ɂ͍Ăѕ�������\��B

���ɓ��̖��o�Ƃ����A�Ƃɂ������ɂ��u���ڑ�v�B
�q���̍��A���ӂ�̐e�ʂ���͂��݂₰���Ƃ����A
���܂��āu���ڑ�̔��Ђ��v�������B
�ǂ���Ǝv���āA��R�����Ă��ꂽ�̂��Ǝv���̂����A
�R�l�������Ȃ��j�Ƒ����H�אs�����ɂ́A�ׂ��d�������B
���������������A���ڑ�̏ċ��B
�L��݂ȂA�����ɏ������B
�u���ڑ�̏ċ��Ȃ�ĐH�������Ȃ��c�v�B
�����v���āA���\�N�������Ă��Ă��܂����B
�������A���̍l�����͌��ł������B
���́u�����ڂ̉��Ă��ٓ��v(1000�~)�́A
����Ȑl�Ԃ̉��l�ς���ς����Ă���邩������Ȃ��B
�������Ղ�̋��ڂ̖��킢���A�������̎_���Ɉ����o�����B
���ږ{���̖��Ƃ������̂́A����قǂ܂łɔ����������B

�����g���ځh�̖��͂�̊��ł����̂́A
���i��ʂ��āu�h�g�̔������v��m�������Ƃ��傫���B
���ڂ̎��Ǝɗ��̊Â݂��g�ݍ��킳�������킢�͌����B
���́u���ڑ�̂킳�їt�����v�i900�~�j�́A
�V��ɗR������킳�т̗t���ς������A�N�Z���g�B
���ɃV���v���ȍ\���ŁA�ʂ����������A
�����ł��y�����Ƃ��������Ȉ�i�B

���ڂ̉w�قɂ��ď����Ă��āA���߂Ďv���B
���́A���܂�ɂ��b�܂ꂽ�y�n�ň���Ă��܂����̂��B
�x�m�R������O�A�����|���̓�����O�A
�������A�|�����ڂ����ē�����O�B
�y�n�𗣂ꂽ���ƂŁA���̐������q�ϓI�ɔF�߂�ꂽ���A
�u������O�v�����ݍ���ł��܂����͕̂ς��Ȃ��B
���ڂÂ����̗L��݂́A���������Ɣ���Ȃ��̂����c�B
�u���ڑ�̉����i�v�i840�~�j�B
�g���ʂقNj��ڑ₪�D���h�Ȃ�ĕ���������A
����ȕ��ɂ͂����̂�������Ȃ��B

�u���v���g�����u�����i�v�Ƃ����w�ق́A
��D�E���c���Ȃǂɂ����邪�A�ɓ��}���c�ɂ����݂���B
�����������������ɁA���o���V�r�A�ɂȂ炴��Ȃ����A
�����Ɉ����H�ׂ�����A���̉w�ق��I�����ɓ����Ă���B
�i1050�~�j
�ߊC���̂̊C�̍K�������Ղ�̈ɓ��}���c�w�فB
�����ȃC�Z�G�r�ƁA���Ƃ����ڌ����ł��D���ɂȂ����ڂ̉��Ă��B
���̂Q�͂��ЁA������Ă��������B
�����̃����|�C���g�`�i�q�E���S���ʓ��}�ōs�����T�u�x��q�v
�ŋ߂́g�͒Í��h�Ȃ�Ă̂��L���ɂȂ��āA
���t�̓�ɓ��́A���Ȃ�̐l�C���Ă���B
�������A���Ă���~�J���̓�ɓ����̂Ă������B
�t�قǐl�͂��Ȃ����A�^�Ă̂悤�Ȕς��Ƒ��A������Ȃ��B
��ɓ��������͂������ɖ��킦��̂́A
���͂��̎��G�ł͂Ȃ��낤���B
�������`���c�E�Q���ԂS�O���̗�

�u�x��q�v���ɂ͂R��ނ���B
�܂��́A�ł��O���[�h�������u���߰�ޭ��x��q�v�B
90�N�ɓo�ꂵ��251�n�d�Ԃ�����g�p����A�S�Ԏw��ȁB
�O���[���Ԃ͂R��V�[�g�ŁA��������ق��A
���}����������߂ɐݒ肳��Ă���B

���ʂ́u�x��q�v��81�N�o��A113�n�����ނ������A
���C�����̓d�Ԃł͍ŌÎQ�ƂȂ�185�n�d�Ԃ��g�p�B
���R�Ȃ��ݒ肳��A�C�y�ȏ�Ԃ��o����B
�o�ꓖ���́A���ʗ�Ԃƕ��p���ꂽ�ԗ��̂��߁A
�V�[�g���|��Ȃ��������A���ł̓��j���[�A������A
�悤�₭���}�炵���ԓ��ɂȂ����B
���}�Ȃ̂Ɂu�����J���v���A�c�O�Ȃ���r���ʼnw�ق̗����͂Ȃ��B
�����E�����̂���M�C�ӂ�ł��Ζʔ������̂����c�B

�����āA�y�E�x���𒆐S�ɉ^�s�����u���]�[�g�x��q�v�B
�ɓ��}�s�̊Ŕ�ԁu(�A���t�@)���]�[�g�Q�P�v���[������A
���S�̗�ԂƂ��ď��߂ē����w��������ʂ������B
�����T���̒��ǂ��ɁA�����w�Ŏ��S�̓d�Ԃ����邱�Ƃ��o����B
�u���]�v�ɓ��������u���]�[�g�Q�P�v�́A85�N�̃f�r���[�B
�����A���̏Ռ��͑����Ȃ��̂ł��������A�Q�O�N�ȏ�o���������A
�Â������������Ȃ��̂͑f���炵���B
���ہA�i�q�́u���߰�ޭ��x��q�v���o�����̂��A
�ɓ��}�́u���]�[�g�Q�P�v�̑��݂����������炾�B
���ݏ�����̂����ʂ��������ꂽ�����Ⴞ�낤�B
���Ȃ݂ɂ��̓d�ԁA���i�͔M�C�`�ɓ��}���c�Ԃ�
���ʗ�ԂɎg�p����Ă���A���}�����Ȃ��ŏ�Ԃł���B

�u����������炻���͈ɓ��v�Ƃ����R���Z�v�g�̉��ɓo�ꂵ��
�u���߰�ޭ��x��q�v�ɂ́A���̗��O�̎����̂��߂ɁA
�ԓ����D�̔p�~���s��ꂽ�B
����ɏ�Ԍ��Ńr���[���f�B�Ȃ邨�o����ɐؕ���������B
��Ԍ��ɂ��o������Ƃ����̂́A
�V�����̃O���[���ԁi�����{�j�ł͂悭�����邪�A
�ݗ������}�ł͋H�L�ȑ��݁B
�`���b�g�D��ȋC���ɐZ�邱�Ƃ��o�����u�ł���B

�i�F���y���ނȂ�A�ǂ́u�x��q�v�ł��u�`�ȁv���m�ۂ������B
�`�ȂƂ����̂́A�Y�o���u�C���̑����v�̍��Ȃł���B
�ŋ߂́A�C���^�[�l�b�g���g�����w��Ȃ̗\��T�[�r�X�ł�
�u�`�ȁv���I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă���ق��A
�w�̎w��Ȍ����@�ł́A�Ă�����ȕ\����I�ׂ�̂ŁA
���̃T�[�r�X�́A�ϋɓI�Ɋ��p�������Ƃ��낾�B
���āA�������o�ĂP�T���A�u������v��n���Ă܂��͓����E�o�B
�V�q���t�߂Ń^�C�~���O���ǂ���A���}�̉����ƃf�b�h�q�[�g�B
�˒ˎ�O�ōŏ��̃g���l����������A�E��Ɋω��l��������Α�D�B
�n�����n���Ďb���s���A���߂ɊC���m�F���č��{�Òʉ߁B
���c���邪����Ɉ�u���E�ɓ���A�g���l�������Ƃ��납��A
���悢��C���ԋ߂ɔ����Ă���B
���{��w��O���A���C�������ł̓r���[�X�|�b�g�B
���͌��ōŏ��̉���q�𗎂Ƃ��A���ؐ��n���ĐÉ����B
�q�������������M�C���߂���ƁA��Ԃ͈ɓ����ցB
�K�N���ƃX�s�[�h�������āA�s���Ⴂ�̒�Ԃ�������B
�ɓ��ŏ��̃r���[�X�|�b�g�́A�ɓ�����̎�O�B
����Ă���ΐ��ʂɏ������]�߂�B
�썑�I�ȕ��͋C�̍����P�R�T�����������Ă�����A�Ԃ��Ȃ��ɓ��B

�����ŏ斱������サ�āA��Ԃ��ɓ��}�s���ɓ��������Ƃ�����B
�A�b�v�_�E����̊����Ȃ���A�S���t�R�[�X�̌������ɁA
���C���]�߂�A��ޕt�߂��̂Ă������B
�Ԃ��Ȃ��ɓ������Ŏ�҂̑唼�������A�ԓ��̕��ϔN��A�b�v�B
�����ނ藧�����߂�M��̉w�ŁA�����ɗ������Ƃ������B


���̕А����c���߂���A���悢��u�x��q�v�̃n�C���C�g�I
���ɓ��̔g�ł��ۂ��Ԃ͑��s�A�ɓ��哇���ԋ߂ɔ���B
�u��Ԃ͂��ꂩ�瓌�ɓ��̊C�ݐ��𑖍s���܂��v
����Ȉē������������āA�ɓ��}���ōł����N���N����u�ԁB
�����o�ĉ͒Â܂ł́A�g���l�������݂Ȃ���C���y���߂�B
�@�䎛�ŁA���ɓ����ʂ̋q�𗎂Ƃ��ĂR���B
�I���E�ɓ��}���c�̍s���~�܂莮�z�[���Ɋ��荞�ށB

�悭�u�ԓ��̐��|�E�����̂��߁c�v�ƃz�[���ő҂�����邪�A
�u���]�[�g�x��q�v���ɂ��[�������ɓ��}�s�́u���]�[�g�Q�P�v�ł́A
���c�̉w�ɒ����ƁA�����Ɓu�ԊO���|�v���s����B
�u���]�[�g�Q�P�v�̔���́A���ƌ����Ă��O�ʓW�]�B
�����𗁂тđ��邾���ɁA���K���X������₷���̂����������A
�Ŕ��i�ւ̈���ƁA���͎�����B
�u����Ă悩�����Ȃ��v�Ǝv�킹�Ă����ЂƃR�}�ł���B
�n�C�O���[�h�ŏd���A�o�u���̖��c������������u���߰�ޭ��x��q�v�A
�J�W���A���Ōy���A�W�O�N�㏉���̋�C������u�x��q�v�A
���]�Ȃ炨�܂����u���]�[�g�x��q�v�B
�R�́u�x��q�v�A�����A���Ȃ��͂ǂ��I�Ԃ��H
�����c�̊X�Ŋ�����u���j�v

������t�̂T�N�A���ĊW���ł��ٖ��ɂȂ����Ƃ�����B
���̓��ĊW�̌��_�́A�����m�u���D�v�B
���̎����ꂽ�A���Ęa�e���ɂ���āA
���فA�����ĉ��c�̂Q�`���J���ꂽ�B
�Q�O�O�N�ɂ킽��u�����v�������ꂽ�u�Ԃł���B

�]�ˎ���A���҂��̍`�Ƃ��ĉh�������c�B
���̉��c���A�P�W�T�S�N����̂S�N�ԁA
���{�j�̕\����ɖ��o���B
���̖��c����A���ɓ`���鎛���u���厛�v�B
���Ęa�e���ׂ̍����l�߂��s���A
�A�����J�C�R�ɂ����{���́u�m�y�R���T�[�g�v��
�s��ꂽ�̂��A���̎��Ȃ̂��������B
�T���𒆐S�ɁA�����ɂ̓A�����J�W���X�~���̉Ԃ��炭�B
���̍��肪�A���̒n�����ĊW�̌��_�ł��邱�Ƃ��A
�ۉ��Ȃ��Ɋ���������B

���̌��ʁA�A�����J�l�́u���c�̊X�����R�ɕ��������v��
��ɓ���邱�ƂƂȂ����B
���A�y���[���[�h�ƌĂ��ӂ�i�摜�j���A
���̐̂́A�����̃A�����J����舕������̂�������Ȃ��B
�����A�J���I�ȍ`���䂦���A���{�̏����ƃA�����J�l�̊Ԃɂ́A
���R�ƃt�����h���[�ȊW�����܂ꂽ�Ƃ����B
�ł��A�����ق��Č��Ă����Ȃ������̂����{�̖�l�B
�����������獢��Ƃ����ə�߁A���������ɂ��������Ƃ��B
��l�Ƃ����̂́A���̎���������ɕېg�ɑ�����̂��B

���̒��ŁA�P�̔ߌ������܂ꂽ�B
�L���ȁu���l���g�v�̘b�ł���B
�M��H�̖��Ƃ��Đ��܂�A��\�l�ɂ���
���c����̔��e���ւ�|�W�Ƃ��Ė���y�����B
���̔������䂦�A���{�̖�l�̖ڂɗ��܂�A
�A�����J�̏�����{���̎��E�n���X�̎����ƂȂ����B
�n���X�Ɏd�������Ԃ́A�Z�����̂ł��������A
���̎��A���g�ɕ��ʂ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��悤�ȑ����
�x����ꂽ���Ƃ������āA��������͓i�܂�āA
�u���l�v�Ɣl����}�𗁂т邱�ƂƂȂ��Ă��܂����B
�̂Ɍ��������⎖�Ƃ���肭�������A
�����Q�S�N�A���J�̖�ɐ�ɐg�𓊂��āA
����A���̔g���̐��U�̖������낷�c�B
�i�摜�͂��g���J�������������E�����O�j
���́A���c�����̎��z�Ԃ��������G�߁B
���c���ʂւ̗��s���v�悵�Ă�����������Ǝv�����A
�K�ꂽ�為�ЁA�J���Ƃ������j�̌��̕��������łȂ��A
���j�̋��Ԃɐ��܂ꂽ�u�A�̕����v�����߂����B
����͂����Ȃ��u����v�I
�ɓ��ɗ�����A��͂����Ȃ��̂��u����v�ł���B
�����A���c�̎s�X�n�ɂ͈������ꂽ�������ꂪ�ꌬ�̂݁B
������Ƒ���L���āA��ɓ����̉�����ڎw���B

�ɓ���т��J�o�[���Ă���o�X�u���C�o�X�v�B
���݂͕��Љ�����A���c���ӂ͓�ɓ����C�o�X�̃G���A�ƂȂ�B
��ɓ����ʂւ́A�ɓ��}���c�w�̃o�X����A�R�E�S�Ԃ���
����A�ΘL��`���ʂ̃o�X�ɏ�荞�ށB

��ɓ��ɂ́A����Ή���Ƌ|���l����̂Q�����邪�A
����͉���Ή���A�|���l����͉������̈����ł���B
����Ή���́A����̉��x���A���悻�P�O�O�x�ƍ����A
���鏊�œ�������������āA�����炵��������邪�A
�c�O�Ȃ���A������u��������v�͏Z����p�ŁA
�O���̐l�Ԃ́A���̎{�݁u��̓���فv�𗘗p���邱�ƂɂȂ�B
���ٗ��͑�l�X�O�O�~�ł��邪�A���b�J�[���P�O�O�~�Ȃ̂ŁA
������A�P�O�O�O�~������ƍl���Ă悢�B

���́u��̓���فv�A�����P�U�O���b�g���Ƃ����N�o�ʂɂ�
�ւ�炸�A�I�V���C�����݂���Ȃǎ{�݂��傫���B
�܂��A���َ҂������������A�z�����p����Ă���B
�P�O�O�O�~�Ƃ����������ٗ����A����䂦��������Ȃ��B
���̒��ŁA�I�V���C�́u�̓��v�Ɩ��t����ꂽ�����A
���������ɂȂ��Ă���͗l�B
�܁A��ӏ������ł��A���������̗������݂����Ă���̂�
�~���Ƃ������Ƃ��B

�g�������h�Ƃ́A�܂��ɂ��̂��ƁB
�u�|���l�v�ƌĂ��A�|�Ȃ�̌ʂ�`��������̊C�ݐ��́A
���c�̔��l�A�͒Â̍���l�ƕ��ԁA�ɓ��O����l�ɐ������A
���{�̏��E�S�I�ɂ��I��Ă���B
���߂邾���ő傫�Ȗ��������o����C�ݐ��́A���������Ȃ��B

��������Ƃ����_�ł́A�������
�|���l�ɂ���u�݂ȂƓ��v(300�~)�̕�������₷���B
���������ɂ����āA�C�݂���͏�������Ă��邪�A
�o�X��u���_���O�v���炷���B
�߂��ɂ͏������Ȃ��璓�ԏ�������āA�Ԃł��n�j���B

����łP�O�O�x�ŗN���o�����A�����ʂ������h�������́A
�|���l�Ɉ��������ԂɁA����Ȃ�ɂ����������ɂȂ��Ă��邪�A
����ł��A���\�M���B
�����A�����̓��[�͖ō���Ă���ق��A
�������ɂ́A���|����Ƃ���܂ō���Ă���B
���͂��́u�݂ȂƓ��v�A�X�Q�N�ɏo������r�I�V��������ŁA
�ǖʂɂ͋���ȃ����[�t�������Ă���A
�ό��q�ł�����₷���A���Y��ɍ���Ă���B
�M�������ɔ��āA�������[�Ńm���r�����Ă�����A
�Ⴂ�N���Q�l�A��œ����Ă����B
���C��Œ��肪�e�ނ̂́A�����Ă��A��A�̔N�z�̕��Ȃ̂����A
�������A�N�̂P�l���b�������Ă���ł͂Ȃ����B
�u���A�Ȃ�Ǝ��̕�Z�̂��ׂ̍��Z�̏o�g�B
�������w������͓s���ŁA���̍Ŋ�̗w�������Ƃ����B
���̏t�A�Љ�l�Ƃ��āA�悭�j�b�|�������ł��b�l������Ă���
�u�t�@�b�V�����Z���^�[���܂ނ�v�ɏA�E�A
���ǁA�����E�x�m�{�̓X�܂ɔz�����ꂽ�Ƃ����B
�����ď��߂Ă̋x�ɂ��A�ɓ��̉���ւ���ė����̂��Ƃ��B
���z�̗ǂ��ƒ���̐S�n�悳�́A�A�܂������炢�ɐڋq�����B
�������ăA���o�C�g�����Ă����A���̊w���o�C�g�N���A
������Ƙb�����Ă݂�A�d���̏o���s�o���͐����ł������A
���̒��肪�o����t���b�V���}���Ȃ�A�d�����o�������B
�����̂��X�́A�����l�ނ��l�����̂ł͂Ȃ����B
�`�F�[���X�����ɋ��������������낤���A�撣���Ăق������̂��B

�|���l�ŏh�����Ȃ�A���E�߂́u�x�ɑ��E��ɓ��v�B
�P���~���x�ł��Ȃ�L���A�Y��ȕ����ɔ��܂邱�Ƃ��o����B
���C�͏z�����A��r�I�����̐����������邱�Ƃ��ł���ǎ��Ȃ��́B
�H�����o�C�L���O�`�������A���͈����Ȃ��B
�ɓ��Ń��[�Y�i�u���ȏh��T���̂ł���A�I�����̈�Ƃ������B

�u�x��q�v���ŖK�ꂽ��ɓ��B
��ɓ���K���ۂ́A�K�{�A�C�e���Ƃ��Ă��E�߂������̂��A
�u�x��q��ɓ��t���[�������v�ł���B
�R���ԗL���A�ɖZ���ł��g�p�ł���ق��A
�����`�ɓ��}���c���u���߰�ޭ��x��q�v�ʼn������邾����
���������A���ɓ��E�������܂Ńo�X������B
���̑��݂�m��Ȃ��̂��A�o�X�Ō����Ŏx�����Ă���ό��q��
��������ꂽ�B
�����ł��I�g�N�ȃ`�P�b�g��T���̂́A���̊�{�B
���ЁA���p���ꂽ���B
����́A�i�q�`���S���ʓ��}�ōs�����̑�Q�e�B
�����ɓ������̐������A���ɓ������グ��B
Copyright(C) 2005 Nippon Broading System,Inc,All Reserved.