 この後、こんな姿になる。事前に心拍数等を測定する線をつける。
この後、こんな姿になる。事前に心拍数等を測定する線をつける。 この後、こんな姿になる。事前に心拍数等を測定する線をつける。
この後、こんな姿になる。事前に心拍数等を測定する線をつける。 |
 いよいよ測定器具を装着 |
 なんと一人の選手に6人のスタッフ。すご~い。これで測定料が1,020円なんて安い |
 安静時の乳酸値を測るため採血。ちょっと痛い 安静時の乳酸値を測るため採血。ちょっと痛い 心拍数が表示 これは測定中の選手にも見える |
 スタッフ一同 測定開始。 |
 スタート! まずは走行速度180m/分から |
 3本目。240m/分 |
  5本目。走行速度300m/分。約3'20分/kmペース。 |
  6本目。330m/分です。約3'00分/kmペース きつい |

乳酸をとるため、左手薬指にちくっと針をさして血を出し、その血で乳酸を図っている。ちびっと痛かった。
結果の数字とともに山地先生からトレーニングの指導を受ける。最初から厳しい指摘を受ける。
●「あなたは以前から見てますが、ばたばた走りですね。足音が気になりませんか。」そんなにフォームがひどいのか。ただ、自分は同じ位置で足音を聞いているので、足音が大きいとかはわからない。「自分では、足音はわかりません」正直に答える。
山「こんな走りだと故障しませんか。シューズも薄いようだし」
堂「この一年間で2回肉離れをしました。」肉離れは関係ないかな。
堂「3年ほど前に、足を痛めてます。いつもはクッションのよいシューズにアルファゲルの中敷を入れています。このシューズはレースだけはいてます。」
山「それぐらいしないと危ないですね」
●「体は垂直の方がいいですよ。垂直の方がストライドが伸びます。衝撃も少ない。前傾では衝撃が大きい」
堂「そうですか。以前も、前傾が強すぎると言われて直そうとした事があります。でもなかなか直りません」悩んでいた。やはり垂直か
山「生まれて1年後に立ち上がって若い人でも20年、立ってるときのフォームが固まっています。簡単には直らないでしょう」
●「体が硬いですね。」
堂「言われるとおり硬いです」
山「いや、物理的な硬さではなく、走ってるときのがちがちな硬さ、ぎこちない硬さ。」
(どうすりゃいいのだろう。ばたばた走り、やわらかい走り。いきなり言われて、少々ショック。聞くのを忘れた)
山「それでは今日の結果からレベルを引き上げることを指導します。まだまだ上がります。」
●①呼吸循環系測定結果
| 氏名 | 堂谷 芳範 | 性別 | 男 | |
| 生年月日 | S31.06.09 | 測定年月日 | H14.09.21 | |
| 専門種目 | 陸上 マラソン | 所属 | 北陸電力 |
| 身長 | cm | 178.0 | 皮下脂肪 | 上腕 | mm | 5.0 | |
| 体重 | kg | 63.3 | 背部 | mm | 10.4 | ||
| 胸囲 | cm | 88.5 | 腹部 | mm | 9.2 | ||
| 座高 | cm | 94.0 | 体脂肪率 | % | 11.5 | ||
| 最大負荷運動時間 | 3分0秒 |
| Vo2max ↓ | |||||||
| 走行速度 | m/分 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
| %Vo2max | % | 57 | 67 | 75 | 87 | 94 | 100 |
| 酸素摂取量 | ml/分 | 2055 | 2424 | 2694 | 3127 | 3408 | 3609 |
| 酸素摂取量 | ml/kg・分 | 32.5 | 38.3 | 42.6 | 49.4 | 53.8 | 57.0 |
| 乳酸値 | mmol | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 4.8 | 9.6 |
| 呼吸商 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.18 | |
| 肺換気量 | l/分 | 59.6 | 69.7 | 76.8 | 91.1 | 104.7 | 130.2 |
| 呼吸数 | 回/分 | 49 | 43 | 43 | 44 | 48 | 70 |
| 一回換気量 | l | 1.22 | 1.62 | 1.79 | 2.07 | 2.18 | 1.86 |
| 心拍数 | 拍/分 | 121 | 134 | 147 | 162 | 171 | 176 |
| 酸素脈 | ml/拍 | 17.0 | 18.1 | 18.3 | 19.3 | 19.9 | 20.5 |
・限界の心拍数は176。まだまだいけますよ。年齢はいくつですか。
堂:46です。
山:220-46=174 ううん、こんなもんですか。(どうも、もっと若いと見えたようだ)
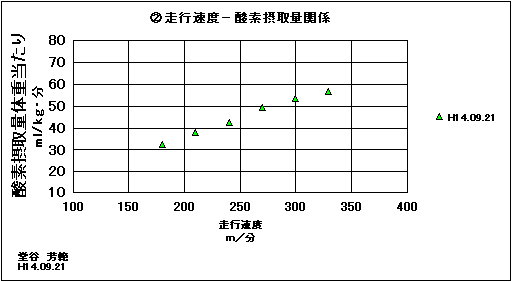
・限界のスピードでの酸素摂取量=最大酸素摂取量は56ml/kg・分
記録を上げるには、
★①最大酸素摂取量を高める。
これを上げればより速く走れる。
これはトレーニングにより高めることができる。
上げるのは若いときでないと難しい。年齢からすると現状維持がベストかな
記録を縮めるには、もう一つ、
★②効率よく走ることが必要。(同じ酸素でより速く走る。省エネ走法、ムラなく走ることか、集団の中で走り力を溜める、こう解釈した)
1500mの選手なら、毎日1500走ればいい。10000mの選手なら毎日10000m走って効率的な走りを覚えればいい。しかし、人間は同じ事をしていると飽きる。
実際には、強度を上げ下げした練習となる。
効率を上げるトレーニングとしては、(ランニングエコノミーという)
・加速走(スピードを加速していく)
=ビルドアップ(一方的に上げていくものと思っていたが、少しずつ上げていって、ドスンと落とし、また少しずつ上げていく。数回繰り返す)
年をとると最大酸素摂取量を上げるのは難しい。むしろ、落ちるのを防ぐと考えた方がよい。
ベテランランナーは、最大酸素摂取量が落ちる分、ランニングエコノミーでカバーしている。
このカーブは、トレーニングの効果を把握するため、定期的にとるとよい。
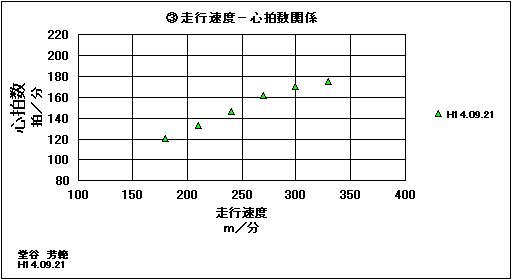
・下のグラフ④から乳酸が溜まるスピードは290m/分。このときの心拍数はこのグラフから170と読み取れる。これ以上の心拍でトレーニングすれば、乳酸が溜まるトレーニングとなる。
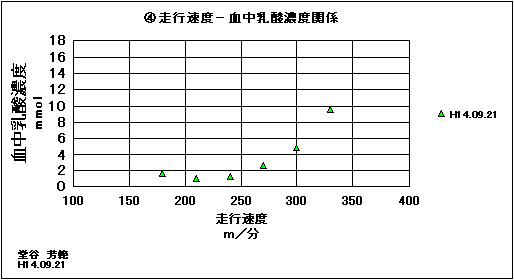
・乳酸値が4を超えるスピードが乳酸の溜まるスピード。4以下なら、ずっとスピードを維持できる。
乳酸が溜まるとは、発生するのと分解するのと収支バランスが崩れるスピードのこと。マラソン選手はこれより低いスピードで走っている。、
この限界値を乳酸性作業域値(Lactic Acid Thresh
Hold:LT値)
あなたの場合、このグラフから290m/分と読める。このスピードで30kmぐらいまでなら行けるのでは(3'30のスピード)
このスピード以上で走らないとトレーニングにならない。インターバル、レペなどがよい。
・乳酸値MAXは9.6。乳酸値が少ないとのこと。歳のせい?
追い込みのすごい選手は15 20の選手もいるとか。
限界になると、トレッドミルで蛇行し、危ない。
安全を考えればこんなもの。
・トレーニングを積むとLT点を右傾化できる。一線ランナーは実施している。
また、レースのスピードで走ると筋肉に無理がかかり、傷めることもある。
実際には、強度を上げ下げした練習となる。乳酸が溜まる以上の強度は練習として必要。
また、疲れたままでは、強度を上げられないので、適度な休養も必要。休養は完全休養ではなく、130ぐらいの脈で30-60分。ゆっくり長く。歩くのもよい。完全休養がいいのか、ジョグの休養がいいのか、試してみればわかるでしょう。
実業団の選手はレースが日曜にあると、休養を月曜、金曜に入れている。休養の後は、レースより早いスピードトレーニング。
実業団選手の一般的な週間トレーニングとして、
日曜 レース
月曜 疲れをとり、休養
火曜 レースより速いペース
水曜? ビルアップ、ファルクトレーニング
木曜? 持久走
金曜 休養
土曜日曜 レースorタイムトライアル、レペ、持久走など
山地先生は日本でも有名なランニングスポーツの専門家。かけっこも学問にかかるといろいろと奥が深い。難しい言葉も出てくる。初めて聞く言葉はなかなか理解できない。
前の自転車をする中学生の親と、
自転車のトレーニングの場所がなくて大変でしょう、早朝に競輪場でも開放してくれればいいのに。しかし、事故が起こったときの責任を誰がとるのか、とかいろいろと理由をこじつけてなかなか開放してくれない。
総合運動公園のクロカンコースも自転車もことを考えていたが、競技場入り口のトンネル部分が狭すぎて自転車は危ないという事で自転車が禁止された。中途半端な設計。今では、走るのでさえひどい状況。
これを聞いて、選手の立場に立った見方そのものと見た。この声がほんとに必要なもの、削ってはいけないものを反映する。まったく同感だった。
エアロバイクでのトレーニングについて質問すると、
心肺機能を上げるには非常にいい。しかし、やりすぎると太ももが太くなりすぎて、ランニングの邪魔になる。負荷を小さく150ぐらいで、速くこぐ、長くこぐとよいとのこと。
もっともな理論。しかし、いつもトレーニングしている自分としては、副作用はあまり感じない。太ももに筋肉がつくほどしていないのだろう。
自分はいつも限界まで追い込んでいた。負荷がかかりすぎていた。しかし、150くらいでは少なすぎる。楽すぎる。
今までの負荷で回転数を上げよう。「速すぎます」を超えるぐらいがいいと見た。また、3日連続はまずい。トレーニング回数で半分以上にならないようにしよう。ただ、会社のトレッドミルはいつもふさがりがち。エアロバイクならいつも開いている。確保が難しいな。
今年急に悪くなったのは、太もものせいなのだろうか。太ももが太くなったから?
自転車のトレーニングでは、力いっぱい追い込んでも脈は160ぐらい。170など滅多に超えない。なぜ?
指導員に聞いたら、エアロバイクでは、足だけ酸素を要求。足が先に参るので息も絶え絶え。しかし、足以外はまだ余裕があるので、酸素の量はさほど要求されない。脈もさほど上がらない。エアロバイクの測定では、最大酸素摂取量の測定は少なめにでるとか。