桐集成材がおすすめです。軽くやわらかいので加工が楽です。また、比較的安価。ホームセンターに行って、どんなサイズの製品があるかを調べておきましょう。厚み18mmの桐集成材を使いました。引き出しには引き出し深さに合うヒノキ材(スギ材でも可)使用。引き出しの底板にはシナベニヤを採用しました。
切り集成材 500×1820×18mm
ヒノキ材 9×30×1820mm
シナベニヤ 厚み3mmのもの
1.簡単な図面を作成。図面から寸法がわかればいいので、フリーハンドで描いてオーケーです。
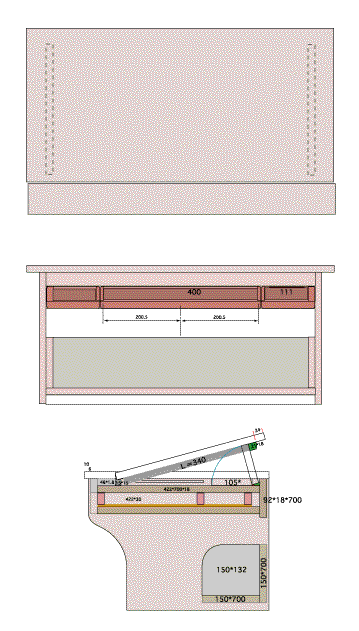
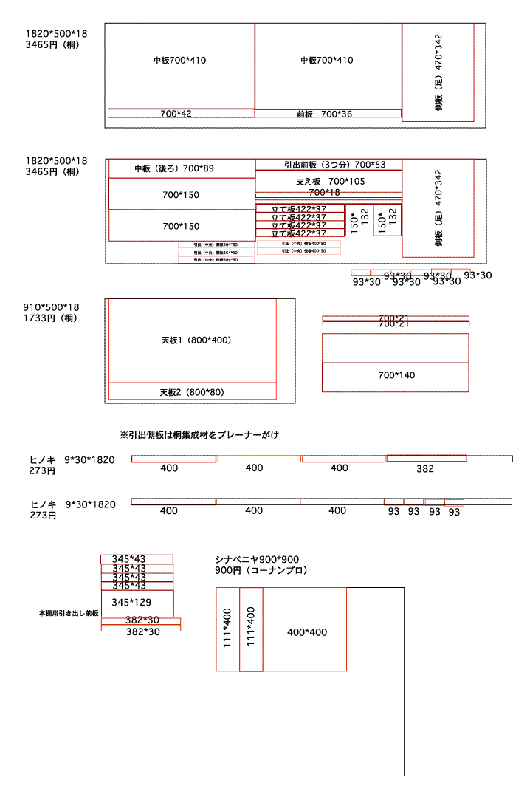
桐材はやわらかいので傷が付きやすいというのが短所ですが、市販のカッティングマットを天板に置いて使うといいのではないでしょうか。