主原料の珪藻土は、生きているように呼吸していると言われています。これは、珪藻土の超微細・超多孔構造によるものです。珪藻土の大小さまざまな細孔サイズの配分が、活発な呼吸性の原動力となっています。
細孔サイズが小さいほど活発な呼吸性を発揮するわけではないそうです。乾燥材メーカーのホームページに紹介されていましたが、細孔サイズが異なる2種類の乾燥材が製品化されており、ひとつは、湿気を吸着して乾燥状態を保つために使うタイプ、もうひとつは、過湿になれば湿気を吸い、乾燥気味になれば放湿する調湿機能タイプ。細孔サイズが小さすぎると、吸着力が強くなりすぎて、吸湿した湿気を放さなくなるそうです。
エコ・クィーン内壁材を施工したお宅2軒を、「小型温湿度記録計」で1週間測定させていただいたことがあります。屋外1カ所、室内2カ所に設置しました。冬でしたが、室内湿度は約60%で保たれ、加湿器が必要ない状態でした。屋外の湿度は激しく上下していました。気密住宅です(高気密ではありません)。いずれも、暖房器具にエアコンを使用していないお宅でしたのでよりよい結果が出たとも考えられます(エアコンや電気ストーブでは、乾燥気味になる可能性があります)。
また、真夏(午前9時から正午)に測定させていただいたお宅では、湿度計はちょうど50%をキープしていました(そこそこ正確な湿度計です)。冷房機はエアコンではなく、格子状に並んだ金属板の中を冷水が循環して部屋の空気を冷やすもので、LDKに3カ所設置していました。金属板の表面は常時結露してビショビショ状態です(下部の水受けで受けて排出する構造)。
2.結露防止
結露は、空気が冷やされることで発生します。
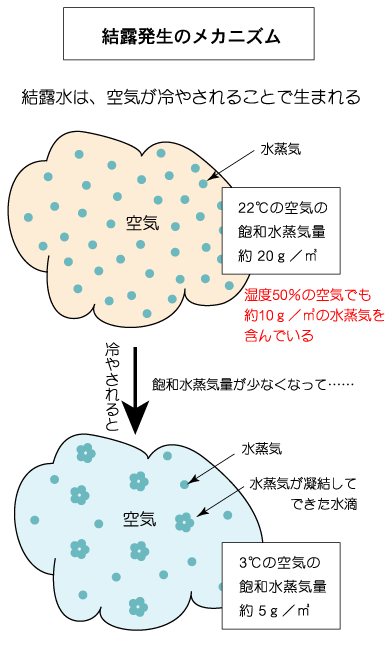
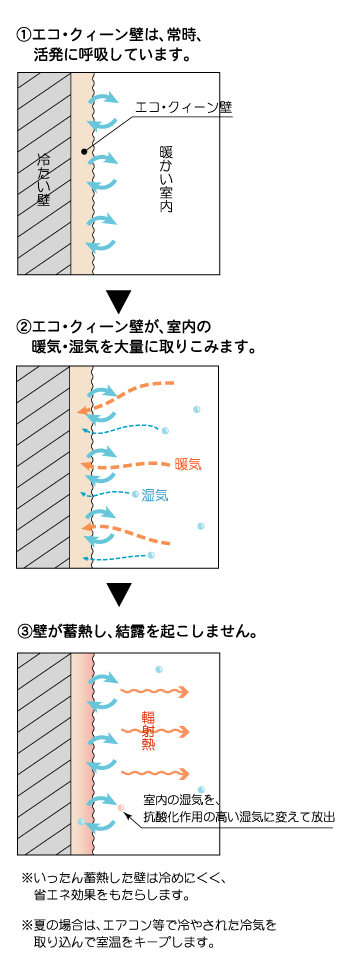
結露がピタリと止まりました。
※結露する壁には、〈ペーストタイプ〉をおすすめします。粉末タイプよりも断熱性・蓄熱製が高いと感じていますので。
3.防カビ性
当クラブの前身『家づくりお助けクラブ』のときは、屋外で『DIY珪藻土壁塗り講習会』を開いておりました。そのときに、エコ・クィーン内壁材を塗った石こうボードを雨のかからない地面の上に長期間おいていたことがあります。石こうボードの表面には黒いカビがびっしりと生えていましたがエコ・クィーンの表面にはカビが生えていませんでした。これは、エコ・クィーンがpH10〜12の強アルカリ性であることによります。強酸性もしくは強アルカリ性であれば、防カビ剤を入れなくてもカビが生えにくいとのことです。多湿な環境にも安心して使える壁材です。ただし、壁面の湿潤状態が長期間つづき、カビの生育に適した温度になると、カビが生える可能性があります。浴室内の施工の場合は、石鹸カスなどが付着しにくい天井面のみにして換気を心がけるようにしてください。もしくは、浴室内には施工をしない方がいいかも。
4.吸着作用
ナノサイズの超微細孔で超多孔構造を持つ珪藻土(木炭の5千倍の孔を持つと言われています)により、湿気のほか、ニオイ物質やホルムアルデヒドなどの有害な物質も吸着するため、敏感な方でなくても、「ニオイが消える」「ニオイが残らない」と驚かれます。
台所と書斎に施工されたT.Iさんは、お好み焼きを食べた後、洗い物をそのままにして寝たときに、以前はそのニオイが枕元まで漂ってきていたのに、まったくしなくなったと言ってました。猫を15匹飼っているお宅の奥さんは、ペット臭がなくなったと喜んでいました。なお、ニオイが消えるなどの空気清浄効果は、後で記載している抗酸化力が大きく作用しているようです。
5.省エネ効果(冷暖房効果)
珪藻土壁は断熱性と蓄熱性を併せ持っています。たくさんの微細な孔を持っていることと、壁に取り込まれた湿気(水)が保有できる熱量の大きさによるものと、私は思っています。
冬にMさん宅で、室内の表面温度を測定させていただいたことがあります。大断面の無垢の木を床・柱に使用している家でしたが、壁も床も天井も21℃〜20℃でした。その輻射熱でとても気持ちのいい環境になっていました。パネルヒーターを夜〜朝の間使用し、後は補助的に点けたり消したりしていました。気密・断熱住宅の場合、このように、室内を構成する部材の温度を一定に保つように冷暖房を行うのが正しい方法であり、断熱性と蓄熱性を併せ持つエコ・クィーン内壁材は、それに適した壁材であると言えます。
6.音響効果
これは、私自身、比較したことがないので言明は避けます。ただ、表面が固い建材で囲まれた空間では、音の反響が人の神経にさわるということが建築の本に書かれていました。超微細・超多孔構造の壁が高音域の音を吸収するそうです。
7.不燃
珪藻土は、昔から不燃材料として活用されてきた火に強い土です。七輪はその代表と言えます。エコ・クィーン内壁材を塗った板にバーナーの炎を当てても燃えることはありませんし、ビニールクロスのように有害なガスを出すこともありません。
現在の火事は炎よりも新建材が燃えて出るガスの方が恐ろしく、3〜4回吸い込むと動けなくなるそうです。10年ほど前に火事の第一発見者となって、中にいる奥さんを助けにいこうとしたことがありますが、玄関を開けると中は白い煙で5センチ先も見えず、そのきついニオイで中に入る勇気がなくなってしまいました。消火された後に奥さんは救助されましたが、中毒症で入院しました。玄関あたりで倒れている可能性もあったので、せめて手探りで玄関土間だけでも確認すべきだったと後悔しました。
万一の火事のことを考えると、室内にそのような建材は多用しないのが賢明と言えます(難しいことですが)。エコ・クィーンは、大火になるところを小火(ぼや)で済んだ実例も持っています。
8. 光触媒効果(汚れも消える分解力)
「たばこのヤニで汚れることもなく、壁がいつまでもきれい」「壁の汚れがいつのまにか消えている」「台所の壁が数年経った今もきれい」「合板下地からのアクが完全に消えてしまう」など、エコ・クィーン内壁材が持つ光触媒効果の実例は、幾度となく見てきました。
これは、珪藻土という土に微量ながら含まれている『酸化チタン』の『光触媒作用』によるものではないかと、日本ケイソウ土建材株式会社のカタログに解説されていましたが、〈エコ・クィーン〉の抗酸化作用を持つ湿気の働きも考えられます。
光触媒作用は光が当たることで起こります。『太陽光』や『蛍光灯』の光が当たると表面に付着したもの(有機物)を分解します(380ナノメートル以下の波長の光が必要。白熱球やLEDの光では起こりません。)
細菌も有機物ですので分解されます。染料系のサインペンの落書きは消えますが、顔料系のサインペンだと消えません。
ホルムアルデヒドなどシックハウスの原因物質やニオイ物質も分解します。
エコ・クィーンのアルカリ性も作用して、最終的に水と二酸化炭素にまで分解します。
詳しくは、光触媒の解説本やインターネットでお調べください。
神戸市須磨区のお宅を施工させていただいたとき、合板下地の一部からアクが出てしまったことがあります。ペーストタイプはアクをきれいに分解してくれることを経験から確信していましたので、しばらく様子を見てもらうようお願いしました。光がよく入る2階のリビングは2週間できれいに消えました。1階のトイレは、太陽光が入らず、また、照明が白熱球でしたので、『ブラックライト』をお渡しし、就寝中に点灯していただくようお願いしました。ここも2週間できれいに消え、工務店の人も驚いたそうです。
※ペーストタイプは、有機物の分解力が高い壁材です。粉末タイプ仕上材も同様の効果を持っていますが、付着した汚れ(有機物)が完全に消えるまでには、時間がかかります。

エコ・クィーン内壁材から放出される微細な湿気には抗酸化作用があることが判明しています。この抗酸化力に優れた湿気は、空気中にあるニオイ物質や有害な物質を分解して無害化します。
活性酸素も消去しますので、体内に取り込めば、好影響があると考えられます。
居酒屋『次郎長』(西宮市今津・現在休業中)で店のご主人と一緒に施工したときの話をします。仕上げ材(粉末タイプ)を半分ほど施工したときに、それまで充満していた防腐剤入り塗料〈キシラデコール〉のニオイが完全に消し飛んでいることに気づき、驚いたことがあります。壁はまだビショビショ状態です(現場の湿度は非常に高い状態だったと思います。つまり、抗酸化作用を持つ湿気が充満している状態)。この塗料は1年経ってもニオイが出るものです。翌日朝一番で現場に入ってもニオイは全くしませんでした。これは、壁材から放出された湿気の抗酸化力によるものと思われます。
「台所にいると気持ちいい」とおっしゃる方がいましたが、これも、抗酸化作用が影響していると思われます。他の部屋に比べて、湿気の発生量が多い場所だからです。
この抗酸化作用をうまく引き出すためには、湿度の管理がポイントとなります。エコ・クィーンは快適な湿度に保つ働きをしますが、空気の乾燥が続く冬などは、壁の湿気の保有量も少なくなっていき、室内湿度が40%前後にまで下がることもあります。こういうときは加湿器を稼働させるか、壁に直接、霧吹きで水分を与えて、室内湿度を50〜65%くらいにしてあげましょう。エアコンをかけすぎた場合も同様です。

クロスをはがして、書斎と台所を粉末タイプで施工。
敏感な方は、エコ・クィーンを施工した部屋に入ると、「空気が違う」と言います。
エコ・クィーンが空気をきれいにするのは、先に挙げた『光触媒効果』と『抗酸化作用』、そして、活発で旺盛な呼吸性の相乗効果によるものです。
自分なりにいろいろな本を読んで調べましたが、「空気中のイオンバランスを正常にもどす」ということだと思いました(専門家でないので間違っているかもしれませんが)。
気密で新建材を多用し(家具なども同様)、電気製品も多く使用する住まいでは、このバランスが崩れるそうで、こまめな換気をするだけで、頭痛や不眠症などが改善されるという実験がテレビで放映されていました(外の空気も汚れていますが、それ以上に室内空気は汚れているということです)。気密住宅に暮らしている人ほど、窓の開け閉めをしなくなっているのですね。常時換気設備を付けたお宅の場合でも、空気の通りが悪い場所では換気が不十分になりますので扇風機を併用するなど工夫が必要となります。
一時期、「マイナスイオン」がブームになりましたが、効果が怪しい製品が数多く出回ったことと、簡易な測定器では正しく測定できないことから今は影を潜め、日本ケイソウド建材でも、「マイナスイオン」という言葉での説明を避けています。
でも、空気清浄機能のメカニズムを突き詰めていくと、「イオン」の話になってしまうと私は思っています。