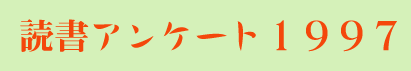
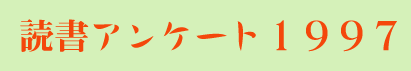
偙偙偱偼丄ICU Press 婜惉夛偑丄崙嵺婎撀嫵戝妛偺忢嬑嫵堳乮1997擭12寧18擔帪揰乯偺曽乆偵峴偭偨傾儞働乕僩傪曇廤偟偰丄弌斉偟偨嶜巕亀撉彂傾儞働乕僩丂1997亁傪岞奐偟偰偄傑偡丅WWW忋偱偺岞奐傪偛彸戻偔偩偝偭偨嫵堳偺曽乆偵屼楃怽偟忋偘傑偡丅
側偍丄岞奐偝傟偰偄傞偡傋偰偺暥復偵偼挊嶌尃偑偁傝丄偙傟偼屄乆偺昅幰偵懏偡傞傕偺偱偡丅
傑偨亀撉彂傾儞働乕僩丂1997亁偵偼曇廤挊嶌尃偑偁傝丄偙傟偼ICU Press 婜惉夛偵懏偡傞傕偺偱偁傞偙偲傪庡挘偟傑偡丅
柍抐揮嵹摍丄挊嶌尃丒曇廤挊嶌尃傪怤奞偡傞偙偲偺側偄傛偆偵偍婅偄偟傑偡丅
Hyper Text Link偺峫偊偵懃傝儕儞僋僼儕乕偲偟傑偡偑丄僼儗乕儉撪偱偺巊梡偵嵺偟偰偼丄URL偺柧婰摍怲廳側攝椂傪側偝傟傞傛偆婓朷偟傑偡丅
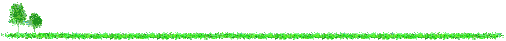
愭惗偑杮擭拞(1997.1.1乣1997.12.31)偵偍撉傒偵側傜傟偨乮側傜傟傞梊掕偺乯彂愋偺側偐偱丆師偺忦審偵揔偆傕偺傪嶰嶜傪尷搙偵偛夞摎偔偩偝偄丅
侾丏嵟嬤俆擭娫偵岞姧偝傟偨傕偺偱偁傞偙偲
俀丏摿偵報徾揑(impressive)偐偮巋寖揑(stimulating)偱偁偭偨偙偲
俁丏杮妛偺妛惗偵堦撉傪姪傔傞偵抣偡傞傕偺偱偁傞偙偲
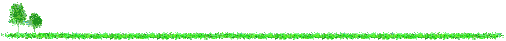
乮恖暥壢妛壢乛彆嫵庼乛僼儔儞僗暥妛乯
侾丂愇愳旤巕挊
丂丂亀帺揱偺帪娫亁
丂丂丂乮拞墰岞榑幮丄1997擭乯
丂暃戣偵乽傂偲偼側偤帺揱傪彂偔偺偐乿偲偁傞傛偆偵丆帺揱偲偄偆宍幃偵揑傪峣傝側偑傜傕丆傛傝峀偔丆傂偲偼側偤彂偔偺偐丆偲偄偆暥妛偺崻杮揑側栤偄傪丆昅幰偼屓傟偵壽偟偰偄傞丅偦偺惷偐側昅抳偲丆恖娫偺惗傊擏敆偡傞娽嵎偲偺怐傝側偡壒妝揑側巚峫偺悽奅偼丆堦庬僗儕儕儞僌偱偝偊偁傞丅
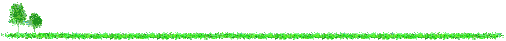
乮崙嵺娭學妛壢乛嫵庼乛崙嵺朄丒崙嵺宱嵪朄乯
侾丂僟僯僄儖丒儁僫僢僋挊乛昹柤桪旤懠栿
丂丂亀杬曻側撉彂丂杮寵偄偺偨傔偺怴撉彂弍亁
丂丂丂乮摗尨彂揦丄1993擭乯
丂偙偺杮偼丄撉彂偟偨偄偑丄杮偼嵟弶偐傜嵟屻傑偱偒偪傫偲撉傑側偗傟偽偲巚偆嫼敆娤擮揑撉彂朄偵偲傜傢傟偨恖偨偪傗撉彂偲偼壗偐傪怴偨偵栤偆恖偵慐傔傞杮丅暃戣偑杬曻側撉彂朄偺10儢忦偲偄偆偲偍傝丄偙傟傪撉傓偲彅孨偼偳偆偟偰偐杮岲偒偵側傞偲偄偆丄僼儔儞僗偱儀僗僩僙儔乕偲側偭偨撲偺杮丅偟偐偟嶌幰偑乽杮傪撉傓帪娫偼丄垽偡傞帪娫偲摨偠傛偆偵丄恖惗偺帪娫傪峀偘傞乿偲偄偆傛偆偵丄偙傟偼恖惗偺彂偱傕偁傞丅
俀丂儅儖僋丒僼僃儘乕挊乛戝栰堦摴栿
丂丂亀怴偟偄悽奅巎丂慡悽奅偱巕嫙偵楌巎傪偳偆岅偭偰偄傞偐亁
丂丂丂乮怴昡榑丄1990擭乯
俁丂暿巬撃旻挊
丂丂亀愴憟偺嫵偊曽丂悽奅偺嫵壢彂偵尒傞亁
丂丂丂乮怴挭幮丄1986擭乯
係丂幱悽婸挊
丂丂亀悽奅巎偺曄妚丂儓乕儘僢僷拞怱巎娤傊偺挧愴亁
丂丂丂乮媑愳峅暥娰丄1988擭乯
丂偄偢傟傕屆偄偑恾彂娰偵傕偁傝傑偨屆杮壆偱尒偮偐傞偙偲偑偁傞丅屆杮壆傪曕偔偺傕撉彂偺侾偮丅慜俀彂偼奺崙偺妛峑偼愴憟傪偳偆嫵偊偰偄傞偐偑庡戣丅偦傟傪捠偟偰擔杮恖偺楌巎姶妎偺撦姶偝傪嫵偊傜傟傞丅戞俁彂偼惣墷巎拞怱偺楌巎娤傪廋惓偟偰悽奅巎偺怴偨側擣幆曽朄傪嫵偊偰偔傟傞丅偄偢傟傕崙嵺幮夛偵怴偨側栚傪奐偐偣傞桳堄媊側挊嶌丅
俆丂僼僃儖僫儞丒僽儘乕僨儖挊乛嬥捤掑暥栿
丂丂亀楌巎擖栧亁
丂丂丂乮懢揷弌斉丄1995擭乯
丂1976擭偵僕儑儞丒儂僾僉儞僗戝妛偱乽暔幙暥柧偲帒杮庡媊丒嵞峫乿偲偟偰島墘偟偨傕偺偱丄僽儘乕僨儖偺柤挊亀暔幙暥柧丒宱嵪丒帒杮庡媊亁偺擖栧彂偱偁傝傑偨丄斵偺戙昞嶌亀抧拞奀厽乣叄亁乮偄偢傟傕撉傒弌偟偨傜戝妛巐擭偼偐偐傝偦偆側戝晹偺挧愴偺彂乯傪傛傝傛偔棟夝偡傞偨傔偵傕椙偄丅楌巎偲偄偆帪娫偺拞偵嬻娫傪摫擖偟丄偦偺楌巎暘愅偐傜変乆偼惗偒傞堄媊偝偊嫵偊傜傟傞丅
丂埲忋丄庡偵楌巎彂傪嫇偘偨偑丄楌巎偙偦慡偰偺妛栤偺曣偱偁傞丄廬偭偰傾儊儕僇偱偼HIS-STORY偼HER-STORY偲偄傢傟偰偄傞丠
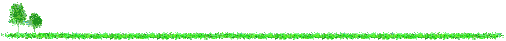
乮嫵堢妛壢乛弨嫵庼乛幮夛怱棟妛乯
侾丂媨忛廳擇挊
丂丂亀彈惈偼側偤挿惗偒偐丂挿庻偵妛傇寬峃偺僐僣亁
丂丂丂乮島択幮僽儖乕僶僢僋僗丄1996擭乯
丂妝偟偔撉傓偙偲偑偱偒傞丅壂撽偑岲偒側恖側傜偝傜偵妝偟偄丅抝惈偺庛揰偲偟偰偺幮夛揑揔墳惈偲偄偆暥尵傕側偤偐報徾揑偱偁傞丅
俀丂挿旜丂崉挊
丂丂亀燍愇僑僔僢僾亁
丂丂丂乮暥錣弔廐丄1997擭乯
丂嶌昳傪捠偟偰偝傑偞傑側燍愇憸偑採帵偝傟傞丅堄奜偲傕巚偊傞柺傕偁傞乮戣柤偺偮偗曽側偳乯丅燍愇傪偲傝姫偔恖娫柾條傕嫽枴怺偄丅
俁丂拞娵丂柧挊
丂丂亀奊夋偱撉傓惞彂亁
丂丂丂乮怴挭幮丄1997擭乯
丂帪愜奐偄偰傒偨偔側傞傛偆側乧乧丅
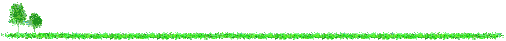
乮崙嵺娭學妛壢乛嫵庼乛崙嵺曬摴榑丒傾儊儕僇尋媶乯
丂崱夞偼丄傾儊儕僇尋媶偺帇揰偐傜丄師偺俁嶜傪慖傫偱傒偨丅
侾丂僕儑儞丒K丒僼僃傾僶儞僋挊乛姉抧揟巕丒暯栰寬堦榊嫟栿
丂丂亀拞崙夞憐榐亁
丂丂丂乮傒偡偢彂朳丄1994擭乯
丂傾儊儕僇偺拞崙尋媶偺懽搇偺50擭偵傢偨傞拞崙偲偺娭傢傝偺婰榐丅尋媶幰偺帺揱偱偁傞偲偲傕偵丄戞俀師戝愴慜偐傜愴屻偵偐偗偰偺傾儊儕僇偺傾僕傾娤偺婳愓偱傕偁傞丅
俀丂僕儑乕僕丒働僫儞挊乛娭尦栿
丂丂亀擇廫悽婭傪惗偒偰丂偁傞屄恖偲惌帯偺揘妛亁
丂丂丂乮摨暥彂堾僀儞僞乕僫僔儑僫儖丄1994擭乯
丂僜楢乽晻偠崬傔惌嶔乿偺惗傒偺恊偲偝傟傞働僫儞偵偼丄愴屻傾儊儕僇奜岎偵娭偡傞戝晹偺夞屭榐偑偁傞偑丄偦傟偲偼暿偵丄偙傟偼89嵨乮1993擭乯偺帪偵彂偄偨斵偺恖娫娤丄傾儊儕僇榑丅傗傗儁僔儈僗僥傿僢僋偵揥奐偝傟偰偄傞偑丄傾儊儕僇偺嵟崅偺抦幆恖偺堦恖偺巚嶕傪抦傞偺偵奿岲偺彂丅
俁丂儘僫儖僪丒僞僇僉挊乛垻晹婭巕丒愇徏媣岾嫟栿
丂丂亀傕偆堦偮偺傾儊儕僇儞丒僪儕乕儉丂乗傾僕傾宯傾儊儕僇恖偺挧愴亁
丂丂丂乮娾攇彂揦丄1996擭乯
丂偙傟偼尨挊偺彺栿偩偑丄捠忢偺傾儊儕僇巎偵搊応偟側偄傾僕傾宯傾儊儕僇恖偺柌偲嬯摤偺楌巎丅懡暥壔庡媊偺尒抧偐傜彂偐傟偨壓偐傜偺柉廜巎丄幮夛巎偱偁傞丅堄梸偁傞恖偼尨挊傪撉傓偵偙偟偨偙偲偼側偄丅
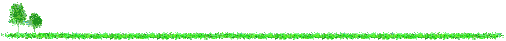
乮崙嵺娭學妛壢乛嫵庼乛崙嵺嫤椡丒崙嵺峴惌乯
丂崙撪奜傪栤傢偢丄桪傟偨儕乕僟乕僔僢僾偑晄懌偟偰偄傞崱擔丄幮夛偺暵嵡惈丄擡傃傛傞悽婭枛揑晽挭丄晄摟柧姶丄晄埨掕惈側偳偑憡傑偭偰丄偙偺傑傑偱偼悽奅偼梿慁傪昤偒側偑傜捑壓偟偰峴偔偺偱偼側偄偐偲偺寽擮偑峀傑偭偰偄傞傛偆偩丅偙傟傜偺悥惃偺攚屻偵偁傞傕偺傪抦傝丄巗柉偲偟偰丄怴偟偄幮夛偲悽奅偺峔憿傪偳偆峫偊丄偳偆憂偭偰峴偔偐丄偦偺壜擻惈傪柾嶕偡傞偺偵丄師偺彂暔偼栶棫偮偺偱偼側偄偐丅妛惗彅孼巓偵慐傔偨偄丅
侾丂嶁杮媊榓挊
丂丂亀憡懳壔偺帪戙亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1997擭乯
丂悽奅拋彉偺係偮偺僨傿儊儞僔儑儞丄偡側傢偪崙嵺慻怐丄崙壠丄巗応丄巗柉幮夛偺椡妛傪暘愅偟丄恖娫偺懜尩偲暯摍尃傪偦偺惓摑惈偺崻嫆偲偡傞巗柉幮夛偺壽戣傪尒帠偵榑偠偰偄傞丅
俀丂屆悾岾峀丒峀悾崕嵠挊
丂丂亀僀儞僞乕僱僢僩偑曄偊傞悽奅亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1996擭乯
丂僀儚儞丒僀儕僀僠偺乽僐儞償傿償傿傾儖側摴嬶乿傪幚尰偟傛偆偲偟偰僷僜僐儞偲僀儞僞乕僱僢僩傪堢偰偰偒偨恖乆偺巚憐偲峴摦偵徟揰傪摉偰丄僀儞僞乕僱僢僩偑傕偨傜偡忣曬嫟桳傗丄懡尦揑嫟惗傊偺壜擻惈偲惌嶔壽戣傪傢偐傝堈偔揱偊偰偄傞丅
俁丂Graham H. May.,
丂丂"The Future Is Ours
丂 : Foreseeing, Managing and
Creating the Future"
丂丂丂(Westport, Conn. : Praeger, 1996)
丂21悽婭傪惌嶔巚峫偺懳徾偲偟傛偆偲偡傞傕偺偵偲偭偰戝曄帵嵈偵晉傫偱偄傞丅俀丄俁偺億僀儞僩傪廍偭偰傒傞偲丄
楌巎偼梌偊傜傟傞傕偺偱側偔丄恖娫偑偮偔傞傕偺丅
偝傑偞傑側僨傿儗儞儅偑憹壛偟偰偄傞尰嵼丄枹棃梊應偼傑偡傑偡崲擄偱偁傝丄偩偐傜偙偦梊應曽朄偺夵慞偼媫柋丅
宱尡揑偵塢偭偰丄奆偑婅朷偡傞枹棃梊應偺曽偑丄奆偑朷傑側偄枹棃梊應傛傝尰幚偵側傝傗偡偄丅
丂挊幰偼塸崙Leeds戝妛偱崙嵺宱塩丄搒巗寁夋丄娐嫬惌嶔偺島嵗傪扴摉偟丄枹棃尋媶夛
U. K. Futures Group 偺庡梫儊儞僶乕丅
係
丂丂"Foreign Affairs:
75th Anniversary 1922-1997"
丂丂丂(Sept./Oct. 1997)
丂"The World
Ahead"偲戣偡傞偙偺摿廤崋偵偼丄惌帯丄宱嵪丄僐儈儏僯働乕僔儑儞丄暥壔偺奺暘栰偺榑暥14杮偑宖嵹偝傟丄姫枛偵偼夁嫀幍屲擭娫偵弌斉偝傟偨乽嵟傕寙弌偟偨彂暔乿栺幍乑嶜偑奺暘栰偺挊柤側妛幰丄愱栧壠偵傛傝慖偽傟彂昡偑側偝傟偰偄傞丅
丂戝偒側楌巎揑曄梕偺帪戙偵嬤枹棃傪揥朷偡傞榑暥偺懡偔偺傕偺偼丄怴偟偄戣嵽傪埖偄側偑傜傕丄揱摑揑側抧惌妛揑丄崙壠拞怱揑傾僾儘乕僠傪堐帩偟偰偄傞偺偑嫽枴怺偄丅堦悺晄巚媍側婥傕偡傞丅
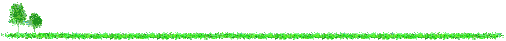
乮棟妛壢乛慜嫵庼丒尰旕忢嬑島巘乛暔棟妛乯
侾丂孌揷棽巎挊
丂丂亀乽峫偊傞椡乿傪偮偗傞杮亁
丂丂丂乮嶰妢彂朳丄1997擭乯
丂峫偊傞椡傗暔帠傪尒偮傔傞懺搙傪梴偆偙偲偺昁梫惈偼尵偆傑偱傕偁傝傑偣傫丅寉偔撉傒偒傟傞偺偵尒夁偛偡傢偗偵偼偄偐側偄杮偩偲巚偄傑偡丅
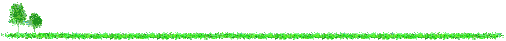
乮岅妛壢乛彆嫵庼乛塸岅嫵堢乯
侾丂 Crystal, David.丂
丂丂" The Cambridge
encyclopedia of the English language"
丂丂丂(Cambridge [England] ; New York : Cambridge University
Press, 1995)
丂尵梩偭偰偍傕偟傠偄丄恖娫偭偰偍傕偟傠偄丄偲偄偆偙偲傪嵞妋擣偝偣偰偔傟傞丅儓乕儘僢僷偺曈嫬偩偭偨僽儕僥儞搰偺尵岅偑崙嵺岅偵偺偟偁偑偭偰備偔僾儘僙僗傕傛偔暘偐傞丅塸岅妛偺僨僷乕僩偺傛偆側丄撉傫偱丄挱傔偰丄妝偟傔傞杮丅
俀丂
丂丂"The Oxford English
Dictionary. 2nd ed, CD-ROM"
丂丂丂(Oxford: Oxford University Press, 1994)
丂堦嬨敧嬨擭慡柺夵掶偵側偭偨OED偺丄CD-ROM version丅慜彂偒傪撉傓偩偗偱丄塸岅巎丄塸岅彂帍妛偺棳傟丄妛栤偲尰戙暥柧偲偺娭傢傝偑暘偐傞偟丄傂偲偮傂偲偮偺扨岅偺楌巎丄岅尮丄堄枴丄梡椺傪尒傞偺傕嫽枴怺偄丅 CD-ROM側偺偱丄偄傠偄傠側憖嶌偱娙扨偵専嶕偱偒傞丅帺暘偑惗傑傟偨擭偵惗傑傟偨扨岅傪傒偮偗偨傝丄摿掕偺嶌壠偺梡椺傪儕僗僩偵偟偨傝丄擔杮岅偐傜偺庁梡岅傪儕僗僩偵偟偨傝丄梀傇偺傕偍傕偟傠偄丅恾彂娰堦奒偺僐儞僺儏乕僞偵擖偭偰偄傞丅
丂
俁丂 Lord, Albert Bates. Mary Louise
Lord. ed.,
丂丂"The singer resumes the
tale"
丂丂丂(Ithaca and London: Cornell University Press, 1995)
丂尵梩偱梀傇丄尵梩傪寍弍偺崅傒偵徃壺偝偣傞恖娫偺傢偞丄傑偨偦傟偑彂偒尵梩側偟偵傕廩暘壜擻偱偁傝丄傓偟傠暥帤偑側偄曽偑恖娫偼尵梩偺寍弍偵挿偗傞偺偐傕偟傟側偄偲巚傢偣傞杮丅傑偨僼傿乕儖僪儚乕僋偵傛偭偰尵岅僨乕僞傪廤傔傞偙偲偺戝愗偝傕抦傞偙偲偑偱偒傞杮丅
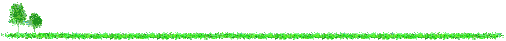
乮幮夛壢妛壢乛嫵庼乛擔杮惌帯巚憐巎乯
侾丂
丂丂亀媨揷岝梇廤乹惞彂偺怣嬄乺亁慡幍姫
丂丂丂乮娾攇彂揦丄1996擭乯
丂40擭埲忋妛惗偲惗妶傪嫟偵偟偰丄惞彂傪妛傃撉彂夛傪懕偗偰棃偨惌帯妛幰偺丄悢懡偔懡曽柺偵傢偨傞挊嶌偺僄僢僙儞僗丅
俀丂
丂丂亀摗揷徣嶰挊嶌廤亁慡10姫
丂丂丂乮傒偡偢彂朳丄1997乣1998擭乯
丂偙偺僔儕乕僘偺亀慡懱庡媊偺帪戙宱尡亁偑弌偨帪丄巹偼偦傟傪乽悽懎壔偝傟偨廔枛榑乿偲昡偟偨丅偦偙偵偼尰戙傊偺丄懠偵椶傪尒側偄怺偄斸敾偲丄偟偽偟偽尒摝偝傟傞偺偩偑丄堦庬偺廔枛揑婓朷偲偑岅傜傟偰偄傞丅朄惌戝妛偺惉郪岝巵偼丄乽挿擭摨偠怑応偱恎嬤偵愙偟偨懎暔僉儕僗僩嫵搆偱偁傞昡幰傪偟偽偟偽抪擖傜偣偨乧乧崅婱偝偑挊幰偺拞偵偼妋偐偵偁傞乿偲偺傋偰偄傞偑丄偦傟偼妛惗帪戙偐傜挊幰傪抦偭偰偄傞巹偺巚偄偱傕偁傞丅
俁丂愳揷墄巕挊
丂丂亀棿暯偲偲傕偵丂栻奞僄僀僘偲偨偨偐偆擔乆亁
丂丂丂乮娾攇彂揦丄1997擭乯
丂愳揷棿暯孨偺偍曣偝傫偺庤婰丅懡帠懡擄側擔乆偺楢懕偺拞偱丄嬃偔傎偳懡偔撉傒丄怺偔峫偊偰偄傜傟傞偺偵姶摦偟偨丅巹偺僋儔僗偵偍彽偒偟偰偍榖傪偆偐偑偄偨偄偲峫偊偰偄傞丅
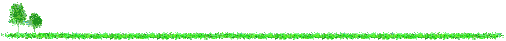
乮棟妛壢乛島巘乛惗暔妛乯
侾丂僇乕儖丒僙乕僈儞丄傾儞丒僪儖乕儎儞挊乛攼尨惛堦懠栿
丂丂亀偼傞偐側婰壇丂恖娫偵崗傑傟偨恑壔偺曕傒亁乮忋丒壓乯
丂丂丂乮挬擔怴暦幮乹挬擔暥屔乺丄1997擭乯
丂挊幰偼丄堦嶐擭媫惱偟偨桳柤側塅拡壢妛幰晇嵢丅偄傠偄傠側娤揰偐傜丄恖娫偲偄偆偺懚嵼傪尒偮傔捈偡挊彂傪彂偄偰偄傞挊幰偑丄偙偺杮偱偼丄嬤擭偺摦暔峴摦妛丄楈挿椶妛摍偺惉壥傪奣愢偟丄恖娫偑擛壗偵摦暔偲堎側偭偰偄側偄偐丄乮埥偄偼丄堎側偭偰偄傞偐乯傪栤偄偐偗傞丅
俀丂僔乕僆丒僐儖儃乕儞懠挊乛挿旜丂椡栿
丂丂亀扗傢傟偟枹棃亁
丂丂丂乮隳塲幮丄1997擭乯
丂朙晉側壢妛暥專丄僨乕僞偺挷嵏傪尦偵丄偛偔旝検側壔妛暔幙偑惗暔偺惗怋婡擻偵擛壗偵怺崗側塭嬁傪梌偊偰偄傞偐傪柧傜偐偵偟偨挊彂丅1960擭戙偵丄偦傟傑偱巊偄曻戣偱偁偭偨擾栻偺婋尟惈傪偁偒傜偐偵偟偨
丒僇乕僜儞偺悽奅揑側柤挊亀捑栙偺弔亁偺嵞棃偲尵傢傟丄傾儊儕僇傪弶傔奺崙偱戝偒側斀嬁傪堷偒婲偙偟偰偄傞丅攔悈偺墭愼婯惂抣傛傝梱偐偵旝検偺壔妛暔幙偵傛偭偰丄恖娫傪弶傔丄懡偔偺惗暔偺斏怋偵怺崗側塭嬁偑婛偵偱偰偄傞偙偲偑柧傜偐偵偝傟偰備偔丅杮彂偺撪梕偱偼側偄偑丄搶嫗偱傕丄懡杸愳偺僐僀偺懡偔偑斏怋擻椡傪幐偭偰偍傝婛偵庤抶傟偲偺挷嵏寢壥傕偁傞丅栿暥偵偐側傝栤戣揰偑巜揈偱偒傞傕偺偺丄杮彂偑栤偄偐偗傞撪梕偼懠恖帠偱偼側偄偩偗偵怺崗偱偁傞丅
俁丂儗僀僠僃儖丒僇乕僜儞挊乛忋墦宐巕栿乛怷杮擇懢榊幨恀
丂丂亀僙儞僗丒僆僽丒儚儞僟乕亁
丂丂丂乮怴挭幮丄1996擭乯
丂戣柤偺乽僙儞僗丒僆僽丒儚儞僟乕乿偼丄"帺慠偺晄巚媍偝偵嬃偒偺栚傪岦偗傞偙偲偺偱偒傞姶惈"偲偱傕偄偊傞傕偺丅擾栻偺婋尟惈傪崘敪偟偨亀捑栙偺弔亁偺挊幰偑丄帺慠偺旤偟偝丄偦傟傪姶偠傞偙偲偺戝愗偝傪嵟屻偵彂偒巆偟偨儊僢僙乕僕丅摿偵丄尰嵼埥偄偼彨棃丄巕嫙傪堢偰偰備偔庒偄悽戙偺恖偵偼惀旕撉傫偱梸偟偄侾嶜偱偁傞丅ICU偺懖嬈惗偺幨恀壠丄怷杮擇懢榊巵偺旤偟偄幨恀偑悘強偵憓擖偝傟偰偄傞丅
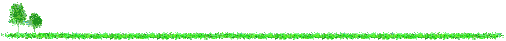
乮恖暥壢妛壢乛弨嫵庼乛廆嫵妛乯
侾丂僄儖儞僗僩丒僇僢僔乕儔乕挊乛拞栰岲擵栿
丂丂亀孾栔庡媊偺揘妛亁乹怴憰暅崗斉乺
丂丂丂乮婭埳殸壆彂揦丄1997擭乯
丂尨挊偼1932擭丄東栿弶斉偑1962擭丅崱擭偦傟偑暅崗偝傟偨丅乽偍偦傜偔恀偺孾栔庡媊傪傕偪偊側偐偭偨偙偺崙偺乧乧乿偲偄偆栿幰偁偲偑偒偺堦尵偵丄偙偺杮傪撉傓偙偲偺堄媊偑帵偝傟偰偄傞丅揘妛傗恄妛偼丄孾栔庡媊偑傢偐傜側偄偲偦偺嬤戙揑側桼棃偑棟夝偱偒側偄丅摿偵戞係復乽廆嫵偺棟擮乿偼丄偙傫偵偪偵傕媦傇孾栔庡媊揑側廆嫵棟夝偺尮愹偲摿挜傪傛偔夝柧偟偰偔傟傞丅偨偩偟丄傢偨偟帺恎偼偙偺棟夝偵棷曐偑偁傞丅
俀丂嬥巕惏桬曇
丂丂亀恖娫妛丂偦偺楌巎偲幩掱亁
丂丂丂乮憂暥幮丄1995擭乯
丂傢偨偟帺恎傕偍悽榖偵側偭偨憂暥幮偺屆嶲曇廤幰偑尵偆偵偼丄嵟嬤偼傕偆扤乆愭惗偑戅怑偡傞偐傜婰擮專掓榑暥廤傪弌偦偆丄側偳偲偄偆帪戙偱偼側偄丅弌偰偄傞偺偼婑偣廤傔偺嶌暥廤偽偐傝偱偁傞丅偟偐偟丄偙偺杮偔傜偄偵掱搙偑崅偗傟偽丄傗偼傝弌偡壙抣偼偁傞丄偲偺偙偲丅拞恎傪撉傫偱擺摼偱偒傞丅幏昅幰偵偼傢偑暲栘峗堦愭惗傕擖偭偰偄傞丅側偍丄乽恖娫妛乿偲偄偆尵梩偼丄嬥巕巵偺堦楢偺挊嶌柤偵偐偗偰偁傞偑丄幚嵺偵偼乽揘妛乿偺堦暘栰傪側傞傋偔尰戙偺庒幰偵撉傫偱傕傜偊偦偆側戣偵尵偄捈偟偨傕偺丅
俁丂Jonathan Edwards,
丂丂"The "Miscellanies,"
a-500: The Works of Jonathan
Edwards, vol. 13"
丂丂丂(Yale University Press, 1994)
丂僄僪儚乕僘寛掕斉慡廤偺戞13姫偱丄弶婜僄僪儚乕僘偺帺慠揘妛揑側榑峫僲乕僩傪丄偁傞妛幰偑暥帤捠傝惗奤傪偐偗偰曇廤偟偨傕偺丅偙偺帪戙偺抦揑惛恄偼丄恄妛傕揘妛傕壢妛傕傒側堦弿偔偨偵側偭偰怴偟偄悽奅棟夝傪惗傒弌偦偆偲嬯摤偟偰偄偨丅僄僪儚乕僘偼丄偟偽偟偽乽儘僢僋偲僯儏乕僩儞偺忋偵拻捈偝傟偨僺儏乕儕僞儞乿偲尵傢傟傞偑丄偙偺杮傪撉傓偲丄僯儏乕僩儞偲偄偆傛傝傓偟傠傾僀儞僔儏僞僀儞偲摨帪戙恖偱偁偭偨偙偲偑傢偐傞丅
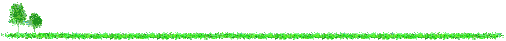
乮幮夛壢妛壢乛嫵庼乛峴惌妛乯
侾丂R丒E丒僯儏乕僗僞僢僩丄E丒R丒儊僀挊乛塒堜媣榓懠栿
丂丂亀僴乕僶乕僪棳楌巎妶梡朄丂惌嶔寛掕偺惉岟偲幐攕亁
丂丂丂乮嶰椾彂朳丄1996擭乯
丂戝摑椞尋媶偺尃埿僯儏乕僗僞僢僩偲奜岎巎壠偺儊僀偵傛傞丄僴乕僶乕僪戝働僱僨傿乕丒僗僋乕儖偱偺傾儊儕僇惌帯峴惌奜岎巎偺幚慔揑棙梡偵娭偡傞島媊傪傑偲傔偨傕偺丅尨挊偼"Thinking
in
Time"偲煭棊偨戣偩偑丄傗傗柍悎側擔杮岅僞僀僩儖偵側偭偰偄傞丅偟偐偟撪梕偦偺傕偺偼尋媶丒嫵堢柺偱懡戝側巋寖偵枮偪偰偄偨丅E丒H丒僇乕偺偄偆乽夁嫀偲楌巎壠偲偺懳榖乿偺偨傔偺傛偒庤堷偒彂丅
俀丂M丒S丒儁僢僋挊乛怷塸柧栿
丂丂亀暯婥偱偆偦傪偮偔恖偨偪丂嫊婾偲幾埆偺怱棟妛亁
丂丂丂乮憪巚幮丄1996擭乯
丂儀僗僩僙儔乕偲側偭偰曽乆偱尵媦偝傟偰偄傞偺偱鏢鏞偟偨偑丄偙傟傑偱摨條儁僢僋偺挊嶌偼恖娫傊偺怺偄摯嶡偲椶婬側傞惤幚偝偱娧偐傟偰偍傝丄嫇偘偢偵偼偄傜傟側偄丅傑偨偔傝曉偟撉傒曉偝偢偵偼偄傜傟側偄丅偨偩丄擔杮偺撉幰偑偳偆偄偆撉傒曽傪偟偰偄傞偺偐丄廃埻偺恖娫傪嵸偔偨傔偵巊傢傟偰偄傞偺偱偼偲丄婥偵側傞丅帺屓偲偺懳榖偺偨傔偵偙偦枴撉偟偨偄丅
俁丂栰杮梲戙丄R丒僂傿儕傾儉僘挊
丂丂亀僴僢僽儖朷墦嬀偑尒偨塅拡丂僇儔乕斉亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1997擭乯
丂嶐壞崙棫揤暥戜偺嬤偔偵堷偭墇偟丄怮幒偵揤憢偑偁傝丄僿乕儖丒儃僢僾渁惎憶偓傕偁偭偰揤暥妛幰偺桭恖傕偱偒丄塮夋乽僐儞僞僋僩乿傪尒偨傝偱丄惎傗寧偵恊偟傓傛偆偵側偭偨丅堦壄岝擭岦偙偆偺懢屆偺嬧壨傗惎塤偺僇儔乕幨恀傕寑揑偩偑丄恖椶偺柌偩偭偨戝婥寳奜偺僴僢僽儖朷墦嬀偑媴柺廂嵎偲傗傜偺弶曕揑儈僗偱塅拡偺崅壙側慹戝偛傒壔偟偦偆偵側傝偐偗丄偟偐偟俁擭屻僗儁乕僗僔儍僩儖偺35帪娫偵媦傇慏奜妶摦偱壗偲偐廋棟偑惉岟偟丄崱慛柧側塮憸偑尒傜傟傞偙偲偺曽偵傕僪儔儅偑偁傝丄側偐側偐尒朞偒側偄丅栭嬻偲偺懳榖傪桿偆丅
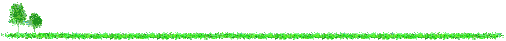
乮嫵堢妛壢乛嫵庼乛崙嵺丒斾妑嫵堢乯
侾丂Edgar Faure et al.,
丂丂"Learning To
Be: The World of Education Today
and
Tomorrow"
丂丂 (UNESCO 1972 )乛暯捤塿摽栿亀枹棃偺妛廗亁戞堦朄婯
俀丂Jacques Delors et al.,
丂丂"Learning:
The Treasure Within"
丂丂丂(UNESCO
1996)乛揤忛孧娔栿亀妛廗丂旈傔傜傟偨曮亁偓傚偆偣偄
丂忋婰偺俀嶜偺杮偼儐僱僗僐偺愝抲偟偨崙嵺嫵堢奐敪埾堳夛偺曬崘彂偱偁傞丅慜彂偼1970擭埲崀偺嫵堢偺敪揥偵戝偒偔婑梌偟丄偙傟傑偱偺嫵堢娤傪乽嫵偊傞乿偙偲偐傜乽惗奤傪捠偟偰妛傇乿偙偲偵廳揰傪曄偊偨丅堦曽丄屻彂偼21悽婭偵岦偗偨怴偟偄係偮偺嫵堢偺帇揰傪偁偘偰偄傞丅椉彂傪堦弿偵撉傓偙偲傪姪傔傞丅
俁丂Samuel P. Huntington,
丂丂"The Clash of
Civilizations and the Remaking of World Order"
丂丂丂丂(Simon&Schuster 1996)
丂奀奜偵塱偔廧傓偲丄側偤擔杮偑撈傝慞偑傝偺屒撈側懚嵼偐傛偔暘偐傞丅偙偺挊彂偼丄偦偆偟偨栤戣傪暥柧偺徴撍偲偄偆帇揰偐傜尒偰偍傝丄桴偗傞偲偙傠偑懡偄丅
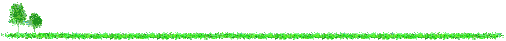
乮崙嵺娭學妛壢乛嫵庼乛崙嵺娭學榑乯
丂
侾丂嶁杮媊榓挊
丂丂亀憡懳壔偺帪戙亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1997擭乯
丂ICU偺妛惗偼抐曅揑抦幆偼偦偙偦偙帩偭偰偄傞偑丄偦傟傜偺抦幆傪摑崌偡傞榞慻偼庛偄傛偆偵巚傢傟傞丅柍堄幆偵棳峴偺榞慻偵廁傢傟偰偄傞恖傕偄傞丅偝傑偞傑側巚憐傗榞慻傪専摙偟偨忋偱侾偮偺慖戰傪偡傞偺側傜傛偄偺偩偑丄偦偺傛偆側専摙傪宱偢偵棳峴偺巚憐傪摉慠偺傕偺偲偟偰庴偗梕傟偰偄傞恖偑懡偄偺偱偁傞乮傕偭偲傕偙傟偼ICU惗偵尷傜側偄偱偁傠偆偟丄堦斒嫵堢壢栚傗婎慴壢栚偱巹偑愙偡傞婡夛偑懡偄侾丄俀擭惗偺報徾偵堷偒偢傜傟偰偄傞偐傕抦傟側偄偑乯丅
丂巹偺峫偊偱偼偙偺栤戣揰偼丄ICU惗偑楌巎傗巚憐偵偮偄偰廩暘妛傃丄峫偊偰偄側偄偙偲偲娭學偑偁傞丅杮彂偼楌巎偲巚憐偵怺偄摯嶡傪帩偮崙嵺惌帯妛幰偑挊偟偨丄尰嵼偺悽奅偺曄摦偺堄枴傪柧傜偐偵偟傛偆偲偡傞帋傒偱偁傞丅挊幰偺庡挘偺偡傋偰偵巀惉偡傞偐偳偆偐偼偲傕偐偔偲偟偰丄巚峫偑巋寖偝傟丄崱偺帪戙傪峫嶡偡傞僸儞僩偑梌偊傜傟傞偙偲偼惪偗崌偄偱偁傞丅
俀丂嶳杮怣恖懠挊
丂丂亀搶撿傾僕傾惌帯妛丂抧堟丒崙壠丒幮夛丒僸僩偺廳憌揑僟僀僫儈僘儉亁
丂丂丂乮惉暥摪丄1997擭乯
丂搶撿傾僕傾偵偮偄偰傛偔偱偒偨嫵壢彂偩偲暦偄偰攦偭偰傒偨傜丄側傞傎偳傛偔偱偒偰偄傞丅彇弎偼暯柧偱偁傞偑丄扨側傞昤幨偵偲偳傑傜側偄塻偄暘愅偑悘強偵尒傜傟丄擖栧彂偲偟偰偼嵟揔偱偼側偄偐丅傑偩偁傑傝桳柤偱側偄30戙偺庒庤俆恖偺嫟挊偱偁傝丄桳柤側弌斉幮偱傕側偄偺偱丄攧傟傞偐偳偆偐偑怱攝丅墳墖偺堄枴傕崬傔偰悇慐偟偨偄丅
俁丂Ted Robert Gurr et al.,
丂丂"Minorities at
risk : a global view of
ethnopolitical
conflicts"
丂丂丂(Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press,
1993)
丂尋媶偺儗儀儖偺崅偝偵埑搢偝傟偰偟傑偆杮偑偁傞丅偙偙偵徯夘偡傞杮傕偦偺侾嶜偵悢偊偰傛偄偱偁傠偆丅偙偺杮偺応崌偵埑搢偝傟傞偺偼壗傛傝傕朿戝側嶌嬈検偱偁傞丅偦傟傪壜擻偵偟偨偺偼僠乕儉偵傛傞嶌嬈偱偁傞偑丄擔杮偺幮夛壢妛丒恖暥壢妛偱偼偙偺庬偺恀偺堄枴偱偺嫟摨尋媶偼偒傢傔偰彮側偄丅傑偨丄悢検壔偟偵偔偄尰徾傪偁偊偰悢検壔偟偰暘愅偡傞嵺偺曽朄榑傕嶲峫偵側傞丅傕偪傠傫丄嬶懱揑側寢榑傕旕忢偵帵嵈偵晉傓丅柉懓暣憟傪宯摑揑偵暘愅偟偨尋媶偲偟偰丄昁撉偱偁傠偆丅
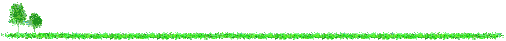
乮岅妛壢乛嫵庼乛僼儔儞僗岅妛丒尵岅妛乯
侾丂崙峀揘栱挊
丂丂亀棟憐偺崙岅帿揟亁
丂丂丂乮戝廋娰彂揦丄1997擭乯
丂壗嶜偐偺崙岅帿揟傪庢傝忋偘偰丄偦傟傜偺堄枴婰弎傪専摙偟丄挊幰偺棟憐偲偡傞帿揟婰弎傪採尵偡傞丅偨偲偊偽丄乽偁偲乿偲乽偆偟傠乿丄乽晽宨乿偲乽岝宨乿偼偳偆堄枴偑堎側傞偺偐丅擔杮岅偺堄枴偺悽奅偵桿偭偰偔傟傞愨岲偺彂丅
俀丂徏尨廏堦挊
丂丂亀僼儔儞僗偙偲偽帠揟亁
丂丂丂乮島択幮妛弍暥屔丄1996擭乯
丂摨偠挊幰偺亀偙偲偽偺攚宨亁乮1974擭乯偲亀婋側偄榖亁乮1979擭乯傪侾嶜偵傑偲傔丄壛昅丒廋惓偟偨傕偺丅傾僀僂僄僆弴偵側偭偰丄堷偒傗偡偔側偭偨丅
丂乽僷儞乿丄乽偵傢偲傝乿側偳栺90偺僼儔儞僗岅偺扨岅傪楌巎揑丒暥壔揑偵徯夘偟偰偄傞偑丄拞偵偼丄乽挶乿偲乽夐乿偼偄偢傟傕僼儔儞僗岅偱偼
papillon 偵憡摉偟丄婎杮揑偵偼嬫暿偑側偄乮塸岅偱偼 butterfly / moth
乯丄偲偄偆傛偆側偙偲傕弌偰偄偰嫽枴怺偄丅
俁丂怴栺惞彂東栿埾堳夛曇廤
丂丂亀怴栺惞彂厽乣叄亁
丂丂丂乮娾攇彂揦丄1995乣1996擭乯
丂暥岅栿偼偨偟偐偵奿挷崅偄偑丄傕偼傗屆傔偐偟偔側偭偰偟傑偭偨丅崱夞偺東栿偼僊儕僔傾岅尨揟偵拤幚偱丄怴慛偐偮嬶懱揑側僀儊乕僕偱僀僄僗偺惗奤傪姭婲偟偰偔傟傞丅儁乕僕壓偺拲傕帵嵈偵晉傓丅怴栺惞彂傪枹撉偺恖偵傕丄廬棃偺斉偵恊偟傫偩恖偵傕慐傔偨偄丅
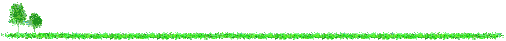
乮棟妛壢乛慜嫵庼丒尰媞堳嫵庼乛忣曬壢妛乯
侾丂懞堜丂弮挊
丂丂亀僀儞僞乕僱僢僩亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1995擭乯
丂挊幰偼僀儞僞乕僱僢僩偺擔杮偱偺尅堷幵偱偁傞丅恖娫妶摦偺怴偟偄僀儞僼儔僗僩儔僋僠儍偲偟偰偺僀儞僞乕僱僢僩偺尨棟偲堄枴傪丄帺傜偦偺峔抸偵実傢傝丄栤戣偺夝寛偵偁偭偨偭偨偄傠偄傠側妏搙偐傜榑偠偰偄傞丅
俀丂嵅攲丂泗挊
丂丂亀僐儞僺儏乕僞偲嫵堢亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1986擭乯
俁丂嵅攲丂泗挊
丂丂亀怴丒僐儞僺儏乕僞偲嫵堢亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1997擭乯
丂"嫵堢偲偼壗偐"偲偄偆栤傪峫偊傞拞偐傜僐儞僺儏乕僞偺帩偮堄枴傪尒偄偩偦偆偲帋傒偨傕偺丅乽怴乧乿偼丄峏偵僐儞僺儏乕僞偺嫵堢偱偺妶梡偺堄枴丄僀儞僞乕僱僢僩偺帩偮堄枴偵偮偄偰媦傫偱偄傞丅
係丂D丒俠丒儕儞僪僶乕僌懠挊乛搉曈惓梇娔栿
丂丂亀恄偲帺慠亁
丂丂丂乮傒偡偢彂朳丄1994擭乯
丂ICU偺壢妛巎尋媶僙儞僞乕偺帠嬈偲偟偰弌斉偝傟偨傕偺偱偁傞丅杮彂偺徯夘偼娔栿幰偱偁傞搉曈惓梇愭惗偵偟偰偄偨偩偔偺偑嵟傕揔愗偱偁傠偆丅偳側偨偐偑杮彂傪悇慐側偝傞偲巚偆偑丄傕偟傕傟傞偲偄偗側偄偺偱嫇偘偰偍偔丅
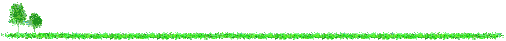
乮岅妛壢乛嫵庼乛擔杮岅妛乯
侾丂媑揷抭峴挊
丂丂亀擔杮岅偼悽奅堦傓偢偐偟偄偙偲偽丠丂擔杮岅偲悽奅偺尵岅亁
丂丂丂乮傾儕僗娰丄1997擭乯
丂巹偨偪擔杮恖偼丄帺暘偺柤傪旘揷亄椙暥乮惄亄柤乯偲偡傞偑丄塸岅偱彂偔偲丄Yoshifumi
Hida乮柤亄惄乯偲偡傞丅偄偭偨偄悽奅拞偺尵岅偱丄偳偪傜偑懡偄偺偐丅偙偆偟偨慺杙側媈栤偐傜丄偙偲偽偺杮幙偵偣傑傞尵岅妛偺擖栧彂丅巕偳傕梡偱偁傞偑丄戝恖傕廫暘妝偟傔傞儗儀儖偺崅偄杮丅
俀丂旘揷椙暥曇挊
丂丂亀擔杮岅暥復昞尰朄亁
丂丂丂乮敀掗幮丄1997擭乯
丂恖偼壗偺偨傔偵偙偲偽傪彂偔偺偩傠偆偐丅戞侾偼昁梫側忣曬傪朰傟側偄偨傔儊儌偡傞丅戞俀偼墦偔偺恖偵揱偊傞偨傔庤巻傪彂偔丅戞俁偼帺屓偺懚嵼徹柧偺偨傔丄儗億乕僩丒榑暥丒彫愢丒昡榑側偳傪彂偔丅屻悽偵揱偊傞偨傔偱偁傞丅戞巐偼峫偊傞庤抜偲偟偰彂偔丅帺暘偺峫偊傪媞娤壔偟丄惍棟偟丄暘椶偟偰丄峫偊傪敪揥偝偣傞偨傔偱偁傞丅彂偗側偄恖偺梫朷偵墳偊傞丄僷僜僐儞丄儚乕僾儘帪戙偺怴暥復撉杮偱偁傞丅
俁丂媑揷丂岶挊
丂丂亀擔杮偺抋惗亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1997擭乯
丂擔杮崙壠偺惉棫傪丄搶傾僕傾悽奅偺拞偱傒偮傔傞嫽枴怺偄暥壔巎丅崙崋栤戣丒揤峜惂丒壠偺惂搙側偳丅乽擔杮乿崙壠偑惉棫偟偰丄傢傟傢傟擔杮恖丄擔杮岅偺栤戣偑惗偢傞偙偲傪丄夵傔偰峫偊偝偣傜傟傞丅
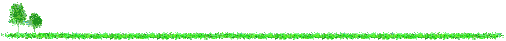
乮恖暥壢妛壢乛嫵庼乛廆嫵妛丒惞彂妛乯
侾丂彫昹堩榊挊
丂丂亀僆僂儉偲慡嫟摤亁
丂丂丂乮憪巚幮丄1995擭乯
丂僆僂儉恀棟嫵帠審傪偳偆峫偊傞偐丄偁傞偄偼偙偺帠審偑嶻弌偟偨尵愢傪偳偆峫偊傞偐偼丄尰戙擔杮偵懳偡傞帺屓偺巚憐揑僗僞儞僗傪寛傔傞偲尵偭偰傛偄偩傠偆丅媑杮棽柧巵側偳偺抦幆恖偺敪尵偲怱忣偲傪斸敾揑偵嬦枴偟偨杮彂偼撉幰偵敾抐偺妋棫傪敆傞丅
俀丂惓懞弐擵挊
丂丂亀旈枾偲抪丂擔杮幮夛偺僐儈儏僯働乕僔儑儞峔憿亁
丂丂丂乮櫎憪彂朳丄1995擭乯
丂乽抪偺暥壔乿傪幮夛堄幆偺娤揰偐傜塻棙偵暘愅偟丄擔杮恖偺怱惈偺摿幙傪採帵偡傞丅帺慠偲嶌堊偺娭學偺夝柧側偳偐傜孾敪偝傟傞偙偲偑懡偄丅
俁丂峚岥梇嶰挊
丂丂亀岞巹亁乹堦岅偺帿揟乺
丂丂丂乮嶰徣摪丄1996擭乯
丂拞崙巚憐偺愱栧壠偑丄拞崙偲擔杮偵偍偗傞乽岞乿偲乽巹乿偺奣擮偺嵎堎傪挿擭偺尋媶偵婎偯偄偰丄屆戙偐傜尰戙偵摓傞傑偱偺楌巎揑僷乕僗儁僋僥傿僽偺拞偱娙寜揑妋偵榑偠偨岲挊丅
![]()
乮恖暥壢妛壢乛嫵庼乛擔杮暥妛乯
丂崱夞偼楑壙偱寉曋側暥屔杮傗怴彂敾傪俁揰嫇偘傞丅
侾丂擔杮愴杤妛惗婰擮夛曇
丂丂亀怴斉丂偒偗傢偩偮傒偺偙偊丂擔杮愴杤妛惗偺庤婰亁
丂丂丂乮娾攇暥屔丄1995擭乯
丂偳傫側杮偐偼夝愢偡傞傑偱傕側偄偑丄崱擔偺暯榓偲斏塰偵偙偆偟偨愭恖偺懜偄媇惖偺偁偭偨偙偲偼塱媣偵朰傟偰傎偟偔側偄丅摿偵椉恊丄庒嵢丄梒側巕側偳壠懓偵埗偰偨彂忬側偳偼丄椳側偟偵偼撉傔側偄丅
俀丂徖栰廩媊挊
丂丂亀壆崻偺忋偺僶僀儕儞僈儖亁
丂丂丂乮敀悈幮乹敀悈 僽僢僋僗乺丄1996擭乯
丂偙傟偼斀懳偵寉偔撉傒偲偽偣傞杮偩偑丄塸岅偟偐奜崙岅傪抦傜側偄懡偔偺ICU惗偵丄偙偺杮偵巜揈偝傟偰偄傞傛偆側堎暥壔僐儈儏僯働乕僔儑儞傗僶僀儕儞僈儕僘儉偺栤戣傪峫偊傞偙偲傪婜懸偡傞丅挊幰偼NHK儔僕僆偺儘僔傾岅島巘傕偟偰偄偨偑丄億乕儔儞僪暥妛愱峌偺僗儔償傿僗僩丅
俁丂垻晹墄惗挊
丂丂亀働儞僽儕僢僕偺僇儗僢僕丒儔僀僼丂戝妛挰偵惗偒傞恖乆亁
丂丂丂乮拞岞怴彂丄1997擭乯
丂塸崙偺柤栧働儞僽儕僢僕戝妛偺嫵堢偲尋媶偼偳偺傛偆偵峴傢傟偰偄傞偐丄奜晹偐傜偼傢偐傝偵偔偄僇儗僢僕乮妛椌乯惗妶偺偁傟偙傟傪丄嵟嬤偺棷妛宱尡偵婎偯偄偰弎傋偨杮丅ICU偲偼戝暘堘偭偨戝妛偲戝妛惗妶傕偁傞偙偲傪嬶懱揑偵抦傝丄峫偊偰傎偟偄丅
![]()
乮嫵堢妛壢乛弨嫵庼乛嫵堢妛乯
侾丂拞搰峆梇挊
丂丂亀偱偒側偐偭偨巕傪偱偒傞巕偵偡傞偺偑嫵堢丂巹偺懱尡揑嫵堢榑亁
丂丂丂乮儈僱儖償傽彂朳丄1997擭乯
丂嫵堢幰偺乽巔惃乿偑栤傢傟傞撪梕偱偁傞丅
俀丂旜栘捈庽挊
丂丂亀尰嵼乮偄傑乯傪惗偒傞拞丒崅惗丂怱偺嫃応強傪媮傔偰亁
丂丂丂乮擔杮彂愋丄1996擭乯
丂栤戣傪偐偐偊傞拞崅惗偺巔偐傜嫵堢偺偁傝曽傪斀徣偟峫偊偝偣傜傟傞丅
俁丂恀栰堦棽挊
丂丂亀擔杮偵偍偗傞廆嫵嫵堢偺壜擻惈丂僉儕僗僩嫵庡媊妛峑偺柧擔偵岦偗偰亁
丂丂丂乮僉儕僗僩怴暦幮丄1985擭乯
丂崱擔偺僉儕僗僩嫵庡媊妛峑偼僉儕僗僩嫵嫵堢偺尨揰偵棫偪婣傞昁梫偲丄帪戙偺曄壔傊偺懳墳偲偄偆戝偒側壽戣傪書偊偰偄傞丅嫟偵峫偊偰傒傞昁梫偑偁傞丅
![]()
乮幮夛壢妛壢乛嫵庼乛恖椶妛乯
侾丂儌乕儕僗丒儗僫乕僪乛嶁堜怣嶰栿
丂丂亀僪丒儌僇丂儊儔僱僔傾悽奅偺恖暔偲恄榖亁
丂丂丂乮偣傝偐彂朳丄1990擭乯
丂乽僷儔僟僀儉偑堘偆乿偲偄偆偙偲傪丄懱尡偝偣偰偔傟傞杮丅
俀丂僂儖儕僢僸丒儀僢僋懠挊乛徏旜惛暥懠栿
丂丂亀嵞婣揑嬤戙壔丂嬤尰戙偵偍偗傞惌帯丄揱摑丄旤揑尨棟亁
丂丂丂乮帶棫彂朳丄1997擭乯
丂揱摑偲嬤戙偲偄偆擇尦榑傪挻墇偡傞偨傔偺尰戙揑側庤偑偐傝傪採嫙偟偰偔傟傞杮丅栚偐傜椮偑棊偪傑偡丅
俁丂Coleman, James S.,
丂丂"The Asymmetric
Society"
丂丂丂(Syracuse University Press, 1982)
係丂Scheffler, Israel.,
丂丂"Science and
Subjectivity"
丂丂丂(Hackett Publishing Company, 2nd ed. in 1985)
![]()
乮幮夛壢妛壢乛嫵庼乛楌巎妛乯
侾丂懞堜復夘挊
丂丂亀奀偐傜尒偨愴崙帪戙亁
丂丂丂乮偪偔傑怴彂丄1997擭乯
丂巎椏傪堷偒側偑傜擔杮拞悽偺奀帠巎傪彂偄偰偄傞揰偱儐僯乕僋丅擔棖丄擔惔偺尋媶偼偁傞偑丄乽奀偺擔杮巎乿傪偒偪傫偲彂偄偰偄傞丅
俀丂栐栰慞旻挊
丂丂亀擔杮幮夛偺楌巎亁
丂丂丂乮娾攇怴彂慡嶰嶜丄1996乣1997擭乯
俁丂戝栘丂峃挊
丂丂亀柧枛偺偼偖傟抦幆恖亁
丂丂丂乮島択幮慖彂儊僠僄丄1995擭乯
丂嫿恆偺嬶懱憸傪彂偄偰偄傞丅尐偺嬅傜側偄撉彂丅
![]()
乮幮夛壢妛壢乛弨嫵庼乛楌巎妛乯
侾丂儅儖僋丒僽儘僢僋挊乛嶿堜揝抝栿
丂丂亀楌巎偺偨傔偺曎柧丂楌巎壠偺巇帠亁
丂丂丂乮娾攇彂揦丄1956擭乯
丂尰戙偺楌巎妛偵妚柦傪偍偙偟偨嶨帍亀傾僫乕儖亁憂愝幰偺傂偲傝儅儖僋丒僽儘僢僋偺彂丅儐僟儎恖偲偟偰儗僕僗僞儞僗塣摦偵恎傪搳偠丄僪僀僣孯偵傛偭偰廵嶦偝傟偨偙偺婬桳偺楌巎壠偺偙偲偽偵丄惀旕帹傪孹偗偰梸偟偄丅乽僷僷丄楌巎偼壗偺栶偵棫偮偺丠乿偲偄偆彮擭偺栤偄偵丄斵偼偦偺妛幆偺偡傋偰傪孹偗偰丄暯堈偵偙偨偊傛偆偲偟偨丅妛幰偲偟偰丄偦偟偰傑偨恖娫偲偟偰偺惤幚偝偵怱懪偨傟傞丅巹偼楌巎傪妛傃偼偠傔偨偲偒丄偙偺彂偵弌夛偆偙偲偑偱偒丄岾偄偱偁偭偨丅
丂側偍丄尨挊偼Bloch, Marc Leopold Benjamin., "Apologie pour
l'histoire ou metier d'historien" (Paris: Librairie Armand Cdzn,
1949)
![]()
乮幮夛壢妛壢乛嫵庼乛惌帯巚憐巎乯
侾丂Ernest Gellner.
丂丂"Conditions of
liberty : civil society and its
rivals"
丂丂丂 (New York: Allen Lane/Penguin Press, 1994)
丂怴偟偄巗柉幮夛榑偑崱丄墷暷彅崙偱媍榑偝傟偰偄傞丅偦偆偟偨拞偱杮彂偼丄偡偖傟偨摯嶡偲巚嶕傪偨偨偊偰偄傞岲挊偲偟偰昡壙偑崅偄丅1950乣60擭戙偺傢偑崙偺乽巗柉幮夛榑乿乮撪揷媊旻巵丄崅搰慞嵠巵丄暯揷惔柧巵側偳乯偲斾妑専摙偟偰傒傞偺傕丄嫽枴傇偐偄壽戣丅
俀丂C. Douglas Lummis.
丂丂"Radical democracy"
丂丂丂(Ithaca: Cornell University Press, 1996)
丂俠丒僟僌儔僗丒儔儈僗偱側偄偲彂偗側偄乽儔僨傿僇儖丒僨儌僋儔僔乕榑乿丅乽儀暯楢乿偵傒傜傟傞60擭戙丄70擭戙偺擔杮偱偺巗柉塣摦傊偺挊幰偺偐偐傢傝傕丄杮彂偺攚宨偵偁傞偲峫偊偰傛偄偱偁傠偆丅崱擔偺悽奅偵偍偗傞僨儌僋儔僔乕偺棟榑揑偍傛傃幚慔揑堄枴偵娭怱偺偁傞岦偒偵偼婱廳側挊嶌丅
俁丂壛摗丂愡挊
丂丂亀撿尨斏丂嬤戙擔杮偲抦幆恖亁
丂丂丂乮娾攇怴彂丄1997擭乯
丂嬤戙擔杮偺惌帯揘妛幰撿尨斏偺屄恖偺intellectual
history偑丄嬤戙擔杮偦傟帺懱偺intellectual
history傪丄堦柺丄撈摿偺巇曽偱塮偟弌偟偰偄傞偙偲偵嫽枴傪偍傏偊偨丅
![]()
乮岅妛壢乛嫵庼乛尵岅妛乯
侾丂Ma Bo,
丂丂"Blood Red
Sunset: A Memoir of the Chinese
Cultural
Revolution"
丂丂丂 (Penguin, 1995)
As I believe reading the literature of a country can help me
understand its vulture and ways of thinking, I read Ma Bo's memoir of
his experience during the cultural revolution. His very honest and
straightforward account was an eye-opening experience.
俀丂Su Tong,
丂丂"Raise the Red Lantern"
丂丂丂(Penguin, 1993)
As I had seen the movie of the same title, I decided to compare it
with the novel and became even more fascinated by the story of life
in a large, wealthy Chinese family of the pre-Maoist rea. In
particular, I learned more about the role of women and wives in such
families.
俁丂Michael Agar,
丂丂"Language
Shock: Understanding the Culture
of
Conversation"
丂丂丂 (William Morrow, 1994)
Agar is a well-known American ethnographer, who is
able to make his subject matter accessible to non-experts. While
looking for a textbook to use with ICU students, I found his very
readable, enjoyable, and enlightening.
係丂Herbert H. Clark,
丂丂"Using Language"
丂丂丂(Cambridge University Press, 1996)
A well-known psycholinguist, Clark's new book is
an argumentation on reasons language use is really joint action of
speaker and listener behaving in coordination with each other. He
brings together cognitive and social processes to explain
interactions. This book represents a decade of his careful,
insightful experimental work and thinking.
![]()