|

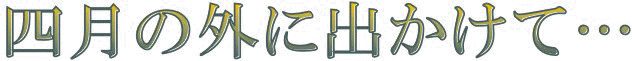

街路樹のある通りを走りぬけていた時のことです。目がチカチカして、思わずバイクのブレーキをかけまし た。そのとたん「ハッハッ…ハクショーン!」
「あー、かぜでもひいたかな。それともおれもついに花粉症とやらになったのかな」
私は郵便配達人です。同じ職場の仲間が休みをとったので、今日はいつもとはべつの配達区をまかされました。それでちょっと勝手がちがい、まよいながら町の中を走っていました。
「こんな日にかぜになったら最悪だな。おっと、どうやらこのへんだぞ」 手紙のあてさきの住所をたしかめながら、私はあたりを見まわします。並木の枝先には、明るい緑があふれています。
「あった、ここだ。ここだ」 それはなんとも奇妙な感じのするアパートでした。正面玄関にはりっぱな円形の太い柱が四方に立っています。でも建物全体はとても古ぼけて見えるのです。上のほうを見上げると、たぶん六、七階建ての高さでしょうか。なんだかのしかかるような感じで、かたむいて見えます。壁にはあちこちひびができています。
「やれやれ、この手の古いアパートには、だいたいエレベーターなんてないんだよな。おや…?」
入口のガラスごしにのぞくと、おどろいたことにドアマンが立っています。ホテルならまだしも、こんなオンボロ
アパートになんでドアマンが立っているのでしょう。中に入ってさらにめんくらったのは、郵便受けがないことです。
「おや、ここは郵便受けがないんですか」 ドアマンに声をかけました。
「ええ、ごらんのように古いつくりでね。各部屋のドアについているんですよ。部屋番号は?」
「1302…。これって13階ってことですかね?」
ドアマンはニヤニヤわらってうなずくと、変な目配せをしました。そして自動ロックのドアを開けてくれたので す。
1階の廊下のまん中ぐらいに、エレベータがあったのは意外でした。中に入ってボタンを押してから奇妙なことに気がつきました。15階まで表示があるのです。
「このアパート、外からは七、八階ぐらいにしか見えなかったぞ。俺が押したのは13階…」
上にあがっていくにしたがい胸が苦しくなってきました。キューンと音がして13階でドアがあきます。一歩ふみだしてみると、暗くカビくさい廊下が左右にのびています。窓がなく、まるでばかでかい筒の中に入りこんだような気がします。床には古ぼけたじゅうたんが敷いてあります。一足ごとにひっかかり、歩きにくいったらありません。こんな気味の悪いアパートは初めてです。しかし配達人は手紙を届けねばなりません。
「おじさん!」
とつぜん声をかけられ、ギクリとして立ちどまりました。子どもの声のようです。
「だれだ、どこにいるんだ…」
「ここよ…」
かぼそい、すきとおるような声です。暗くぼんやりとした柱のかげから、一人の少女が現われました。
「どこへいくの?」
そう問いかける少女の目を見て、私はゾッとしました。大きな瞳はどんよりとにごって、遠くを見ているようで
す。なぜか死んだ人を思わせる瞳の色です。
「1302号室ってどこだか教えてくれる?」
すると少女は
「郵便屋さんが1302号室はどこかって私にきく…。郵便屋さんが1302号室はどこかって私にきく…」
と呪文のようにつぶやくのです。それからフッと目を合わせ
「私と約束をしたなら教えてあげてもいいいわ」
「どんな約束?」
「なぞなぞをといて、私といっしょに出かけるの」
「オーケー、なぞなぞならおじさんも大好きだ。さ、問題を出してごらん」
「あのね、この駅から終点までいくらかかるか」
「この駅?アパートの中に駅なんてあるわけないじゃないか」
この子は大人をからかっているのだろうか。すこし声を荒げてにらみつけました。そんなことを気にするようす
もなく、少女は両手を広げて、おどるように一回転しました。すると、少女の姿がかきけすように見えなくなった
のです。そして、ふしぎふしぎ。さっと霧が晴れたかと思うと、そこに古そうな駅が現われました。
「これはなんだ。いったいどこの駅?」
私は野原のまんなかの、小さなひなびた駅の前に立っていました。背後からわらい声がします。
「あははは…。早くなぞなぞといて。そこにいると火がつくよ」
「火がつくってなんのことだ?」
わけがわからずにいると、線路のむこうで、ほんとうに火が燃え上がっています。キナくさいにおいがして、こ
ちらにせまってくるようです。
「早く早く、お金をいれてキップを買うのよ。電車がきたらとび乗って」
歌うような、からかうような少女の声がします。 どこからか、線路づたいに音がひびいてきます。
「ああ、本当に電車がくる…」
私は目の前の自動券売機に飛びつきました。
「150円、200円…?いったいこれはいつの表示だ」
100円が1円の単位に変わったのは、もう10年も前の話、西暦が2001年になった年のことです。私の頭は混
乱してきました。「冗談じゃない。100円なんてコイン、俺は持ってないぞ」 すると耳のそばで少女の声がしました。
「だいじょうぶよ。ただいくらかかるかあてればいいの」
「終点までだ!最後の駅までいって1302円。これでいいいだろう」
終点駅の表示を押すと、しずしずとキップが出てきました。ちゃんと1302円と印刷されています。
「それでいいのよ。さあ電車が来たわよ…」
窓の外を緑の林が線を引いて通り過ぎていきます。私はぼうぜんとして、少女を見つめていました。アパート
の中で会った時は、まだ7、8歳にしか見えなかったのに、今は背たけもずんとのびて15歳ぐらいに見えます。でも一番驚いたのはあのにごった瞳が、少し変わったように見えることです。悪魔のようにギラギラしていた瞳が、悲しみを帯びた色に感じられたのです。あまり私が見つめていたせいでしょうか、少女はプイと横をむきました。
「私たちはどこへいくんだ」
少女はニンマリとわらって
「終点よ。決まってるじゃない」といいます。
「そうか、終点。で、そこはどこなんだ。なんていう場所?そこからどこへいくんだ」
「4月の外…」
「えっ、4月の外?…」
私は思わず、あたりを見回しました。そういえば今は4月です。森のキラキラとした若葉が燃えあがるようです。日は高い所にあって、地上にまぶしいばかりの光を注いでいます。
「こんな日に亡くなったのよね」
「え…?」
「死んじゃったのよ。私のおじいちゃん」
「そ、それはお気の毒だったね。じゃあ君はおじいさんのお葬式にいくところなのかい」
「ふん、葬式なんか…。死んでからいったってだれもよろこばないもの。それにおじいちゃんがなくなったのは、
私が子どもだった時…」
今だってまどもじゃないかと言おうとして、私は口をつぐみました。前の席に座っているのはあきらかに大人の女の人です。さっきよりもさらに成長して、20歳ぐらいに見えます。
ほかの座席の人が気になって私はキョロキョロあたりを見ました。しかし乗客の目に気がつくと、ハッとして下を向いてしまいました。あきらかに、かれらは私たちの会話に興味を持って聞き耳を立てていたのです。
「私の名はマリカ。おじいちゃんは、私が8歳の時死んだの」
マリカは窓の外に顔をむけたまま、遠くを見る目つきで話します。
「私は会いたくなかった。とても大好きなおじいちゃんだったのに。でもベッドに横たわっているおじいちゃんは、醜くなってその上怒りっぽくて、同じ人とは思えなかったのよ。母やまわりの人がみまいにいくよう何回も言うんだけど、そのたびにかんしゃくを起こして絶対行かないとがんばったのよね。そのうちおじいちゃんは亡くなったわ」
「それで後悔したの?」
「いいえ、なぜかすぐ忘れちゃったの。無理に忘れようともせずに」
マリカはこちらへ顔を向けてほほえみました。その時電車が止まったのです。乗客がつぎつぎおりていきます。
「さ、ここが終点。私たちもおりるのよ」
駅を出ると、私はマリカについて歩きはじめました。郊外の小さな町のようです。おそろしく古ぼけた家並みが続きます。垣根の向こうに見える家のようすは、灰色のうすい板をはりあわせた壁、黄ばんだ障子と細い縁側の廊下…まるで写真で見た、前世紀なかばごろの光景です。
「私がおじいちゃんのことを思いだしたのは、20歳をすぎてからのことなの」
マリカの話かける声で、私は我にかえりました。
「母が教えてくれたの。どんなに私のことを待ってたかって。死んでも死にきれないと、おじいちゃんは泣いてたそうよ」
そういうと、マリカはたえきれないといったように、はらはらと涙をこぼしました。
「おいおい、こんなところで泣くなよ。人が誤解するじゃないか。涙をふいて。きみがいきたいところにいってあげるから」
「ほんとう?じゃあ郵便屋さん、ぜひお願いしたいことがあるのよ。あなた、もちろんあの手紙もってるね。1302号の番号がついている…」
町はずれの病院へつくと、マリカは急にそわそわしはじめました。
わかるかしら。私、この手紙おじいちゃんのために心をこめてかいたの。大人になって後悔してもまにあわないかもしれないけれど、なんとかおじいちゃんが死ぬ前に私の気持ちをつたえておきたいの」
「まかせておけって、俺は郵便配達人だ。1302号室ににおじいちゃんがいるんだね」
私はさっそうと病室へ向かいます。
病室のドアをあけたとたん、あたりで「ワアーッ」という恐怖にみちた声がしました。なにごとだろうと後ろをふりかえると、ひきつった顔の医師や看護婦が私を注目しています。そのとたん突風がふいて、私はよろよろと部屋にころがりこみました。
「なんだ、お前は!」
耳がわれるような声がして目をあげると、そこには信じられないほど巨大な怪物がいました。灰色の体は水袋みたいにブヨブヨとして、ベットから一部はたれさがっています。目玉はギラギラとにぶく光り、飛びだしそうです。私はちぢみあがり、声がふるえました。
「あなたの孫のマリカさんから、手紙をあずかってきました。ほらここにあります」
「孫娘のマリカから手紙だと…!見せてみろ」
私はカバンから例の手紙をとりだし、おそるおそるさしだしました。手紙をひったくるとマリカの祖父は封をひらき、よだれを流しながらなめるようにして手紙を読みました。読み終えた怪物はカッと目を上げ、私をにらみつけます。その皮膚はたちまち緑色にかわり、湯気がでています。
「お前はマリカの手先か?」
「え、え…手先?冗談じゃありません。私はただの郵便配達人です」
「ふわっふわっふわっ…。なるほど見るからにただの郵便屋だ。だが俺がだませると思うか。このトンチキ野郎」
「なにをいうんです。マリカさんは大人になってから、あなたに会わなかったことをとても後悔しているんです。だからあなたにこの手紙をなんとかして渡したいと、泣いていましたよ」
「だまれ、このおたんこナス!この手紙になにが書いてあると思うか。いいかバカ娘はこう書いている。
『おじいちゃん、今は2010年。マリカも60歳になりました。20歳ぐらいのふりはできるけど、8歳の子どもになるのはとてもむずかしいの。おじいちゃんおねがいよ。おじいちゃんが亡くなったとき、私はまだ8歳で歳をとるってことの意味が分からなかったの。でももうだめ。どんどん歳をかさねていくということ、あともどりはできないってことが分かったの。おじいちゃんは、千年も長く生きてきたと、おかあさんから聞きました。その秘術はもっとも愛した孫のうちのだれかにさずけるんだってことも。それって私のことでしょう。どうか教えてくださいな。そして返事はこの郵便屋さんに渡してね』…どうだ、とんだバカ娘だろう」
私は大きな口をあけて、その場につっ立っていました。
「ほんとうになんて娘だ。でも私はどうしたらいいんです。そのバカ娘のおかげで、こんなところまで来たんですよ」
「知ったことか。さっさと俺の前から消えうせろ!」
そういうと、怪物はフウーッと息を吹きつけました。ものすごくくさい風がふいて、私は宙に飛びました。開いていたドアを通り、病院の玄関からさらに外にでます。その時、耳もとで「ギャーッ」という声がしました。マリカが病院の玄関口に立ち、ものすごい形相でどなっています。
「返事は、返事は?…」
私はだまって首をふりました。
「あんたって、ほんとうに役立たずの郵便屋ね!」
くやしそうに歯がみをしながらマリカがかけよってきます。しかし私は春風にのって、空の高みへと飛ばされました。
ふと気がつくと、私はあのアパートの暗い廊下に倒れていました。カビくさいにおいがはなをつきます。顔をしかめて立ちあがり、ヨロヨロと壁づたいに歩きました。やれうれしや、エレベーターはもとのところにあります。
私はあたりを見回しました。どこか柱の陰にでも、マリカがひそんでいやしないかと思ったのです。
一階に無事におりるまでは、私の胸はドキドキしていました。内扉からそっと外を見ると、ドアマンがまだそこにいます。
「あいつもあやしかったぞ」と思った私は、ふりむきもせず玄関から飛び出していきました。すると後ろのほうで、ドアマンがけたたましく笑いながら声をあびせました。
「このつぎはだまされんなよ!」
|
|

作品に興味を持って下さった方はe-mailでこちらにご連絡下さい。

 連絡先
連絡先
Translation in English
Copyright © Clover Multi-lingual AS

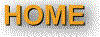
|
![]()
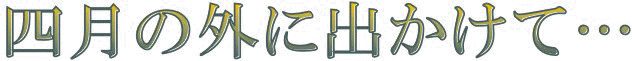
![]()

![]()