百合ヶ丘教会の神父さまはカナダ人。ジャン・ギ・デュポン神父さまです。ケベック外国宣教会の所属で、1957年に日本へ来てからもう40年になります(滞在期間は33年間です)。わたしたち信徒のだれもに深く尊敬され、信頼されている神父さまは、とっても気さくで暖かいひとです。故郷のことや、司祭になったわけなど色々とお話をうかがいました。(インタビュー:ラブ康子)
きらいな食べ物は?ーー「そうですね、こんにゃく、納豆、ピーマンとそれから貝類もだめですね。」それでは、好きな食べ物は?ーー「うなぎ、それと日本料理はなんでも好きです。麺類も、そば、ラーメン、そうめん、何でも大好きです。日本にいて食べ物で不自由なことはありませんね。」
外見はりっぱなガイジンだけれども、中身はほとんど日本人なんじゃないだろうか?「なにか、中途半端な感じじゃないですか?」
カナダへ帰ると、おまえはもうカナダ人ではないと言われます。考え方や表現が「はっきりしない」「あいまいだ」と言われるんです。日本では「へんなガイジン」。まあ、「宇宙人」みたいなものです。
独特のおでこがデュポン神父さまのトレードマークだが、とても心の広い、暖かな人柄はみんなに尊敬されています。かなりの仕事魔で、「働きすぎ」を心配する信者の声もあります。神父さまには、いつまでも元気で、頑張ってもらわなければ困るんです。
健康のために近くのプールに週2回かよっています。だいたい、1時間ぐらい泳ぎます。ひとりでくつろぐときには、私は映画を見るのが好きですから、いないときに録画しておいた映画を見たりします。それに、本を読むことも好きです。
神父さまは1930年1月、カナダのモントリオール生まれ。町の中心部で生まれたが、2才のときに市内の北のほう、St.Denisという通りへ引っ越してそれ以来ずっとそこで過ごした。家族はご両親と2才年上のお姉さん。ケベック市に住んでいるお姉さんには3人の子供と5人の孫がいらっしゃる。 ケベックというところは圧倒的にカトリックの強い地方なのだが、神父さまが司祭になることを志したのはいつ頃のこと、どういうきっかけがあったのでしょうか?
「司祭になって、41年ですが、振り返ってみると、やはりこれは神様の導きだったと思います。」お話によれば、神父さまの家庭は、ごく普通の信者で、特別に信仰が篤かったわけではないそうです。日曜日には家族全員で教会へ行くけれど、その当時よく見られたように家庭で熱心に日々の祈りをしたりするようなことはなかった。20才ごろには、医者になるか司祭になるかと迷っていたが、人の役に立ちたいという気持ちが強く、「心を癒す」、「心を育てる」仕事、つまり司祭への道を選ぶことになりました。そして、どうせ司祭になるのなら、法人司祭ではなく宣教師になりたいと強く希望していました。
神さまの言葉が心の支えになった経験が私にもよくありました。そういう経験を多くの人々と分かち合いたかったんです。それに、どうやら私は少年のころから冒険心が強く、15才のころからヒッチハイクをして友人と遠くへ旅行したりしていました。それで、遠い知らない外国へ行くことにあこがれていたんですねえ。
ケベック外国宣教会へはいって5年間神学校で学び、56年に叙階、日本へきたのは57年、27才の時でした。もちろん第二バチカン公会議の前だから、宣教師としてどこへ派遣されるかは、完全に目上の命令で決まります。当時神父さま自身も、いっしょに勉強した仲間も、まさか「デュポンが日本へ派遣される」とは思っていなかったそうです。当時のケベック宣教会の派遣先はフィリピン、日本、中南米。ケベック州はフランス語圏です。本人も仲間も、英語のできるデュポン神父はフィリピンへ行くだろうと思っていました。神父さま自身も、日本での布教はむずかしいし、日本語もむずかしいと聞いていたので、フィリピンのほうがいいと思っていたそうです。
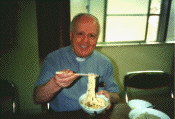 そして、いよいよ日本へ。2年間、東京の日本語学校で勉強した後、青森県の弘前教会へ、そこで7年間働いた時、宣教会の総長が日本に来ました。当時ローマからの指示で世界中の宣教会が南米に司祭を送るようにということになったそうです。日本からも何人か南米に派遣されることになり、デュポン神父さまを含む6名が南米に行きました。最初はメキシコで4カ月間スペイン語を勉強して、その後アルゼンチンへ・・。
そして、いよいよ日本へ。2年間、東京の日本語学校で勉強した後、青森県の弘前教会へ、そこで7年間働いた時、宣教会の総長が日本に来ました。当時ローマからの指示で世界中の宣教会が南米に司祭を送るようにということになったそうです。日本からも何人か南米に派遣されることになり、デュポン神父さまを含む6名が南米に行きました。最初はメキシコで4カ月間スペイン語を勉強して、その後アルゼンチンへ・・。
もう日本へは戻らないだろうと思っていました。ところが9カ月後に総長から電話がありました。私の母が重い病気になったから、帰りたければモントリオールへ帰れということだったんです。故郷へ帰り、病院へ駆けつけると、不思議なことに、それまで意識がなく昏睡状態だった母が意識を取り戻し、低い声で「おまえが帰ってきたから私もうちに帰ります。」と言ったんです。医者も奇跡だと言ったんですけど、本当にそのとおりになったんです!
その後3年間、神父さまはモントリオールにいて、お母さんの看病をしながら、近くの日本人のカトリックセンターで日本人の世話などををしていたそうです。このときの日本人との交流をとおして自分の召しだしは日本で宣教することだと確信した神父さまは、お母さんが亡くなったあと、迷わずに再び日本での宣教活動に戻ったのです。1971年でした。そして、世田谷の赤堤教会で13年間、弘前教会で2年間主任司祭を務め、今度は病気になったお父さんのめんどうを見るために3年間カナダへ帰国しました。
両親のために2回も帰国できたことは大きななぐさめです。宣教会にはいった時には、もうそんなことは出来ないと思っていました。特別な恵みと思っています。
再度、1988年に日本へ戻ってきた神父さまは、百合ヶ丘教会に着任するまでの1年間はあちらこちらの教会の「留守番」司祭をしていました。そして、横浜教区で仕事がしたいと司教さまに申し出て、戸塚教会に着任したのが、事件でボアベール神父さまが亡くなる3週間前でした。そういうわけで、「まだ根を下ろしていないから動きやすい」ということで、百合ヶ丘教会の後任を頼まれたとき、迷わずに、ボアベール神父さまの建てたこの教会へ来る決心をしたのです。ただし、教会とは別のところに住むという条件つきで・・。
1989年3月31日、百合ヶ丘教会の創設者でもある前任のボアベール神父さまは教会3階の司祭館で何者かに殺害されました。いまだに解決されていないこの事件の衝撃が非常に大きく、直後の混乱が大変なものだったことは、直接事件を体験していない私のような者にも簡単に想像できます。そして、それから8年。この共同体をここまで活気のあるものに盛り立てて下さったデュポン神父さまの功績に感謝する信徒の声をよく耳にします。
 大切なのは「共同体をそだてる」ということだと思います。外へ向かってキリストの精神を広めるためには私たちは何をすればいいのか、いろんなことをやって考えてもらうことです。宣教する精神をこの共同体のなかに広めたいのです。
大切なのは「共同体をそだてる」ということだと思います。外へ向かってキリストの精神を広めるためには私たちは何をすればいいのか、いろんなことをやって考えてもらうことです。宣教する精神をこの共同体のなかに広めたいのです。
私が来たときに、すでにボアベール神父さまによって、そういう基盤はできていました。ボアベール神父さまは何でも信徒にやらせるという精神を持っていました・・。命令するのではなく、自発的にやってもらう。責任を持って信徒が考えて実行する。とても活発な教会になりました。今だって、たとえば、インターネットのこと(!!)、典礼研修会、去年の「ミサについての展示会」、配食ボランティア「もみじの会」やいろんなサークル活動も盛んです。「囲碁教室」のように信者ではない人たちにも教会へ来てもらおうと始められたものもあります。こういうふうに広い心をもって活動し、外に出て横のつながりを作るような積極的な信徒の活動は、主任司祭としては嬉しいし、とても助けられる気がします。
若い人たちのことについては、青年会が活動していないのは残念ですけれど、中高生会は活発です。将来に希望を持ちましょう。教会はみんなのものです。いろんな世代の人たちがお互いに広い心を持って、尊敬し合い、譲り合って、生き生きした共同体になっていくようにしたいですね。自分たちの力だけじゃなく、大切なのは神に信頼して、聖霊のはたらきを信じることです。
教会でもいろんなことがありますが、ひとりひとりが自分を過信することなく、あきらめることなくやっていくことが大切なんですね!神父さまどうもありがとうございました。
主任司祭デュポン神父へメールをどうぞ