 |
全国長南会 | ホーム / 長南氏年表 / 世帯数 / 長南氏歴史物語 / 著書の紹介 |
| 中村就一の紹介 / リンク / 掲示板 |
| ふるさと長南大結集(だいけつじゅう)・紅花まつり 2007年6月16日~17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名勝松島を創った長南和泉守 子孫の黒松お供551年ぶり故郷に還る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
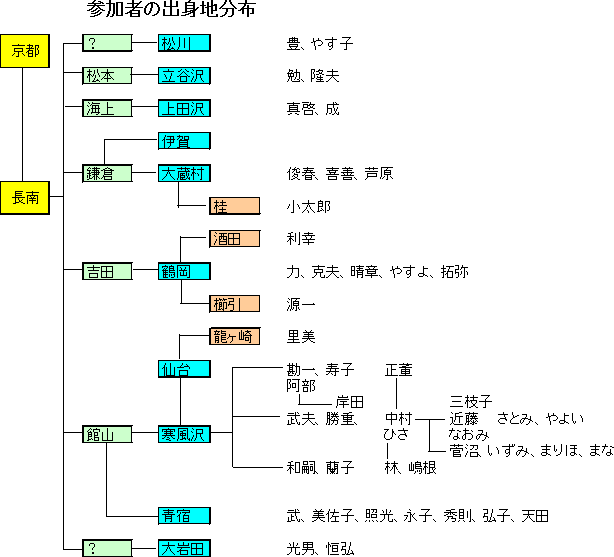
 |
熊野神社 熊野神社の御祭神ならびに 神社創建の長南次郎をはじめ 先祖の皆様に申上げます 皆様は平安時代の昔からこの地で紅花を育て、平和に 暮らしておられましたが 子孫は戦乱の世に各地に分かれ それぞれの生活を築いて 今日に至りました 中でも長南和泉守菅原道本 は黒松を取り寄せて 名勝松島を創り、一族の名を上げました しかし、和泉守はじめ先祖の皆様は、子孫は必ず 長南の地に還れと叫び続けられたことにお応えして 本日ここに全国各地の子孫が御前に集い 松島の黒松子孫を献木致しました この黒松を憑代として 末永くお鎮まりください 我々子孫はこれからも家業に励み ご先祖の名を はずかしめないことを ここにお誓い申上げます 2007年6月16日 全国長南会 長南 俊春 |
|
| 熊野神社 | ||
 |
笠森寺 謹んで十一面観世音菩毎に礼拝し 長南氏のご先祖さまに申上げます 長南氏は平安の世にこの地に居を定め 長南小次郎滋道は 笠森寺の本堂建立に与力しました 後の世に至り 法難の日蓮上人が この寺に身を寄せるやその供養に力を捧げ さらに近世には石灯篭を寄進するなど 信心の誠を尽くして参りました 今日ここに子孫が全国から集まり 祖先の偉業を偲び これからも一層 家業に励み 祖先の名を はずかしめないことを お誓い申上げます 2007年六月16日 全国長南会 芦原貴美大 |
|
| 笠森観音 | ||
 |
長福寿寺 平安時代から 長南の庄 三途台の地に居を定め ここに別邸を営んだ長南氏は 十四代長南光重の時代に 鎌倉で法難に並われた 日蓮上人を ここに迎えて供斉し一族をあげて帰依しました 日蓮上人は その志を尊び 長立山光重寺の 号を授けられました 後に戦乱の世となり 子孫がこの地を去った後は 日蓮宗の寺となり 当時の長南氏の名に ちなんで 本詮寺と名づけられました 本日ここに 故郷長南めざして 各地から 子孫が相つどい日蓮上人のご恩と 長南のご先祖様の偉業を偲び 私たちは これからも 家業に励み ご先祖の名を はずかしめないことを お誓い申上げます 2007年6月16日 全国長南会 菅沼 孝治 |
|
| 長福寿寺 |
|
四街道市史編纂 樋口誠太郎 1.はじめに 熊野神社の縁起に長南庄開拓の祖である、長南次郎滋殖が従者の大木新九郎を紀伊熊野本宮に遣わし御分霊を受け、打出ケ岡に奉祀したとあります。 菅原道真の第11子で長南氏の祖とも言われる菅原善智麿(滋殖)を祖とする長南氏が「紅花」を栽培したりして、約500年近く当地を支配していました。 2.長南氏と紅花 紅花の染料は「くれない」で、これは呉(クレ 当時の中国の名称)と藍(アイ)が詰まって「クレナイ」と発音されるようになったと言われています。 紅花栽培は長南氏にとって重要な産業であったのではないかと思われますが、いつの間にかなくなってしまいました。 3.平良文(千葉系)庁南氏 平良文は、両総平氏の祖とも言われています。その子孫の上総広常について活躍した庁南氏がありました。「庁南氏」を名乗っていた武士たちも長南に住んでいることから長南を名乗っていたのではないかと思われます。 4.長福寿寺と長南氏 今長福寿寺、正式には「三途河頭極楽東門蓮華台上阿弥陀坊大平埜山本実成院長福寿寺」という日本一長い寺号を持っている天台宗の寺院です。 また長福寿寺には、天台宗中興の祖と言われる「木造慈恵大師坐像」(県指定文化財)があります。大檀那は長南城主・長南次郎常秀であることが記されています。 5.長南氏と笠森観音 笠森寺縁起によると、(四方懸造りの本堂)を建立した時の「与力の旦那」として長南小次郎と刑部三郎の名がみられます。この建物が桃山時代に建てられたことがわかりました。 |
6.長南次郎光重と日蓮 念仏無間 念仏など唱えていると無間地獄におちる 禅天魔 禅宗は悪魔の教えである 真言亡国 真言宗を信じていると国を亡ぼしてしまう 律国賊 律宗は国を盗む泥棒のような宗教だ このようなことを鎌倉の辻に出て人々に話しかけたので、中には石を投げる者もいれば、日蓮を殺してしまおうという武士もありました。日蓮は市川の富木胤継の許に逃れました。 この事件の後、日蓮は長南の岩附谷の長南次郎光重のもとに来て保護されていました。日蓮の説くことを聞き光重は日蓮の考え方に感動し家族一同で日蓮の熱心な信者になりました。日蓮は光重に「長立山光重寺」という寺号を与えました。 また日蓮自筆の「南無妙法蓮華緯」と書いたお題目が与えられて、これは現在長南町本詮寺に保存されています。 いつの時代でも、弾圧を受け追われている者をかくまうということは大変なことでありました。日蓮はその後笠森観音堂に移りましたが、彼を訪れる人はほとんどなく長南光重の家臣、墨田某が光重の命を受けて供養に来る程度でした。現在観音堂にこの様子を描いた絵馬が奉納されています。 7.おわりに 少し順序が逆になりますが、源義経に従って平家追討戦に加わっていた長南忠春という人物は、建久元年(1190)頃に田老(現在の岩手県宮古市)で病死したと伝えられています。 長南氏のこの広がりかたは、千葉氏のそれとも良く似ていて、千葉氏もその一族と称される人びとが肝心の千葉には少なく、東北や九州に広がっています。しかし、千葉氏については中村氏の「長南氏の研究」のような研究はありません。 |
| 摩訶般若波羅密多心経 観自在ボサツは深く ハンニャハラミタを行じたまいし時 五ウンは 皆 空なりと 照見したまいて、一切の苦厄を 度したまえり。 シャリシよ、色は空に異ならず。空は色に異ならず。 色はすなわち これ空 空はすなわちこれ色。 受 想 行 識もまたまた かくのごとし シャリシよ、この諸法は空相にして 生せず 滅せず。 垢つかず、浄からず、増さず、減らず。 このゆえに、空の中には、色もなく 受 想 行 識もなく 眼も、耳も、鼻も、舌も、身も、心もなく 色も、声も、香も、味も、触も、法もなく 限界も無く、ないし意識界も無し。 無明も 無く、また無明の尽きることも無し。 ないし老も死も無く、また老と死の尽きることも無し。 苦も、集も、滅も、道も無し 智も無く、また得も無し。 得る所無きをもってのゆえに。 ボダイサッタはハンニャハラミッタに依るが故に 心にケイゲ無し、ケイゲ無きがゆえに 恐怖あること無く 一切のテンドウ夢想を遠離して、ネハンをクキョウす 三世諸仏も、ハンニャハラミタに依るがゆえに、 アノクタラ、サンミャク、サンボダイを得たまえり 故に知るべし、ハンニャハラミタは これ大神呪なり、これ大明呪なり、これ無上呪なり これ無等々呪なり よく一切の苦を除き、真実にして虚しからず。 故にハンニャハラミタの呪を説く。 すなわち呪を説いていわく。 ギャーティ ギャーティ ハーラー ギャーティ ハラソーギャーティ ボジー ソワカ ハンニャ心経 |
般若心経 (摩訶般若波羅蜜多心経) 観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄舎利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識 亦復如是 舎利子 是諸法空想 不生不滅 不垢不浄 不増不減 是故空中 無色無受想行識 無限耳鼻舌身意 無色声香味触法 無限界乃至無意識界 無無明 亦無無明 尽乃至無老死 亦無老死尽 無苦集滅道 無知亦無得 以無所得故 菩提薩垂 依般若波羅蜜多 故心無圭礙 無圭礙故 無有恐怖 遠離一切転倒夢想 究境涅槃 三世諸仏 依般若波羅蜜多故 得阿耨多羅三藐三菩提 故知般若波羅蜜多 是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪 能除一切苦 真実不虚 故説般若波羅蜜多呪 即説呪曰 羯帝羯帝 波羅羯帝 波羅僧羯帝 菩提僧莎訶 般若心経 |
|
| 口語訳 | ||
| 観音菩薩が、深遠な知恵を完成するための実践をされている時、 人間の心身を構成している五つの要素がいずれも本質的なものではないと見極めて、 すべての苦しみを取り除かれたのである。 そして舎利子に向かい、次のように述べた。 舎利子よ、形あるものは実体がないことと同じことであり、 実体がないからこそ一時的な形あるものとして存在するものである。 したがって、形あるものはそのままで実体なきものであり、 実体がないことがそのまま形あるものとなっているのだ。 残りの、心の四つの働きの場合も、まったく同じことなのである。 舎利子よ、この世の中のあらゆる存在や現象には、実体がない、 という性質があるから、もともと、生じたということもなく、滅したということもなく、 よごれたものでもなく、浄らかなものでもなく、 増えることもなく、減ることもないのである。 したがって、実体がないということの中には、形あるものはなく、 感覚も念想も意志も知識もないし、眼・耳・鼻・舌・身体・心といった感覚器官もないし、 形・音・香・味・触覚・心の対象、といったそれぞれの器官に対する対象もないし、 それらを受けとめる、眼識から意識までのあらゆる分野もないのである。 さらに、悟りに対する無知もないし、無知がなくなることもない、 ということからはじまって、ついには老と死もなく 老と死がなくなることもないことになる。 苦しみも、その原因も、それをなくすことも、そしてその方法もない。 |
知ることもなければ、得ることもない。 かくて、得ることもないのだから、悟りを求めている者は、知恵の完成に住する。 かくて心には何のさまたげもなく、むけいげこむうくふさまたげがないから恐れがなく、 おんりいっさいてんどうむそうあらゆる誤った考え方から遠く離れているので、くきょうねはん永遠にしずかな境地に安住しているのである。 過去・現在・未来にわたる正しく目覚めたものたちは知恵を完成することによっているので、この上なき悟りを得るのである。 したがって次のように知るがよい。 知恵の完成こそが偉大な真言であり、悟りのための真言であり、この上なき真言であり、比較するものがない真言なのである。 これこそが、あらゆる苦しみを除き、真実そのものであって虚妄ではないのである、と。 そこで最後に、知恵の完成の真言を述べよう。すなわち次のような真言である。 往き往きて、彼岸に往き、完全に彼岸に到達した者こそ、悟りそのものである。めでたし。 知恵の完成についてのもっとも肝要なものを説ける経典。 |
| 送料込み(円) | 概要 | ||
| 書 籍 | 長南氏の研究 | 一般20,000 | 中村就一著 A6 1899頁 |
| 会員10,000 | |||
| 土師菅原史記 | 2,500 | 長南良一著 古代から道真までの研究 B5 631頁 | |
| 天神様の美術 | 3,000 | NHK制作 道真1000年記念関係の文献、絵画を収集 A4 340頁 | |
| 長南年恵の生涯 | 800 | 雑誌微笑別冊 A4 208頁(売り切れました) | |
| 錦 絵 | ひよどり越え | 2,000 | 71×36センチ 江戸末期版画カラー原寸大 |
| 一の谷 | 2,000 | ||
| 壇ノ浦 | 2,000 | ||
| 蝦夷地渡海 | 2,000 | ||
| 4枚セット | 5,500 | ||
| 先祖書巻物 | 1本 | 100,000 | 予約金、送料込み |
| 2本(1本あたり) | 73,000 | ||
| 4本(1本あたり) | 57,500 | ||
| 6本(1本あたり) | 51,400 | ||
| ※会員とは既に毎年会費を納入している方、今回購入の機会に入会する方の年会費は初年度8,000円、以後は金額自由。 会員には「全国長南会通信」が配布されるほか、「長南氏のルーツを語る会」等各種行事に参加できます。 |
|||