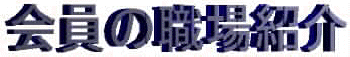 VOL..12
VOL..12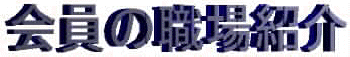 VOL..12
VOL..12
加藤 さおりさん
戸田市立健康福祉の社
特別養護老人ホーム 戸田ほほえみの郷
生活指導員
エントランスホールは、広々とした吹き抜けです。水色のユニフォームで現れた加藤さんは、新しい施設を象徴するような若々しさでした。
「いよいよ、介護保険がはじまりますね。」と話を向けると、「そうなんです、またいちからやり直しです。」と加藤さん。
「いちから」やってきた3年間を振り返ってもらいました。

はつらつとしてさわやか。若さがあふれていました。
プロフィール
平成9年3月、大学卒業と同時に社会福祉士資格を取得。
同4月、社会福祉法人戸田市社会福祉事業団に就職。7月に施設がオープンすると同時に現在の職に就く。
「戸田市立健康福祉の社」とは…
設置主体を戸田市、運営主体を社会福祉法人戸田市社会福祉事業団とし、平成9年7月1日にオープンした。
特別養護老人ホーム(戸田ほほえみの郷)は定員100名、この他にショートステイ定員20名、老人デイサービスセンター(ふれあいランド戸田)定員30名、老人介護支援センター(中央老人介護支援センター)を併設している。
○新しい施設を立ち上げてきたわけですね。
「希望に燃え、もちろんやりがいも感じていましたが、反面戸惑うことも多く、身近に経験のある先輩がいたらどんなに助かるか、と思い続けてきました。というのも、生活指導員は今ではふたりになりましたが、最近までは私ひとりだったからです。
制度的な手続きは、わからないことがあっても簡単に調べられます。
しかし、入所者間のトラブルの場面に遭遇したときなどは、そうはいきません。
結局体当たりで経験して覚えていくしかないのですが、『そのやり方、間違っていない?』と問い掛けてくれる人がいないことの心細さを感じると同時に、一人で突っ走ってしまうことの怖さも忘れないように肝に銘じてきました。
この職に就くにあたっての意気込みとしては、「施設だから」と構えないでいろんなことにチャレンジしたいと考えていました。
そもそも、「生活の場」と言うからには本人のやりたいことができる場でなくてはいけないと思います。出前をとったり買い物に出かけたり、という機会を少しずつ増やしているところです。
どれも最近はじめたばかりでまだまだ充実しているとはいえませんが、元来企画好きなので、いろんな計画を立ててひとつずつ実行に移していきたいと考えています。
昼と夜の食事は2つのコースから選択できるようになっていますが、それでも本人が本当に食べたい食事が提供できているとは限りません。
施設の食事は、どうしてもカロリーの高いものを控えたり、生ものを避けたりしてしまいます。仕方ないな、と思う反面、『生活の場ならいいんじゃないの?』という感性も失ってはいけないと思っています。
○どんなことに悩みましたか?
「平成10年度の社会福祉士現任研修会に参加し、事例検討会で取り上げてもらったケースがあります。私は新人の立場でしたが、経験のある方の意見を聞きたいと考え、あえて3年以上の経験者の枠に入れてもらいました。
Aさんは車椅子生活で、方麻痺があるものの自分で車椅子をこぐことができます。しかし依存的な性格から、「腕が痛い」「腰が痛い」と理由をつけ、職員に車椅子を押してもらおうとしていました。
私は、依存的な性格の相手であっても、聞く姿勢を持つ努力はするべきだと考えていました。それに誰にでも調子のいいときもあれば悪いときもあるものですから、「ここまで来てくれればあとは手伝いましょう」というようにAさんの様子を見ながら場合によっては手伝う、という対応をしていました。
ところが介護職員の間では、ADLの低下を恐れる声が強く、あくまでも自力でさせる、という対応を取っていたことから、次第にAさんの依存の矛先が私だけに向くようになってきたのです。Aさんと介護職員の間に溝ができてしまいました。
事例発表をしたところ、経験のある方から、「依存から自立にいたる過程は子供が成長するときと同じように依存を受け止める段階が必要なのだと思う。その上で、自立につなげるように働きかけていくのがいいのではないか。」という意見をいただき、答えを得られたように思いました。
この頃、職場では職種を越えた連携が上手に取れずにいました。私も自分の意見を他の職員にうまく伝えることができませんでした。
採用の際、看護婦はもちろんですが、生活指導員には社会福祉士の資格が、寮母職には介護福祉士の資格が条件でした。新しい施設だからでしょう。ここまで徹底している施設はまだ少ないと思います。
しかし、その当時はそれぞれが自分たちだけで抱え込むような仕事の仕方をしていたように思います。それぞれの専門職としての視点を持っていることは重要ですが、力を合わせなければいい処遇はできません。
この研修会は、他の職種との連携に向けて、いいきっかけになりました。
まず、研修会の結果を介護主任に報告しました。そして、介護主任を通じて他の職員にも徐々に意見を伝えていくことができました。
さらに職員の間で認識や対応にずれがあったことが反省点として浮かび上がってきました。職種を越えて意見交換をし、処遇についての話し合いをしていくことの重要性をようやく認識できたのです。
今では定例で話し合いを持ち、個別処遇については必ず全ての職種が目を通す、という形が出来上がりました。」
○いよいよ介護護保険が始まりますね。
「現在は、入所している人たちの自己負担額は収入によって決められていますが、介護保険が始まると介護のレベルによって決められるように変わります。
収入がまったくなければ生活保護による対応があるのですが、わずかでも収入があるために生活保護からもれてしまう人は厳しい状況になります。
こうした場合の対応に何か策はないものかと役所に相談するのですが、役所の方でもそうした細かいところまではまだ行き届いていないのが現状です。
何がどう変わるのか、あいまいな部分が多いのが不安なところです。」
![]()
間違いに気付かないでいるとき、それを指摘してくれる人。失敗したとき、『まあ、仕方ないね。』と忘れさせてくれる人。うまくいったとき、ほめてくれる人。そんな先輩が近くにいてくれたら…。
今でも切実にそう願う加藤さんですが、私の目にはもうベテランの風格が漂いはじめているように映りました。
(取材 広報委員 野川kiyoko-n@ta2.so-net.ne.jp)