タイトル、演奏者
ひとこと
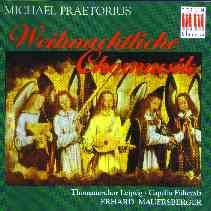
Weihnachtliche Chormusik
Thomanerchor Leipzig, Capella Fidicinia
Erhard Mauersberger
(Berlin Classics 0091282BC)
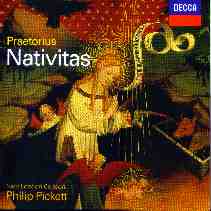
Pickett / New London Consort
(Decca 458 025-2)
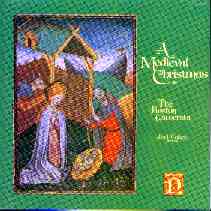
The Boston Camerata
Joel Cohen
(Nonsuch 9 71315-2)
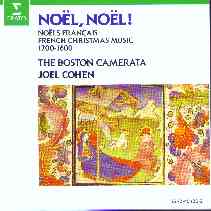
Noels Francais 1200-1600
The Boston Camerata
Joel Cohen
(Erato 2292-45420-2)
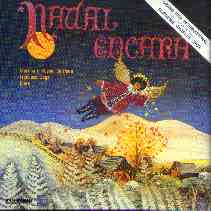
Noels Occitans d'Hier... Aujourd'hui)
Martina e Rosina de Peira
(Revolum)
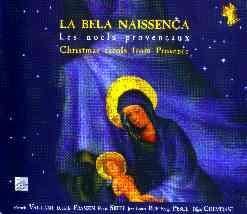
Les noels provencaux
(L'empreinte digitale ED13113)
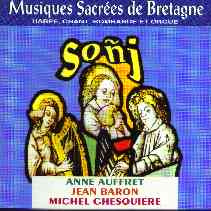
Musiques Sacrees de Bretagne
Anne Auffret, Jean Baron, Michel Ghesquiere
(Keltia Musique KMCD17)
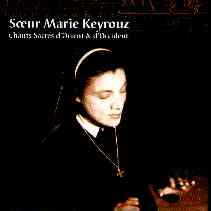
Soeur Marie Keyrouz
(Virgin 7243 5 45379 2 9)
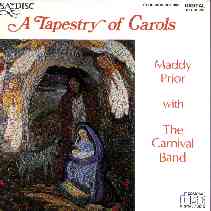
Maddy Prior + Carnival Band
(Saydisc CD-SDL 366)
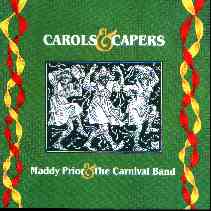
Maddy Prior + Carnival Band
(Park Records PRK CD9)
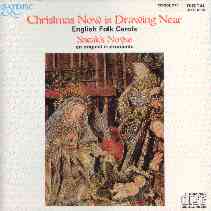
Sneak's Noyse
(Saydisc CD-SDL 371)
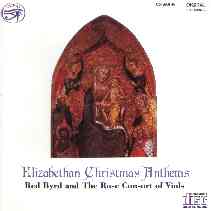
Red Byrd and The Rose Consort of Viols
(Amon Ra CD-SAR 46)
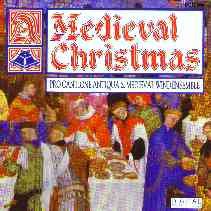
Pro Cantione Antiqua
(IMP PCD844)
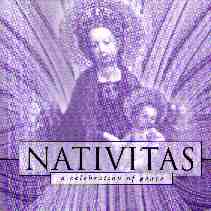
The Choir of New College, Oxford
(Erato 0630-19350-2)
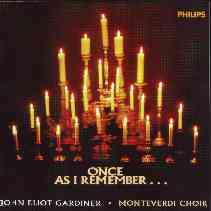
Gardiner / Monteverdi Choir
(Philips462 050-2)
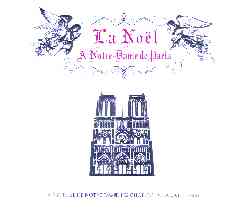
(女子パウロ会 FPD036)
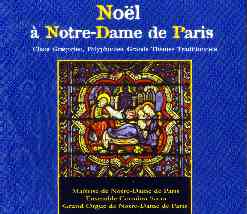
(BMG France 74321 443642)
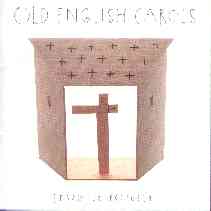
アンサンブル・エクレジア
(女子パウロ会 FPD015)
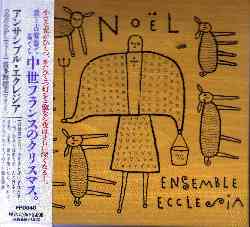
アンサンブル・エクレジア
(女子パウロ会 FPD040)
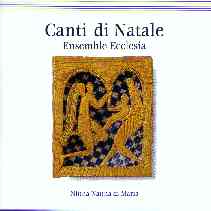
アンサンブル・エクレジア
(女子パウロ会 DCI 17037)
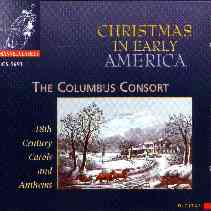
The Columbus Consort
(Channel Classics CCS5693)
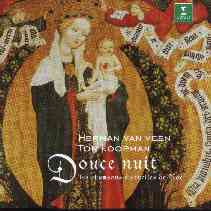
Les chansons eternelles de Noel
H. van Veen & Ton Koopman
(Erato 0630-14771-2)
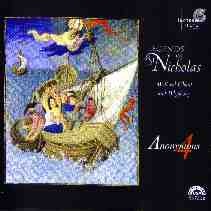
Anonymous 4
(Harmonia Mundi USA 907232)
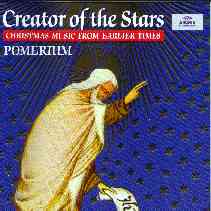
Pomerium
(Archiv 449 819-2)
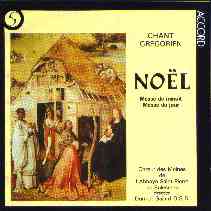
Abbaye St-Pierre de Solesmes
(Accord 221612)