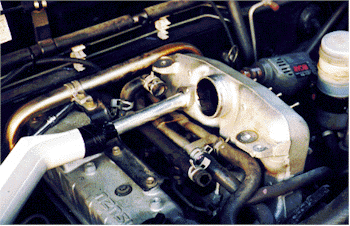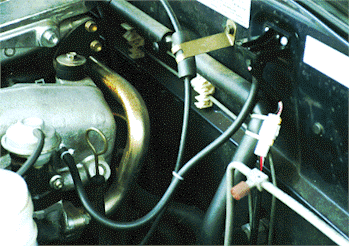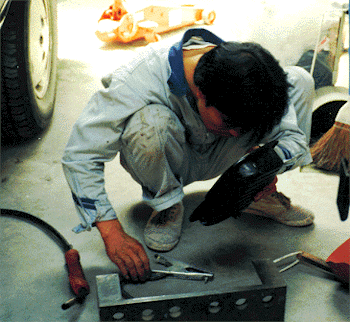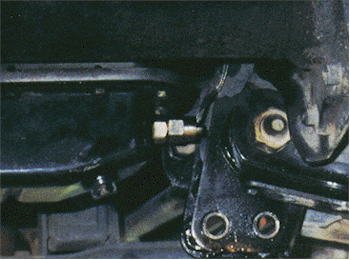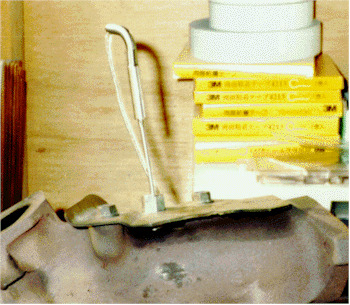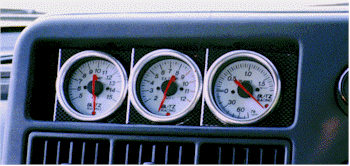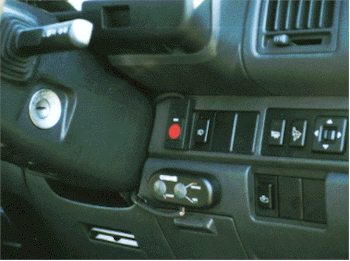| メーター 早いもので、もう98年となってしまった。69の方も追加メーター、マフラー、キノコ、燃調と色々やって何とか使える車になってきた。ところで昨年末、ホックル氏からバリ山のスワンパーを何とタダで貰った。何でも80に着かなかったらしく、さすがに社長太っ腹だ! 69の方は通勤快速&スキーの予定であったが、やはりこいつを入手した以上、本来の使い方をしなければならない。早速、バネとショックを購入し通勤快速からクロカンもできるRVへ変身だ!(あくまでもRVです。クロカン専用ではありません。69の良さはスキーやキャンプ、クロカンから冠婚葬祭までマルチで使える四駆です) さて、研究の方も電気モノをちょこまかとやって来たが、そろそろ本題の方に入りたいと思う。今回は車をいじる上で重要な追加メーターの取り付けの模様についてレポートする。 ● BOOST計は必須 車をいじる場合エンジン・コンディションの把握や壊さないようにいじる為に、追加のメーターが必要になってくる。特にターボ車の場合BOOST計は必須アイテムだ。69の場合、標準で装備されているメータは、燃料、水温、油圧、電圧といったところ。油圧の方は油圧計とオイル切れのワーニングランプが独立し二重になっている。 さて、今回追加するメータの目的だが、いじった場合にノーマルとどの程度違いが出てくるのかを確認したい。従って、BOOST計は当然として、油温、排気温計は欲しい。問題は油圧計だが、ノーマルの油圧計が使いモノになるかどうか・・・。サービスマニュアルのデータと現物を比較してみると、精度はマアマアだしレスポンスも55の時に比べカナリ良くなっている。取り付ける場所の問題もあるし、こいつを信じる事にしよう。 ● メーターの選定 さて、メーターを取り付ける位置だがこれは当初の予定通り一番見易いコンソールの上段、ノーマルのカーステの収まる位置に取り付ける事にする。従って、カーステは時計の位置に移動、そのために時計表示付きのディスプレイがティルト・アップするカーステを選んだワケ。 カーステの位置にメーターを収めるとなると、メーターの大きさはDINサイズ50mm前後。メーターは機械式と電気式があるが、ちゃんとした物であれば精度的にはどちらも変わらないだろう。室内への配管や取り回しを考えると、配管が最小(エンジンルーム内で完結する)の電気式の方が良いだろう。但し、価格は機械式の倍くらいする。 そこで、選んだのは最近発売になったブリッツの電気式52φのメーター。透過照明付きで、予め設定しておいた値を超えるとワーニングランプが点灯する。オプションでピークホールド・メモリが付けられるので、走った後に最大値をチェックできるのでなかなかGood!だ。 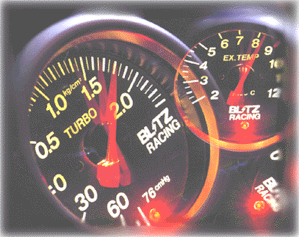 ● メーターパネル メーターを取り付けるパネルは当初自作を予定していたが、ちょっと手抜きをして大森のDINサイズ52φ三連のオフセットしたパネルを利用する事にした。ビッグホーン用に改造(といってもヤスリで削るだけだが)するため、現物合わせでギコギコと削る。面取りして、仕上げはカンタンなカッティングシートを張る事にする。ソフトな感じを出したければクロスや合皮を張っても良いだろう。今回は、奮発してカーボン調のコーティングシートを張った。 ● BOOSTセンサの取り付け BOOSTの取り出しはインマニのサージタンクから取りたい。タービンやインタークーラーの前からでは、吸気温の低下や圧損があったりして正確な数値が出ないと思う。通常、ガソリン・ターボや電子制御ディーゼルの場合、サージタンク近辺にBOOSTセンサーが付いているのでそこに三つ又を付けて割り込ませれば良いが、ボクの69はメカ・ポンプなので何も付いていない。55の時はちょっとインチキをしてインタークーラーの出口から取り出したが、今回はちゃんとサージタンクから取り出す事にする。 サージタンクに穴を開ける場合、本来はインマニを外して作業するのが正しいと思うが、燃料系の配管がインマニに入り組んでいて外すのはちょっと厄介だ。インタークーラーとERGバルブを外し、よく観察するとリリーフバルブの反対側がちょうど良さそうだ。掃除機作戦を決行する。 掃除機のホースに適当なパイプを付け、先端が密着するように縁ゴムを付ける。インマニをウエスで塞ぎ3mm位のドリルを用意し注意深く穴を開ける。 反対側から確認しながらゆっくり開けて行くと先端が盛り上がってくる。素早くドリルを抜き、用意したパイプを力強く密着させながら掃除機のスイッチを全開! 「プオォ〜!」 掃除機が唸りを上げる。 素早くドリルで穴を開け、そのままタップを立てる。 「プオォ〜!」 切削油を付けながら慎重にタップを切る。切削油は切り粉が付いてしまうため最低限にする。 「プオォ〜!」 何回かタップを左右に回し切り粉をよく落とす。 ・・・そっと掃除機を外す。 相手は鋳物のアルミなので粘りも無いため切り粉も皆無だ。もし、切り粉がウエスに落ちてしまった場合には、そっと掃除機で吸い取ればOK! 要はインマニの中に切り粉が落ちずにタップが切れればい〜のだ! オイルクーラーとセットで付ける時によく行われている。加工はほとんど無く、簡単に取り付けられる。但し、車種によってはオイルフィルターのスペースが狭くなるので、55の様な車種は不向きかも? ターボ車はブロックの所にノーマルでオイルクーラーが付いていたりするので正確な油温が出るか、ボクが疑問に思っている。 これも自分の車に合った(ネジ径とピッチが)T型バルブがあれば簡単な作業だ。メジャーな車種は○○用とかいって売られている。センサーの取り付け用にステンメッシュのデリバリー・ホースもある。 これには2通りあって、ドレンボルトの穴にアダプターを介し取り付ける方法と、オイルパンに穴を開けてタップを切りセンサーを取り付ける方法がある。ドレンボルトに取り付ける方は自分の車に合ったアダプターがあれば最も簡単だが、オイル交換の時はちょっと面倒だ。オフロード車は引っかけたりする可能性があるので、あまりお勧めではない。オイルパンに穴を開ける方法は取り付けがちょっと厄介だ。センサーが付けられる平らな場所が無いとオイルが漏ってしまうし、穴を開けるのもオイルパン自体は薄いのでタップが切れないため、特殊工具(?)で打ち抜きで穴を開けそこにタップを切ったりする。(オイルパンを外さないで作業するケースもある。切り粉はどうするのだろう・・・)
街乗りの排気音が低いのはエキマニからセンサーが離れているため(もっとも、マニホールドにセンサーを打つ限り、正確な値は出ないと思うが・・・)、あまりアテにならないのでこれからの相対値として利用する。因みに、これを計ったのは夏。高速全開は145km/h程度。 ここでちょっと気になったのは油温で、街乗り、特に都心の「信号が青になって加速し、少し走って信号待ち」といった走りでは、信号待ちで油温が見る見るうちに上昇する。エアコン併用で「ちょっと回して信号待ち」では100℃を越える事もあった。ま、ある程度想像はしていたが、まさかこんなに上がるとは思わなかった。案外、街乗りの方が車にとっては厳しいかも。 [TOP] |
||||||||||||