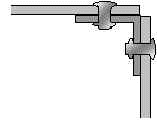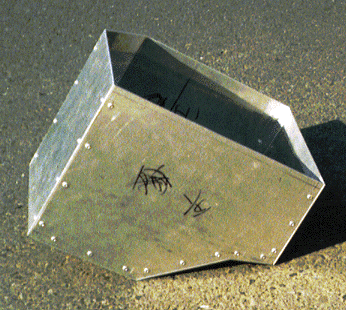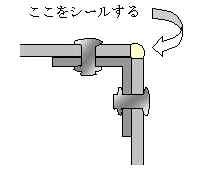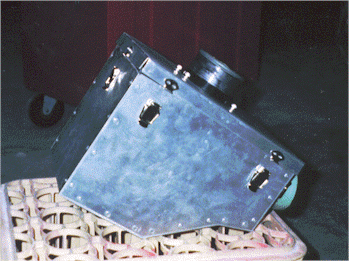インダクションボックス前編
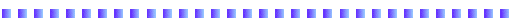
マフラーが完成し、そこそこ通勤快速らしくなった69。今月は、ポンプ調整に入る前に吸気系の改造。キノコの取り付けだ。
●方針検討
エアクリーナーの交換と言えば、一番簡単なのがノーマルと交換するタイプ。ファイナルフィルター等だが、今回は、より吸気効率を上げるため是非ともキノコを付けたい。キノコを付ける場合、注意する点が幾つかあるが一番の問題は熱害対策だと思う。せっかく、効率の良いエアクリーナーに交換しても、エンジンルームの熱をそのまま吸い込んだのでは、かえってパワーダウンになってしまう。
試しに実測してみると、この時期で外気温が22℃の時に、通常走行で50℃、停車時で60℃、加速 − 停車が多い夏場の都心などでは、70〜80℃位まで上がると思われる。
対策としては、乗用車の場合インダクションボックス(遮熱版)を設けたり吸気ダクトを引いたりしているが、四駆の場合オフロードで泥水を被ったりするのでそれだと上手くない。オフロード用にカバーも売られているようだが、所詮はオフロードを知らない人が作った物。隊長ほどじゃないにせよ、泥水がかかる事はまず間違いない。「外気導入」という目的では、エントツを付けるのが手っ取り早いが、それだとキノコが付かないしサンタクロースを待つ歳でもないのでボツ。 ・・・という事で完全密閉型のインダクションボックスを作る事にする。
●仕様検討
インダクションボックスを作る場合、材質としてはFRPやアルミ板などが考えられる。ノーマルのエアクリーナーに比、べキノコは一回り大きいため、あまりスペースに余裕がない。FRPの場合、型を上手く作ればフェンダー内にピッタリと収まる物ができるが、何しろ1個しか作らないので型が無駄となってしまう。また、強度を出そうとすると、意外と重い物になってしまうのでイマイチかな。アルミ板の場合、強度や単純な加工は問題無いが曲面などの加工は難しい。また、接合面の強度や防水対策をしっかり行わないと水漏れの原因になる。アレコレ色々悩んだあげく今回はアルミ板で作成する事にする。
さて、次に検討しなければならないのが空気の取り入れ口。エンジンルーム内だと意味がないし、乗用車のように前面から引くと水が心配だ。走行中に負圧にならなく、かつ、外気がスムーズに入る所・・・。インナーフェンダーかバルクヘッド。
インナーフェンダーは、ちょっと狭いが工作は可能。外から見えないため、多少工作がマズくてもOK! 50φ程度の配管は通せそうだ。バルクヘッドの方は、もともと外気を取り入れるための物で、走行時には風圧が掛かるようになっていてゴミ避けの網も付けられている。詳しく調べるため、ワイパーやモール、カバーを外し内部を観察する。内部は、かなり大きな空間が有って水抜き対策もされている。
両脇の上部は、インナーフェンダーと繋がっていて流量が不足する事もない。吸気位置もインナーフェンダーよりも高く出来るため、水没時にも有利。配管の方も、燃料フィルターを移動すれば100φまでは行けそうだ。吸気音や共振等の問題が懸念されるが、これはやってみないと分からないので、バルクヘッドから取る事にする。
 フェンダーを取るとこんな感じ フェンダーを取るとこんな感じ
●設計
設計と言ってもスペースが限られているため、自ずと形は決まってくる。一応、不具合があった場合の対策として、インナーフェンダーからの配管のスペースを残し、レゾネーター等の不要(?)な物を全て取っ払い出来るだけ箱を大きく作る。段ボールで幾つか試作したのがこれ。
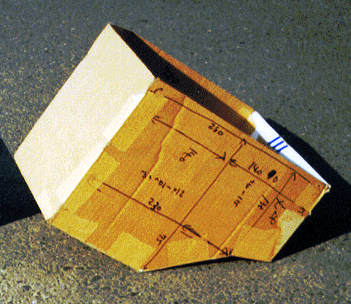
タービンまでの配管は、エンジンが動くためノーマルの物をそのまま利用する。(今回使ったキノコはラックから発売されているK&Nの物で、ちょうどノーマルの配管に付けるようになっている)
バルクヘッドからインダクションボックスまでの配管は燃料フィルターを移動し、80φのアルミパイプで繋ぐ。アルミ板の接合は溶接できれば完璧なのだが、道具もないしやった事もないのでアングルを利用しリベット止めとした。隙間はシリコンシーラーでシーリングする事にしよう。
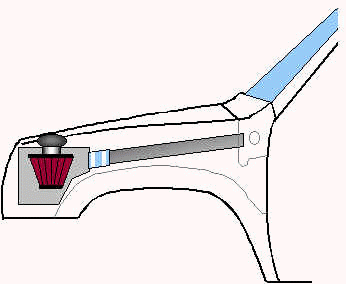 図にするとこんな感じ 図にするとこんな感じ
●部品の入手
アルミ板やリベット、シリコンシーラーなど殆どの物はドイトで入手可能。パイプはアルミでなくても良いが、熱や振動などに耐えられる物が良い。空調用アルミダクト(蛇腹のヤツ)でも良いが、空気の流速が相当早くなるため、騒音や空気抵抗を考えるとフラットなパイプが良いだろう。80φのt=3のアルミパイプがHKSで発売されていたので、ジョイント込みで購入した。
●製作
工作自体は特に難しい作業はないが、正確に作らないと水漏れなどの原因になる。幅のあるアルミ板を曲げるには万力があると楽だ。
まず最初に段ボールで試作した型をバラし、寸法を測ってアルミ板に転記していく。今回は万力で曲げるため、あまり複雑な曲げ方は不可能だ。曲げ方を考慮しつつ、できるだけ接合箇所が少なくなるようにする。
記入した線に沿ってアルミ板を曲げる。プレスがあれば何も考えずに簡単に曲がるのだ が、万力でやる場合には曲がり角がキレイになるようにアングル等を噛ませ、角材や当て 板を使って曲げると良い。
アングルとリベットを使ってアルミ板を接合する。隙間が空かないように、ヤスリなどで修正しながら板の角と角が合うようにしてピッタリと止める。特に蓋が被る部分は水漏れなどの原因となるため高さを均一にする事。
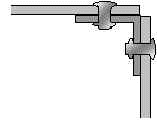
本体が出来たら車に仮合わせをし、各パーツの位置を確認しマーキングをする。具体的には、インダクションボックスを止める位置、エンジン側パイプ及びキノコの位置、燃料フィルターを移動する位置、吸気パイプが通る位置と角度、バルクヘッドに開ける穴の位置などだ。
吸気パイプの仮合わせは、本物を使用せず段ボールや厚紙、ロール紙の芯をなどを使うと良いだろう。今回は、会社のゴミ箱から拾って来たロール紙の芯を適当な長さに切って使った。(この後、また使う予定) インダクションボックスの固定は、ノーマルのエアクリーナーケースのマウントを移植した。
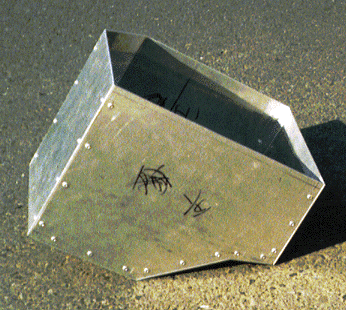
本体に合わせ蓋を作る。本体と蓋との接合部には縁ゴムを噛ますため、その分大きめに作成する。完成したら再度仮合わせを行い蓋にエンジン側パイプの穴の位置をマーキングする。
インダクションボックスから吸気パイプが付く部分を外し、ホールソーで穴を開ける。80φ以上のホールソーとなると円形のコンクリート用の様な形をした物が良いのだが、ドイトなどでは取り寄せとなってしまうため(高価だし)、手持ちであった金属用の方爪タイプの物で開けた。本当は、ボール板でくわえて使うのだが、ゆっくりやればハンドドリルでもOK!
穴が空いたら再度仮合わせを行い、パイプの角度をヤスリで調整する。バルクヘッドの方が位置が高いため、楕円の穴になるハズだ。蓋の方も同様にして穴を開ける。
穴開けが完了したら、吸気パイプを60mm位に切りインダクションボックスに固定する。固定はアングルの切れ端を使用した。このパイプに、ジョイントを介し吸気パイプが接続される。ジョイントが抜けないように、ヤスリ等で溝を付けておくと良いだろう。
インダクションボックスの接合部をシーリングする。シーリング材は何でもOK! 要は隙間が無ければ良いのだ。よく脱脂してマスキングテープを使うとキレイに出来る。脱脂は薬局や金物屋などで売られている、燃料用ベンジンが効果的でお手軽だ。
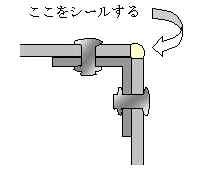
インダクションボックスに縁ゴムを付け接着剤で固定する。角は水が漏らないように切り 込みを入れピッタリ合わせた上、接着剤で固定する。蓋を合わせきちんと閉まる事を確認した後、蓋を固定するための金具(ドイトで購入)を取り付ける。ちょっとキツめが良い。各辺に1個ずつ、計4個使用した。
蓋にキノコのボディを固定する。今回の物はボディが分解できるヤツだったので、ボルトだけ購入し伴締めした。ここも念のため、シーリングする。
以上で基本的な作業は完了。キノコの穴をテープで塞ぎ、吸気口から水を入れ水漏れのチェックを行う。本体の角の蓋との合わせ目や、幾つかのリベットから水が滲み出てくる。「う〜む。水が漏らないようにリベットの下穴は面取りをし、垂直に、しっかり打ったんだけどなぁ・・・」 よく見ると、リベットの芯から滲んでいるようだ。「防水リベットにすれば良かったかなぁ」 蓋の方も金具の数が足りないためだろうか?
水没したまま走る訳ではないので、実用上は問題無いが、一応、水漏れ対策を行う。リベットの方は接着剤を薄く塗りシーリングをする。ネジの袋に付いているタグの丸い穴をマスキングに使うとキレイにできる。蓋の方は、縁ゴムに当たる部分にゴムパッキンを入れる事にする。普通のゴムだと、繋ぎ目で水漏れがしそうなので10mm位の幅で薄くシリコンシーラーを塗布した。マスキングテープやガムテープ等を何枚か重ねヘラを使ってやると均一の厚さにできる。
金具の方も一回り大きな物に変更し止める数を増やす。再度、キノコの穴をテープで塞ぎ吸気口から水を入れ水漏れのチェックを行う。今度はバッチリ! バッチリ!。インダクションボックスの方はこれで完成。
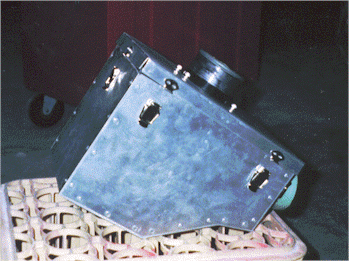
次に車体側の加工に入る。吸気パイプが入るようにバルクヘッドに穴を開ける。穴の縁は縁ゴムでカバーし、吸気パイプの固定は動く所じゃなので差し込むだけにする。蓋と同様にしてホールソーで開けるが、バルクヘッドは平らじゃない上、足場が悪くなかなか上手く行かない。
金ノコとヤスリを駆使し何とか穴を開ける。当初の予定より大きくなってしまったため、縁ゴムを入れてもガタガタだ。ドイトなど色々回って使えそうな物を物色する。で、結局、首都高の下に捨ててあった車から剥ぎ取ったウェザーストリップを利用した。熱や油、紫外線にも強く、ゴムの厚みもあってGood!
Good!
さっき使ったロール紙の芯を使って仮組みし、燃料フィルターの位置や補機記類(EGRのVSVなどがエアクリーナーケースに付いている)の取り回し、配管等を検討する。エンジンが動く事を考慮しよく検討すること。燃料フィルターは、ノーマルの物を加工し移動した。
補機類は、インダクションボックスにナッターを使ってナットを作り、ノーマルと同様にしてボルト止めをした。燃料フィルターを移動したため、燃料パイプが届かなくなってしまった。このままだと動けないので、取り合えず首都高の下へ! 適当なパイプを剥ぎ取って接続。後日、ちゃんとした燃料ホースを購入した。
仮組が完了したら、吸気パイプをロール紙の芯に合わせて切断。角を丸め、最終的な組付けを行う。これまでを文章にすると簡単だが、色々と試行錯誤で作業して来たためインダクションボックスや吸気パイプがキズだらけになってしまった。ピカールで磨く事も考えたが、ここはひとつ、イカサマ「ヘアライン加工」を施す事にする。
加工する部品をバラし平らな台の上に置く。ゴムマットを敷くと作業がし易い。320番のペーパーに大きめのサンディングブロックに巻いて、部品の前から後ろに向かって一気に「引くべし!」 「引くべし!」 「引くべし!」
引くときは真っ直ぐに一気だ。横方向はダメ。線が曲がる。ペーパーの番手によって目地の荒さが変わる。240〜400番がお奨め。本来は、この後、コーティング加工をするのだが、めんどくさいのでパス。さて、完成だ。(結局、FRPで作った方が早かったという噂もある)
●テスト
さて、試走してみる。「シュュュュュュュュュー」。吸気音がうるさい。それもかなり。レゾネーターを取ってしまったためか、アイドリング時に脈動も出る。エアダンパーの効果が無くなってしまったためであろうか? (最近のトヨタ車をみると、タコ壺のようなものが付いているよね)
・・・「う〜む。これは失敗だ!」 対策は、ちょっと厄介そうだ。ゆっくりやる事にしよう。
[TOP]
|
 フェンダーを取るとこんな感じ
フェンダーを取るとこんな感じ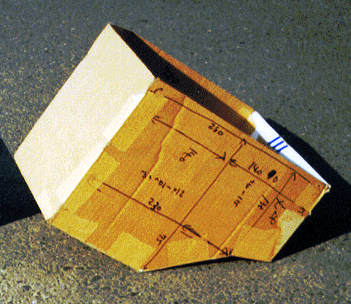
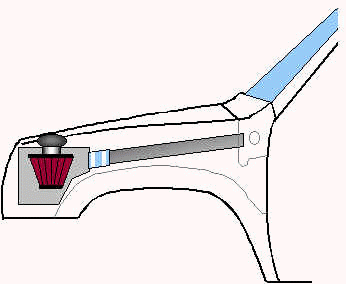 図にするとこんな感じ
図にするとこんな感じ