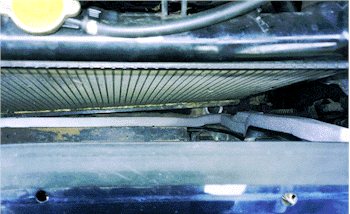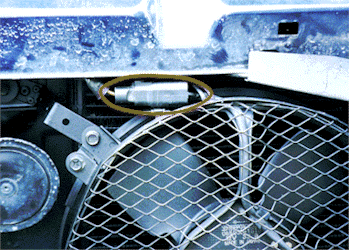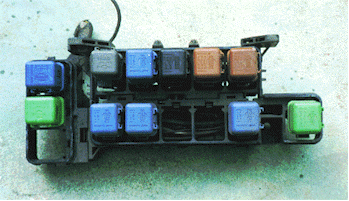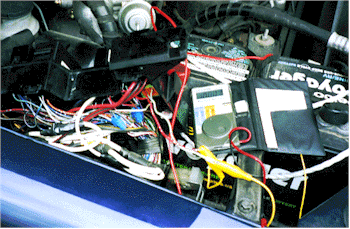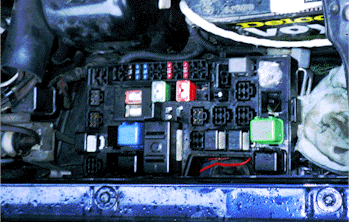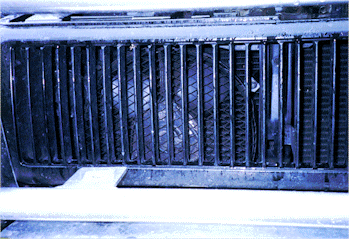電動ファン
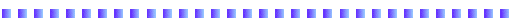
ビッグホーンの冷却系だが、乗っている人はご存じの通りイマイチ性能が良ろしくない。55の時はエンジンオイルの量が少ないせいか、夏になるとエンジンが熱ダレしハンチングを起こすし、エアコンのラジエータには電動ファンが付いていないせいか、夏の炎天下の渋滞では放熱が追いつかなくなり、コンプレッサーの保護回路が働いてコンプレッサーが停止してしまう。69になってからは、さすがに熱ダレは少なくなったが相変わらず電動ファンは付いていないし、キャビンが広くなったせいか冷却能力はイマイチ。そこで、「電動ファン化」という事になるが、ただ単に付けるだけでは脳がない。
ことあるごとに他車のボンネットを開けたり、トヨタのアムラックスに行って片っ端からボンネットを開けたりして(ちょっとひんしゅくだが・・・)地道な調査を行った結果、幾つかのポイントが見えてきた。今回は、長年の地道なる調査と研究の成果を元に、ビッグホーンの電動ファン化を紹介する。
● 基本方針
さて、電動ファンを付ける場合、エンジンのファンも全て取っ払ってしまって電動化する方法と、追加ファンだけを取り付ける方法がある。前者は、エンジンの負荷が減りレスポンスが良くなりファンベルトも長持ちするというメリットがあるが、電動ファンが70W程度消費するためエンジン用とエアコン用を合わせて140W程度の電力を消費する。140Wというとヘッドライトとフォグランプを同時に点灯した位の電力で、バッテリーやオルタネーターの負荷となる。
一方、後者は、お手軽で故障などが起きても走行自体には関係ないが、当然、エンジンのパワー面での改善は望めない・・・。で、実際はどうなんだろう? 炎天下でエンジンのファンを外し試走してみる。
結果は、体感的には全く変わりはない。元々、加速中にエアコンのコンプレッサーが入ってもそんなに負荷にはならない事を考えると、ディーゼルの場合低速トルクがあるしファンにはシリコンクラッチが付いているので、走り出して雰囲気温度が下がったとたんにファンは空回りする・・・。因みに、クラッチは40℃と60℃の2段階で回転数が変化する。55の場合、夏はオーバーヒート気味、冬はオーバークール気味であったが、この点については69はかなり改善されている様なので、水温が安定しているのであれば無理にトラブルの原因になる様な改造をしない方が良い。という事で、エアコン用に追加ファンを付けることにする。
● ポイント
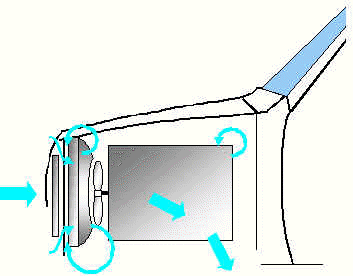 ところで、電動ファンを付ける場合、幾つかのポイントがある。 ところで、電動ファンを付ける場合、幾つかのポイントがある。
イスズ車の場合、ラジエーター周りのマスキングがきちんとされていないため、ラジエーターの排熱がショート・サーキットを起こし、シェラウドを付けているのにチムニー効果が最大限に得られないと思う。他のメーカーでも、同じ様な車は多々見られるが、トヨタ車はこの辺の造りが非常に上手く、きちんと処理されている。(バッテリーも別部屋で保護されている)
 写真にもあるとおり、上側はゴムで塞いでいるがラジエータの横にはかなりの隙間がある。更に、最近のビッグホーンはコストダウンのためだろうか、ボンネットの隙間を塞ぐゴムもなくなっている。(因みに、これがないとエンジンに直接泥を被る) 写真にもあるとおり、上側はゴムで塞いでいるがラジエータの横にはかなりの隙間がある。更に、最近のビッグホーンはコストダウンのためだろうか、ボンネットの隙間を塞ぐゴムもなくなっている。(因みに、これがないとエンジンに直接泥を被る)
従って、これらの隙間を塞いでやると効果的だ。要は、エンジンルーム側の排熱が外側(ラジエーター側)に帰らなければ良いワケだからゴムや隙間テープなどで塞いでやればOK。
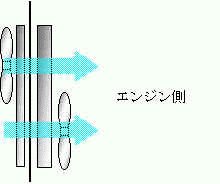 次に、取り付けるファンだが、押し込み用と吸い込み用があるので注意が必要だ。通常、最近の車はエアコンは押し込み。ラジエータは吸い込みになっている。今回は、いつもの様に高速道路の下に捨ててあった平成元年式のコロナから頂いた。 次に、取り付けるファンだが、押し込み用と吸い込み用があるので注意が必要だ。通常、最近の車はエアコンは押し込み。ラジエータは吸い込みになっている。今回は、いつもの様に高速道路の下に捨ててあった平成元年式のコロナから頂いた。
最後に、取り付けるファンの数だが、1個でも2個でも構わない。因みに、トヨタ車は全て1個。図の様な構成になっている。たぶん、2個付けてもコストの割に性能が出ないのと、使わないときはかえって抵抗になってしまうのだろう。今回も、これに倣い1個だけとした。(以前55に付けた時も1個だったが効果はバツグン。エアコンの効きはバッチリだったし、夏の渋滞での熱ダレもなくなった)
そういえば、何故かビッグホーンはエンジンルーム内から直接エンジンのエアを取っている。これだと、夏の市街地では吸気温が上がって、パワーダウンが著しい。インナーフェンダー内から取るなど、もうちょっと考えてもらいたいもんだ。(これはDdになって改善された)
● 取り付け
特に難しい作業はないが、丁寧にやらないとラジエータのフィンを痛めるので慎重に作業をするめる必要がある。
バンパーとグリルを外す。

隙間テープを使って、パネルとラジエータの隙間を埋める。よく見るとあちこち空いているので、全て塞ぐこと。
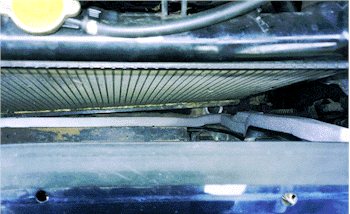
これがコロナの電動ファン。可変ピッチになっていて騒音対策もされている。以前、55に付けた時は、隙間が殆どなかったためモーターはスターレット、フレームはパルサーってな具合でトヨタと日産の合体品でファンを薄くするため羽をカットしたりして少々手間取ったが、69の場合は隙間が多いので、すんなりと付く。

電動ファンはドイトやカーショップで売っている汎用ステーを使って止める。ラジエータとの当たり面は縁ゴムを付けるとGood! 電動ファンを剥ぎ取る時はコネクターも一緒に取ってくる事。メーカー製のコネクターは防水になっていて性能が良い。ギボシ端子などは接触不良になるのでNG!
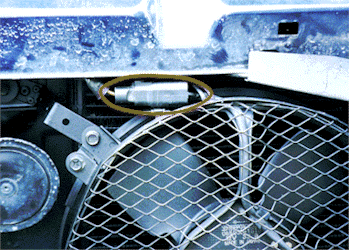
さて、電気系の配線であるが、当初の予定ではオーバーヒート対策も兼ねて、水温センサーを打って、設定値以上の水温になると電動ファンが回るようにするハズだった。が、お金が掛かるしめんどくさいので今回はパス。手持ちの部品と拾ってきた部品でやる事にした。
と言うことで、早速、またまたリレーを拾いに行った。拾ってきたリレーユニットはこれ。日産のホーミーのもの。69のリレーとそっくりだ。
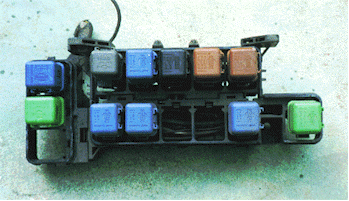
何故かイズズと日産は共用パーツが多い。電動ファンの制御は、エアコンのコンプレッサーのクラッチと連動させる事にする。水温と連動させる手もあるが、夏はエアコンをかけているワケだから、エアコンのコンプレッサーが入った時点でファンが回れば良い。55の時ももそうした。
リレーを外し、ヒューズボックスの裏からエアコンのコンプレッサーのクラッチへ行く電源を探し、エレクトロタップで分岐させる。水の掛からない所はエレクトロタップでもOK!
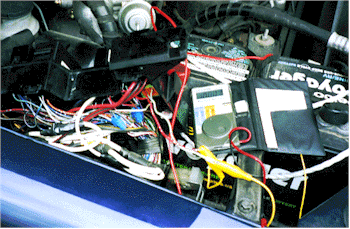
配線が済んだらヒューズボックスの空いているところへリレーを差し込む。なかなか純正風でしょ。
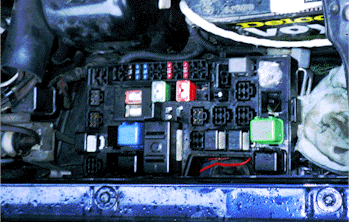
後はグリルとバンパーを元に戻しておしまい。動作確認をする。これで、夏の渋滞時でもエアコンは利くし、信号ダッシュが多い都心の道路も別ダレが無くなって、なかなかGood!
お金が掛からないっていうのも良いね!
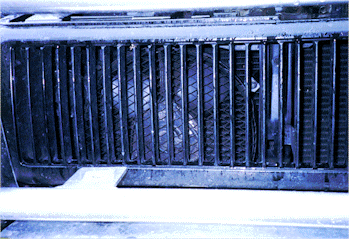
[TOP]
|
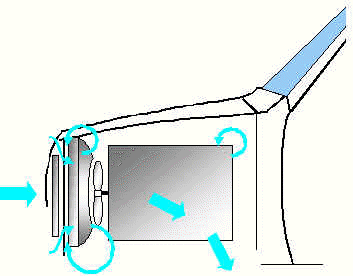 ところで、電動ファンを付ける場合、幾つかのポイントがある。
ところで、電動ファンを付ける場合、幾つかのポイントがある。 写真にもあるとおり、上側はゴムで塞いでいるがラジエータの横にはかなりの隙間がある。更に、最近のビッグホーンはコストダウンのためだろうか、ボンネットの隙間を塞ぐゴムもなくなっている。(因みに、これがないとエンジンに直接泥を被る)
写真にもあるとおり、上側はゴムで塞いでいるがラジエータの横にはかなりの隙間がある。更に、最近のビッグホーンはコストダウンのためだろうか、ボンネットの隙間を塞ぐゴムもなくなっている。(因みに、これがないとエンジンに直接泥を被る)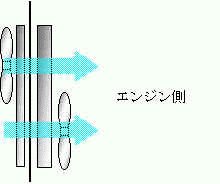 次に、取り付けるファンだが、押し込み用と吸い込み用があるので注意が必要だ。通常、最近の車はエアコンは押し込み。ラジエータは吸い込みになっている。今回は、いつもの様に高速道路の下に捨ててあった平成元年式のコロナから頂いた。
次に、取り付けるファンだが、押し込み用と吸い込み用があるので注意が必要だ。通常、最近の車はエアコンは押し込み。ラジエータは吸い込みになっている。今回は、いつもの様に高速道路の下に捨ててあった平成元年式のコロナから頂いた。