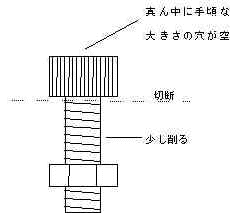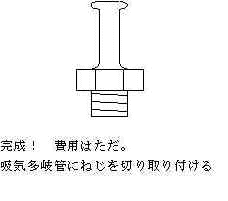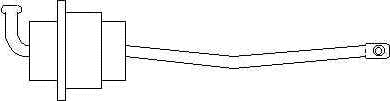| 加給圧上昇大作戦 Webって毛筆ってできないのよね。このレポートを会報に書いたときは縦書き・毛筆の巻物だったのですが、仕方がないのでテキストをそのまま転載します。ま、細かいことは気にせず読んでちょ。 八月ももうすぐ終わりだと言うのに、いや〜 暑いですね〜! こう暑いと野外作業(私の車庫は高さ無制限!)は辛いです。さて、先月までは工作ものばかりでした。う〜む! これではいかん! という事で、今月は過給器付き内燃機改良の定番、「過給圧上昇大作戦」をやります。 ところで、みなさん過給圧上昇の効果については十分理解されていますか? まぁ、ここで改めて説明するまでもまく、雑誌等にはよく出ていますし、特に軽油自己着火型内燃機の場合、原油を蒸留して最初に得られる揮発油型内燃機ほど燃調にも厳しくなく、お手軽改良の定番となっています。それでは早速、本題に入りましょう。 ●てきとう改良その一、 内燃機を良く眺め配管などを確認しろ 私の車、大角(四じぇいびい一)の場合、だいたいこんな感じでしょうか。内燃機からの排気は過給器を通って消音器へ。空気清浄器からの吸気は過給器から暖気弁(寒冷時の暖機運転を早めるため、吸気を絞る弁)を通って過給気冷却器を経て吸気多岐管から内燃機へ。私の車は乗用登録なので、吸気多岐管には排気煙再循環装置が付いている。 過給圧の制御は、過給器に取り付けられた加動器で逃がし弁を駆動し排気を調整する事によって行われている。加動器の過給圧の取り出しは、過給器(過給器住宅)から直接取り出している。 ところで、四じぇいびい一の場合吸気多岐管には圧力を取っている口がありません。この場合、吸気多岐管に穴を開け筍を取り付けます。ところがこの筍、ちょうど良い大きさの物がなかなか有りません。「あなた自身でそれをしなさい商店」で売っている気動工具用は太すぎです。長谷川さんの会社では一個単位で販売していますが、一個だけ頼むのも何ですし(最近は黄色い帽子でも売っている)。壊れた自伝車の制動器鋼索の留め具が手頃な大きさだったので、これを加工し取り付けました。
●てきとう改良その四 邪魔者は殺せ 次に過給圧上昇をやる前に抵抗となる不要な弁を殺します。四じぇいびい一の場合、暖機弁は抵抗になるので取ってしまいましょう。暖機弁は過給気冷却器に取り付けられているので全て取り外します。暖機弁の加動器と弁接続されているねじを緩め弁の中身を全て取り出します。 このままでは、弁の軸の穴が空いたままになってしまうので、軸の不要な部分を回転砥石で切り落とし、合成樹脂系接着剤で元通り接着します。ほ〜ら、これで外見は純正のまま、不要な抵抗物はなくなりました。 次に排気煙再循環装置弁を殺します。排気煙再循環装置弁は加動器に接続されている導管を抜いても殺せますが、過給圧がかかったときに多少漏れるようです。排気煙再循環装置弁を外し防漏板を取り出します。適当な金属板を用意し、防漏板から型取りし切り抜きます。あまり薄い板は不可です。軽量合金板だったら拾五分の一寸くらいでしょうか? 私は拾った「車でお金貸します」の看板を二枚重ねで使いました(これだと金鋏でれるし何しろただ。但し、後で腐食して穴の空く可能性あり!)。 次に過給上昇ですが、過給を上げるにはいくつかの方法があります。一番お金のかからない方法は、逃がし弁の加動器がねじ止めになっている場合には、ここに座金などを挿入すれば良! 過給圧の調整は座金の枚数で行います。次に簡単なのは、過給圧調整器を買ってきて取り付ける方法です。具体的な取り付け方法は製品に付いている説明書を見れば分かるでしょう。(今回はこの方法は採用しません。高いから) さて、究極の方法は、先の丸いタガネと金槌を用意し、加動器の棒を気合い一発!! はっきり言ってこの技は難しい! 13湯麺のバブしか出来ないかもしれない…。 力加減はバブに聞いて下さい。
さて、以上で過給圧上昇は完了です。過給圧計はしようがないとして、できるだけ安く上げたつもりです。更に良い案がありましたら、ご一報下さい。 |