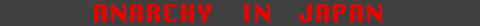
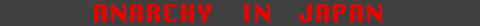
「難波大助大逆事件 虎ノ門で現天皇を狙撃 1979年」(黒色戦線社、文句省推薦図書)
- おなじみ(何がおなじみだ)難波大助さんの天皇暗殺未遂事件です。 現天皇とはヒロヒトの事でアキヒトではない。難波さんは始めはアナキストみたいだが途中でコミュニストに転向したみたいだ。関連本に「煉獄 女たちのの虎ノ門事件」(岩田礼、三一書房)がある。 (K)
「誘う女 ドキュメント日本閣殺人事件」(吉田和正、三一書房 1994年)
- 温泉旅館の女将たるべく、連続殺人を犯し、戦後初の女性刑死者となった小林カウのドキュメント。犯罪実録物は数多いが、迫真力をもって迫る内容を有するものは少ない。あたかも殺人事件現場に立ち合っているかのような名場面を有する傑作だ。自己の欲望にどこまでも忠実で、その為には殺人という大罪も厭わない。そのストレートな目的指向性が、読むものにカタルシスさえ惹起せしむる。与えられずば奪えばよい。人間とは、こういう力を秘めた存在なのだ。心せよ。 (N)
「愛犬家連続殺人」(志麻永幸 角川文庫 2000年)
- 「人間の死は、生まれた時から決まっていると思っている奴もいるが、違う。それはこの関根元が決めるんだ。俺が今日死ぬと言えば、そいつは死ぬ。明日だと言えば、明日死ぬ。間違いなくそうなる。何しろ、俺は神の伝令を受けて動いているんだ」(関根元)
こう切り出せば、鳴呼またかの電波系シリアルキラーかと誤解する向きもあろう。しかし関根元の前には、伝説の殺人鬼たちすら甘く見えてしまう。彼こそは殺人モダニズムの推進者/一人アウシュビッツであるからだ。なれば、本書こそ奇跡のノンフィクションと呼ばれるに不足はない。
しかも、この「埼玉県愛犬家連続殺人事件」事件が、日本犯罪至上屈指の、個人が(共犯者が存在したとは言え)為しうる連続殺人の極北でありながら、阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件という相次ぐこれまた奇跡的な大事件に隠され、しかも前年(94年)に解決を見た関西愛犬家殺人にかぶさり、最早世紀末には、この事件自体が世間の自目から完全に隠されてしまった。にもかかわらず、その共犯者の手により見事に蘇ったということ。正しく全てが奇跡的!
「ボディを透明にする」という画期的な殺人のステルス化技術により、意図もたやすく連続殺人を可能にした関根ではあるが、瞠目すべきは、強烈なキャラクター、それを支える心的な強度であろう。大義名分も「精神異常」もなしでこの偉業/異業を果たす、その超絶したメンタル力にただただ驚嘆するばかり。人間の、個人の持てる力の可能性を示すものである。それが圧倒的に負であったとしても。 (乱乱)
「大西洋漂流76日間」(スティーヴン・キャラハン 早川文庫 1999年)
- 著者S・キャラハンは、1982年大西洋上でヨットレース中難破し、救命イカダ(ゴム製)で、カリブ海までの過酷な76日間の漂流を体験することになる。
手持ちの、わずかばかりのサバイバル用食品が絶えた後、彼はまったくの自給自足で生き延びねばならなくなってしまうのだ。頼るべき他者もシステムもなく、ただ自己の能力と自然の利用のみが生存の条件である。ここに至り彼は、国家、社会、市場、ありとあらゆるシステムから解放された、絶対自由のポジションを得たわけである。
洋上のユートピア!しかし、自分の一挙手一挙動が即生死につながるというすこぶる苛烈な。
一つの連想が起こる。テオ・アンゲロプロスの撮った「シテール島への船出」(1984)である。亡命先から帰還した老革命家が再び祖国を追われ、行先も失い、浮桟橋のみが唯一の居場所となり。そして沖合いに連れ合いと消えて行くというラストシーンが用意されていた。
国家やシステムからの自由は、地上では達し得ない、生を担保に獲得する以外に道はないという暗示なのだろうか。 (乱乱)
『難波大助・虎ノ門事件』愛を求めたテロリスト(中原静子 影書房 2002年)

- 難波大助関連の本を読んだのは何冊目だろ?
5、6冊はもう読んだとおもうが、いまだに新刊が出るとは驚きです。
この本は特に目新しい新事実というのはなかったですが、今までの本のように、難波大助を神聖視しせず難波大助の弱さというものを検証しています。
作者は長年にわたり大助の生まれたところをフィールドワークし、ぼくにとっては新しい難波大助像というものを与えてくれました。
ちなみに大助の親戚などはコミュニストが多いし、関係者も多く、実際大助は民族主義、アナーキズム、コミュニズムっていう思想遍歴をとげているのに、何故かアナ系に人気があるのはなんでだろ?
コミュニストで大助を好意的に書いているのは見たことないです。
やはり「天皇制」という問題をコミュニストとアナーキストでは捉え方が違うからか?
(梅田のんきち)
「久さん伝 あるアナキストの生涯」(松下竜一、講談社 1983年)
- 大正期のアナキスト和田久太郎の生涯を書いた力作、この中に出てくる久板卯之助の生き方や死に方に何か惹かれるものがある。 (K)
「ヤマザキ、天皇を撃て!」(奥崎謙三、有文社 1980年)
- 反天皇ターミネーター奥崎謙三がいかな人物であるかその一端は、あの怪作ドキュメント「ゆきゆきて神軍」のヒットによってあまねく天下に知れ渡った。しかし、この本が世に出た時は、「天皇を撃て!」などと平然と書名にかかげることすら奇跡に近いものがあった。復讐への常ならざる執念。抜群の行動力。意表をつく独創性。超論理性等、奥崎謙三は常に我々の予想を裏切る存在である。電波系など小賢しいラベリングを試みるアホもいるようだが、それを言うなら奥崎は自ら電波を放射する人間である。本書は、彼の原点たるニューギニア戦線から、天皇パチンコ狙撃事件までを描く。思想書であり冒険譚でありドキュメントであり神話ですらありかつそのどれでもない空前絶後の書を一読し、アナキズムなど一笑に付す彼の宇宙パワーを我がものとしよう。って言っても無理だけど。
追記:今度はあの根本敬とタッグ組んで何かまた始めるらしい。今世紀最後のお楽しみだ。 (N)
「俺 勝新太郎」(勝新太郎、広済堂文庫 1998年)
- 現実ー非現実と倒立させることの出来る芸人勝新太郎。修行やサリンに頼らずとも、その圧倒的な存在が、地上の磁場を歪ませる。凡百の芸人自伝ではない。個性の凄味を感じさせる作品だ。 (N)
「地獄からの生還」(梶原一騎、幻冬舎アウトロー文庫 1997年)
- 奇しくも、逮捕取り調べから始まる自伝ということでは、勝新太郎の前掲書と同じだ。人は個々その力に応分の所有が可能なのだとは誰かの弁だが、まさしくシンプルな世界に生きれた幸運さと、それと等価の負債を払わねばならなかった不幸さとが並存する生死である。近年、ダークサイド梶原などと言われ、サブカル世界でも、負の作品にも光が当たりつつあるが、その芥の中にこそ、人間をより描けたという事実があることを看過しては惜しすぎるのだ。 (N)
「河童の手のうち幕の内」(妹尾河童、新潮社 1992年)
- 「他者に解りやすく説明する」というのは、なかなか難しい。自分が見たり聞いたりしたこと・自分の考えを説明することは、人間にとって重要なコミュニケーション能力だ。しかし、自分にはその能力が欠けているようで、その面で優れた才能を持っている人には嫉妬に近い羨望を覚えてしまう。
妹尾河童は、どうして何でも解りやすく描けるのだろう。彼の描く絵図にしても文章にしても、これ以上解りやすいものはないというくらい解りやすい。「手のうち」というのだから、その秘密が解るかもしれないと思い、期待して読んだ。
うーん。そういうことなのか。人並外れて旺盛な好奇心と納得するまで調べないと気がすまない、シツコイ性格がその秘密のようだ。解りやすいのは、自分が納得するまで徹底して調べた結果を書いて(描いて)いるかららしい。
人はつい、他者から聞いたこと・何かで読んだことをそのまま引用したり、よくわかってもいないクセに、エラそうに講釈したりする。また、都合の悪い部分をゴマかしたり、カッコよく見せようと脚色したりする。妹尾河童にはそういう所がない。自分の好奇心に対して素直に、躊躇せず対象に迫っていく。
これには、絵を描くときの観察力が大いに関係しているようである。絵を描くためには、細部に至るまで正確な観察をしなければならない。ぼんやりと見ていたのでは細密な絵を描くことなどできないのだ。
ぼくが「解りにくいもの」しか書けないのは、自分がよくわかっていないことを書こうとするからだろう。「解りやすく」書くためには、何よりも対象を正確に把握していなければならないのである。いたずらに年齢だけとっていて、何もわかっていないのに、わかったフリをするからだ。
コミュニケーション能力・表現能力は、結局自分の観察力・理解力が基本なのだということを、この本によって思い知らされた。 (T)
「義賊伝説」(南塚信吾 岩波新書 1996)
- ハンガリーの義賊であるロージャ シャーンドルの話であるが、前半は鼠小僧やロビンフッドなどの考察もしてある、その中で義賊の定義にアナキストも入れている。
本書による義賊の定義とは、
1、不当な罪ゆえにアウトローになった。
2、悪を正す。
3、豊かな者から奪い、貧しい者に与える。
4、正当防衛または正当な復讐以外に殺人をしない。
5、許されるならば共同体に迎え入れられる。
6、民衆に賞賛され、助けられ支援される。
7、裏切りによってのみ死ぬ。
8、姿を見せず、不死身である。
9、国王や皇帝には敵対しない。
(悪いのは在野の支配者、聖職者である)
なるほど義賊はかっこいいのである、がアナキストが義賊かどうかであるかは疑問がある。
まず、個人主義アナキズムでは2、の「善悪」など誰が決めるかという問題であるのと、最大の問題は9、の国王や皇帝などに敵対しない事だ、これでは水戸黄門と同じで、そのシステムが腐敗しているから起きる問題を小役人の「悪」に還元し、ファンダメンダルな「悪」を正さない不条理性を有しているの同じであるからだ。 (K)
「FOR BIGINERS 大杉栄」(文:竹中労/挿画:貝原浩 現代書館 1985年)
- 竹中労は戦後民主主義者ではない。稀代の風雲児<正気の狂人>大杉栄の生涯を綴った「いささかかたやぶりなこの絵本」は、戦前――大正から、戦後――昭和を照射する、不自由の時代にこそ真に自由な魂の持ち主が生き得たという逆説を提示している。この書は現実的にはおおよそ何の役にも立たない、竹中自身、たぶんそれをわかって書いたはずである、しかし、稀代の講談師<世界革命浪人>竹中労はこの書の冒頭に大杉の愛唱したフローベールの詩を置くと共に、その巻末では、かつて自らを自分の小説の主人公になぞらえ「ボヴァリー夫人は私である」と語ったフローベールよろしく、こう書いている「大杉栄は、私である!」と。
本書では、エピソードに富んだ大杉の生涯を、幼年幼年学校中退の少年時代、大逆事件前後、アナ・ボル抗争、日本脱出記……と追いつつ、特に、大杉と妻の神近市子、愛人の伊藤野枝の情痴のもつれから起きた「日蔭茶屋事件」と、震災下の帝都での甘粕正彦憲兵大尉による大杉(と伊藤野枝、甥の橘宗一)殺害事件に筆をさいている。
竹中の筆は、勝手に愛人を作っちゃ「自由恋愛」とほざき、生活に困ればヌケヌケと政府高官に金をせびる、といった大杉の無茶苦茶な無責任野郎ぶりも包み隠さず描いている。しかしその姿にはなぜか偽善的欺瞞は感じられず、むしろその顰蹙を怖れぬ剛胆な居直りに痛快さを覚えずにいられない。
だが、わたしはどうしてもサリエリの視点からモーツァルトを見るように、自由の魂の化身大杉のネガの如き、犬の魂の男甘粕の視点から大杉を見てしまわずにいられない。読めば読むほど「しかし到底わたしはこんな風には生きられない」という感が募るばかりだ。大杉はきっと、そんなことを言う人間にこそ「何あに、駄目なことがあるものか、やって見ろ、力の限り押し通して見ろ――」(「無鉄砲強情」より)と言うのだろうが。
本書で「この国に革命はあるか? 私の目の黒いうちはあるまい。過程に奮迅すればよし」と書いた竹中労の死からもうすぐ10年、本書の竹中の言葉に依れば、まさに今「昭和の後の大正」を生きる我々は、大杉=竹中の言葉と生きざまをどう受け止めるべきか…… (佐藤<人民の敵>賢二)
「バクーニン(上・下)」(E・A・カー 大沢正道/訳 現代思潮社 1970年)
- 絶版です。古本屋で探して下さい。わたしは中野のサンプラザ図書館で見つけて読みました。
アナキズム史の巨人「実在のドン・キホーテ」の生涯。「トロツキー自伝」の如き血湧き肉踊る冒険活劇を期待して読むと、何のことはない妄想癖の強烈のとっちゃん坊やの迷走劇ばかりで思い切り肩すかしを喰らう。実際、はじめて読んだときは暗澹たる思いがしたが、数年後に再読したら超面白かった。これは悲劇とも喜劇とも読める、まったく『ラ・マンチャの男』そのままだ!
若き日の文豪ツルゲーネフを感嘆させ、音の魔術師ワーグナーを敬服させ、三つの国の監獄を経て、虚実ないまぜの独白記でロシア皇帝の情状酌量を勝ち取り、シベリアから幕末の日本を経て世界を一周してヨーロッパに帰還、マルクスと大喧嘩の末インタナショナルを分裂させる……とまぁ無茶苦茶な人生である。また、貴族の生まれにして無政府主義者、かと思えばロシア民族主義者で反ユダヤ主義者、悪意はないが乗りやすい性格でイタリアのガリバルディや狂信者ネチャーエフと安易に意気投合しては喧嘩別れ、財産にこだわらず異様な気前の良さの反面生涯借金まみれ、大酒のみの大飯喰らいの愛煙家なのだがインポ、とバクーニンはとかく矛盾の人だ。だが、一貫性などくそ喰らえ、というのがアナキストなのかも知れない。
借金まみれのうえ常に官憲に追われ、革命家業界の仲間にも敵が多かった筈なのに、彼は一生涯奇妙な脳天気ぶりを保っている、その「心のゆとり」は貴族の生まれのゆえであろうか?
訳者の大沢も述べている通り、バクーニンの思想の中身について詳しく触れてないのはいまひとつだが、その人生行路だけでも読み応えは十分ある、著者カーは共産主義寄りの近代主義者だが、これも訳者の指摘通り、カー自身書きながら無意識のうちにバクーニンに好感を寄せているフシがある? (佐藤<人民の敵>賢二)
『明治流星雨』(原作:関川夏央/作画:谷口ジロー 双葉社 1995年)
- 日露戦争後から明治末までを舞台にした漫画『「坊ちゃん」の時代』シリーズ五部作の中の一冊、幸徳秋水と大逆事件にまつわる人々を描いた作品である。
土佐の壮士から自由民権運動の挫折を経て無政府主義を標榜した秋水幸徳伝次郎、不遇の少女時代を経て秋水の同志となった菅野、その菅野を慕う寒村、獄中の大杉と堺、紀州和歌山の「赤ひげ」的医師大石誠之助、といった無邪気で無力な革命家たち、一方、未だ近代国家として発展途上の明治日本では官の抑圧は必要悪と考え彼らを追いつめる元老山県有朋、その腹心の国事犯担当警視伊集院彰韶(それぞれ『坊ちゃん』の「校長」と「赤シャツ」のモデルと解される)、無力な傍観者の文士漱石と啄木、といった群像、そしてほとんど空想的レベルの天皇暗殺計画に、ほとんどこじつけの如き強引な検挙、という大逆事件の実相が描かれている。
この一冊のみ単独で読むことも可能だが、シリーズ全作を通して読まれることをお薦めしたい。全シリーズでは、第一巻の『「坊ちゃん」の時代』は夏目漱石を主人公格に置き、荒畑寒村も登場、第二巻『秋の舞姫』は森鴎外が主人公格で、小説「舞姫」のモデルとなったドイツ少女エリスと若き日の鴎外の物語、第三巻『かの蒼空に』は石川啄木が主人公格、この巻から幸徳秋水、菅野スガらが登場、第四巻『明治流星雨』につながる展開となる、最終巻『不機嫌亭漱石』は再び漱石が主役格となり、漱石が夢の中で大石誠之助と語り合ったり、大逆事件裁判での幸徳の陳述書を密かに書き写す啄木の描写などもある。
全編を一読されれば、明治末という時代が実はまぎれもない「現代」であることに気付くだろう。作中、特に漱石、鴎外らとの対比で若い啄木のキャラクターは軽薄なお調子者として現代的に描かれているが、実際、日露戦争と大逆事件を経た大情況の沈静化――明治のポストモダン――の後の内向の時代の病を指摘した啄木の『時代閉塞の現状』は何と現代を言い得ていることか。 (佐藤<人民の敵>賢二)
「黒い花」「黒い花 續」 (立野信之 新潮社 1955年)
- 本編では渡辺政太郎の死に始まり、アナ・ボル抗争まで。続編では大杉の渡仏から暗殺、ギロチン社福田大将狙撃事件まで、大杉を中心に、彼を取りまく多彩な人々が生き生きと描かれている。
和田久の「大杉の糞はバクウニンの匂いがあり、毛穴はクロポトキンの匂いがあるが、どこを突いてもしみ出す血は大杉の匂いしかない」という言葉が印象的。野枝の心情が細かく書かれているので、彼女を嫌いな人も少し見直すかも。
オールスター総出演なので、誰のファンが読んでもそこそこに面白い。各々のエピソードが凝縮されているので「既にどこかで読んだ話」と物足りなく思う向きもあろうが、初心者が人物の大まかな関係をつかむには最適。全体の印象としては、作者の思い入れは飄々とした村木に注がれている感じがした。 (荒若睦月)
「墓標なきアナキスト像」(逸見吉三著 三一書房 1976年)
- このWebページを訪れている人はたぶん、日本のアナキストの思想と運動に興味があると思う。そういう人のなかで、大杉栄、石川三四郎、岩佐作太郎はもういいから、他の多くの人たちの歴史はどうなんだろうと気になっている向きにはうってつけの著作。著者自身が古くから関西で活動したアナキストで、大戦後も中立労連系のアナルコサンジカリストとして活躍したようだ。おやじさんは<借家人同盟>で有名な逸見直造である。
著作の内容は題名どおり、ほとんど歴史に名を残さなかったか、そうでなくても上っ面のみでしか云々されてこなかった戦前アナキストたちの評伝で構成されている。何よりも無告の活動家として闘ってきたなかまに対する著者の愛情が、読んでよかったとぼくに思わせた。感傷がだめなに人とっても、無名の戦前アナキストの足跡の一端を知る上では貴重な一冊であるという評価は動かせないだろう。 (noiztracker)
『箆棒な人々――戦後サブカルチャー異人伝』(竹熊健太郎 太田出版 1998年)
- イベント仕掛け人の康芳夫(日本に「オリバー君」を連れてきたり「猪木VSモハメド・アリ」をプロデュース)、特殊挿画家の石原豪人(60年代少年誌で、後はホモ雑誌で活躍)、作家の川内康範(「月光仮面」「レインボーマン」ほかの原作者だ)、ダダイスト芸術家の糸井貫二(大阪万博で全裸疾走などアート界の伝説的怪人)、という、四人のいずれも「箆棒な人々」へのインタビュー集。初出はすべて『QuickJapan』誌。
虚構のイカガワシサにこそ人間の本性を見る康、無邪気で陽気な耽美主義者の石原、戦後が忘れた日本人の業を直視し続ける川内、意味の解体を徹底した天性のアーティスト糸井、と、いずれもタダモノではないこの四人は、全員60代以上の老人、ことに康以外は戦中世代である。彼らの生きざまには、しょせん戦後の豊かさを前提とした上での過激ぶりっこに明け暮れる我が世代を顧みずにいられない。そう、本書は、四人の「箆棒な人々」を通して戦後の子である竹熊が自身を照射した本でもある。
竹熊の著作としては、オウム事件を契機に、世間嫌いの偏屈な個人主義者、非生産的なことにのみ熱中する「おたく」として生きる者としての自負を胸を張って主張した『私とハルマゲドン』(太田出版)が秀逸だった。
偏屈、変人、世間嫌いを通すにも、それなりの筋ってもんがあるんだよ。 (佐藤<人民の敵>賢二)
「住民運動の原像」借家人同盟と逸見直造伝 (玉川しんめい 白井新平共著 JCA出版 1978年)
- 逸見直造とは、あまり知られていない人であるが、白井新平がいうところの「土着アナキスト」である。
彼は明治の時代にアメリカに渡り「天皇ムツヒトへの攻撃」や「大統領ルーズベルトの暗殺企画」で知られるサンフランシスコ革命党にも関与していたみたいだが、日本領事館のスパイが革命党に居た為、それほど深くはかかわっていなかった。のちにIWW(注1)に吸収されるknight of labour(注2)の活動は積極的におこなっていたようである。
このknight of labourでの活動が日本に戻って来ての思想的基盤になり、やがて大阪では社会主義者だけではなく、ひろく大衆一般にまで知られる人になるのだ。
直造はアナキズムに傾倒しているので(というよりサンディカリズムか)基本的には法は認めないのだが、利用できる法律があるとそれを使って裁判をするのだ。それもかなりの数の裁判を行っている。対行政や悪地主などを相手に戦っているが、相手の弁護士が直造相手ならお金を吊り上げるほどやっかいな相手だったらしい。
また東京のアナキストとは違った実践的アナキズム、白井のいうところの「土着アナキズム」だったようだ。
例えば、直造は映画館を任せられていた時期があった。その映画館に看板を描かせるのだが、それがまったく上映予定も映画会社も作る予定もない看板を描かせるのだ。「近日封切! 大塩平八郎の乱、盗賊は大阪より紀州にありー」とか「嗚呼ニ○三高地の激戦!一将功成って万骨枯る」 たくさん死体の上に立つ将軍が剣を振り上げた看板だって(笑)。
直造の息子、吉三もギロチン社に関与するアナキストである。彼も関西を代表するアナキストだったのだが東京からは無視されるのである。白井はこう言う。「直造はアナ・ボル分裂前からの社会主義者というより実践的な社会運動の大立物であったのに対し、吉三はその生い立ちからアナ系の交友関係にコミットして、実質的には昭和の50年を通じて関西を代表するアナーキストでありながら、東京のサロン・アナからは、軽視、無視されるのは、吉三にとって、むしろ誇りでもあるかもしれない」
なお玉川と白井は直造の死因について、見解の相違があるようである。玉川は事実だけ(中島公会堂の地下食堂で食事中に心臓疾患で死亡)を記しているように思えるが、白井は東の大杉、西の直造というように、どちらも虐殺されたと記している。
直造の奏儀には新聞ダネになるほどの人があつまり、家を出た先頭の人たちが葬儀場に着いたときには、まだ最後列の人たちは家を出れなかったそうである。(注1)IWWはロシア人亡命者やドイツ系亡命者が作って団体。
フランス系サンディカリズムを実践し、エマ・ゴルードマンなどがいた。また、サッコやバンセッディはIWWにいたため冤罪をきせられ処刑された。
(注2)knight of labour(労働先駆者団)はアメリカの生活防衛のための自然発生的労働団体で、秘密結社的な動きもあったようだ。
このように書くとテロとかやっていたのかなあ? と思えるが実際は「あの肉屋高いぞー」と言ってみんなで不買運動をするような秘密結社だったらしい。最後に資料をくださった玉川しんめい様、ありがとうございました。感謝します。 (のんきち)
『釜ヶ先赤軍兵士 若宮正則物語』(高幣真公 彩流社 2001年)
- この本のタイトルは赤軍兵士になっているのが、ぼくには不満である。
ぼくが出会った1980年代後半には若宮さんは完璧なアナキストになっていたし、 赤軍的(ボリショビズム)な物からは決別していたし、また赤軍に限らずコミュニズ ム的なものを嫌っていたように思うからです。この本の後半に書かれている、アナキスト時代の若宮さんに最初に会ったのは、大 阪の太融寺でやっていたアナキズム連合だったと思う、若宮さんはカブのようなバイ クで白いヘルメットをかぶってやってきていた。その連合では、みんなが持ちまわり で、アナキズムについて話していたように思うが、主催者(現在、この人、広島のほ うでアナキストという看板だけあげて、ほとんど国家主義のようなことを言っている トンデモアナに変質してしまったが、トホホなオヤジだよー)のIさんから若宮さん も何か発表してよー、と言われて、笑っていただけで、特に何かをアナ連で言いたい ようなことはない感じだった。
その後、若宮さんから誘われて、釜ヶ崎でAINのメンバーらと「相互扶助の会」 に参加するわけですが(その頃は労働者食堂は休業状態だった)、『釜ヶ崎赤軍』の 本では、労働者に扶助ばかりするのでうまくいかなかったように書かれていますが、 ぼくはこれには激しく違和感を感じています。何故なら、「相互扶助」の会の失敗の 原因は労働者に扶助するだけ、という些細な理由ではなく、(その証左に若宮さんは 扶助することなど苦とも思わず、その後もやっていたし、ある夏の日に若宮さんの借 りていた家にいったときに、日雇い労働から戻った若宮さんは自分の家に引き取って いた労働者にお弁当を買いに行き、ぼくらにスイカを買ってきて食べろとすすめた、 なんでもないことなのだが、その時、ぼくはこの人には絶対かなわないなー、と思った)「意識」の問題だったと思うのです。
相互扶助のほんとの意味を理解できていたのは、若宮さんとアナキストのKさんと、あと数人の人だけで、ぼくも含めて相互扶助の会に参加していた人たちはそこまでの意識に(アナキズムの難しさはそこにあると思いますが、万人の人間が理解しずらいという点において)到達できていなかったように思います。
つまりは、この本にあるように、扶助するばかりだったからという矮小化したような事実ではなく、アナキストあるいは相互扶助という観点においての「意識」」だったのです(もちろん、ぼくの一人よがりな思いかもしれませんが)。ただ、この本の前半で書かれている若宮さんは、若宮さんの赤軍時代を断片的にしか知らなかった、ぼくには大変参考になった。
ぼくたちが会ったときの若宮さんはアナキズム的な思想などほとんど語らず(ただ、ぼくの目指しているのは「キリスト教的アナキズム」です、というのは印象的だった)実践的な運動を志向していたように思います。もっと、書きたいこともありますが、批判的(もちろん若宮さんにではなく、若宮さんを取り巻いていた状況あるいは、自分自身に)あるいは、ドロドロした嫌な部分も書いてしまいそうなのでここで終わります。 (のんきち)