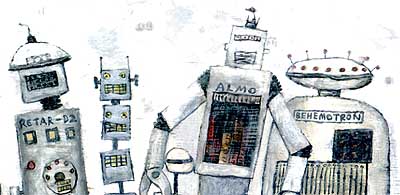Blue Sky On Mars
Matthew Sweet
(Zoo)
 もしかしたら、今ぼくがいちばん好きなプロデューサーかもしれないブレンダン・オブライエンとまたまた組んだ新作。2年ぶり、かな。タイトル文字が、なんとイエスのジャケットでもおなじみだったロジャー・ディーンによるもので、さらにタイトル自体にも“火星”なんて言葉が入っているし、ジャケットがこんなだし。おいおい、プログレか……と一瞬眉をひそめたぼくですが。
もしかしたら、今ぼくがいちばん好きなプロデューサーかもしれないブレンダン・オブライエンとまたまた組んだ新作。2年ぶり、かな。タイトル文字が、なんとイエスのジャケットでもおなじみだったロジャー・ディーンによるもので、さらにタイトル自体にも“火星”なんて言葉が入っているし、ジャケットがこんなだし。おいおい、プログレか……と一瞬眉をひそめたぼくですが。
なわきゃないよね。全12曲、合わせて40分弱。イエスの1曲にも満たない(笑)。相変わらず、繊細さとひねくれ心とを絶妙に混ぜ合わせた独特のポップ・ワールドが展開されていて。ばっちり。これまでのアルバムによく参加していた元テレヴィジョンのリチャード・ロイドやルー・リードとかとの仕事でも知られるロバート・クインといったギタリストたちは、今回はなし。ほとんどの曲のベースとギターをマシュー・スウィート自身が担当している。そのぶん、ちょっと箱庭っぽくなったかなとも思うが、まあ、箱庭っぽいほうがこの人の味が出るとも言えるし。
いい曲いっぱい。ローリング・ストーン誌あたりからは“マンネリだ”と責められてるけど、マンネリもまたこの人らしい。
Dig Your Own Hole
The Chemical Brothers
(Virgin)
 世間で盛り上がっているほど、ぼくはこのイギリスのにーちゃんたちを"革新的"だとは思っていないのだけれど。まあ、革新的であるか否かは別にして、ぱっきり今の時代の気分を表現しているポップ・ユニットだなとは思う。ヒップホップもあるし、ダブっぽい要素もあるし、もちろんテクノだし、ジミ・ヘンドリックスやスライ・ストーンも見え隠れするし。今、おいしい要素はたっぷり。オアシスのノエル君が参加した全英ナンバーワン・ヒット「セッティング・サン」も入っているし。これぞ今の"売れ線"なのだろう。
世間で盛り上がっているほど、ぼくはこのイギリスのにーちゃんたちを"革新的"だとは思っていないのだけれど。まあ、革新的であるか否かは別にして、ぱっきり今の時代の気分を表現しているポップ・ユニットだなとは思う。ヒップホップもあるし、ダブっぽい要素もあるし、もちろんテクノだし、ジミ・ヘンドリックスやスライ・ストーンも見え隠れするし。今、おいしい要素はたっぷり。オアシスのノエル君が参加した全英ナンバーワン・ヒット「セッティング・サン」も入っているし。これぞ今の"売れ線"なのだろう。
機械を駆使しながらでもロックすることはできる、と。そういうことを力強く主張しているかのようなアルバムですが、そんなこと今さら言われたって……って感じだし。それも含めて実に今っぽいポップ・アルバムと解釈したほうがいいかも。アメリカ産のヒップホップはよく聞くけど、テクノのほうはほとんど聞かないぼくの耳にはちょっとビートが軽い。こんなものなのかな。
こういうのもいいな、とは思うけれど、こっちのほうがいいとは思わない。
Pulsars
Pulsars
(Almo)
 ケミ・ブラと同じようなコンセプトのもと、アメリカのシカゴから登場したのがこのパルサーズ。といっても、こっちはけっこうほのぼのしてる。デイヴィッドとハリーのトランフィオ兄弟による、んー、まあ、なんというか、アンビエント・テクノ・ポップ・ロックンロール・ユニットみたいな。そんな感じ。コーギスみたい。エコ・バニみたいな感じもあるし、ジョイ・ディヴィジョンとかキュアを思い出させるときもあるし。そういうアメリカ人の音楽です。すでにオアシスやらブラーのシカゴ公演のオープニング・アクトなどをつとめて、地元では人気者らしい。今はチボ・マットと全米を回っているのだとか。
ケミ・ブラと同じようなコンセプトのもと、アメリカのシカゴから登場したのがこのパルサーズ。といっても、こっちはけっこうほのぼのしてる。デイヴィッドとハリーのトランフィオ兄弟による、んー、まあ、なんというか、アンビエント・テクノ・ポップ・ロックンロール・ユニットみたいな。そんな感じ。コーギスみたい。エコ・バニみたいな感じもあるし、ジョイ・ディヴィジョンとかキュアを思い出させるときもあるし。そういうアメリカ人の音楽です。すでにオアシスやらブラーのシカゴ公演のオープニング・アクトなどをつとめて、地元では人気者らしい。今はチボ・マットと全米を回っているのだとか。
良きころのモータウンと、良きころのニュー・ウェイヴ〜シンセ・ポップの味をミックスした、どこかチープでノスタルジックな音作りが持ち味。いいよ、これ。けっこう楽しい。所属するアルモ・レコードの設立者のひとり、ハーブ・アルパートにもトランペット吹かせてたりして(笑)。やるね。
Hand It Over
Dinosaur Jr.
(Reprise/Blanco Y Negro)
 久々。中心メンバーのJ・マシスがソロで行なったアコースティック・ツアーのライヴ盤を出したり、サントラ盤『グレース・オブ・マイ・ハート』に参加して映画でマット・ディロン演じていたブライアン・ウィルソンらしき男がらみの音楽を手がけたり。そんなだったもんだから、こりゃ解散するのかなぁ……と、漠然と覚悟を決めてたんだけど。
久々。中心メンバーのJ・マシスがソロで行なったアコースティック・ツアーのライヴ盤を出したり、サントラ盤『グレース・オブ・マイ・ハート』に参加して映画でマット・ディロン演じていたブライアン・ウィルソンらしき男がらみの音楽を手がけたり。そんなだったもんだから、こりゃ解散するのかなぁ……と、漠然と覚悟を決めてたんだけど。
3年ぶりの本作でも、持ち味はそのまま。うれしい。グランジって言葉もすっかり死語ですが。そんな言葉では包括しきれなかったダイナソーにとってはいい時代かも。けだるくて、ラウドで、でも深いところでむちゃ美しいダイナソー・ワールドが楽しめる。
ドラムはジョージ・バーツが担当。マイ・ブラディ・バレンタインからケヴィン・シールズとビリンダ・ブッチャーも参加。神経質そうでいて、しかしけっこう太いグルーヴをたたえたJの歌声は、やっぱよいっすねー。
Fantastic Spikes Through Balloon
Skeleton Key
(Capitol)
 バター08のリック・リーとスティーヴン・カルーンによるニュー・プロジェクト。ギター、ベース、ドラム、パーカッション……という妙な4人組。でも、このパーカッションがなかなかいい。いわゆる通常のギター・トリオのハード・ドライヴィングなロック・サウンドに、ティンバレスが加わっているわけで。シャープでタイト。太めのバンド・グルーヴにうまいことスピード感を加味している感じ。各メンバーもかなりの腕と見た。そうとうファンキー。ミクスチャー・ロックっぽい手触りではあるけど、サウンドの感触は新鮮だ。
バター08のリック・リーとスティーヴン・カルーンによるニュー・プロジェクト。ギター、ベース、ドラム、パーカッション……という妙な4人組。でも、このパーカッションがなかなかいい。いわゆる通常のギター・トリオのハード・ドライヴィングなロック・サウンドに、ティンバレスが加わっているわけで。シャープでタイト。太めのバンド・グルーヴにうまいことスピード感を加味している感じ。各メンバーもかなりの腕と見た。そうとうファンキー。ミクスチャー・ロックっぽい手触りではあるけど、サウンドの感触は新鮮だ。
他のことは全然わからず。だって、ジャケットのクレジットとか、ちっこい文字で、しかも全部逆版。読みにくくて(笑)。そういう人たちみたいです。ひねくれやがって。
Dust Bunnies
Bettie Serveert
(Matador/Capitol)
 なーんか、不思議とアメリカで人気のあるオランダのバンド。これが3枚目だと思う。ダッチ・ロック、ね。平成のショッキング・ブルー? 違うか。
なーんか、不思議とアメリカで人気のあるオランダのバンド。これが3枚目だと思う。ダッチ・ロック、ね。平成のショッキング・ブルー? 違うか。
ペイヴメントあたりと仕事してるブライス・ゴギンのプロデュースのもと、ウッドストックのベアズヴィル・スタジオでレコーディングされている。ヴォーカルのキャロルちゃんのどこか投げやりな歌いっぷりが印象的。でも、近ごろ多い乱暴なだけの女性オルタナ・シンガーとは違って、基本的にはあったかい歌声。そこんとこがいい。アメリカのオルタナ・ロック・シーンを外側からながめつつ、ちょっとポップにデフォルメしてみせたバンドってところだろう。
Take a Look Over Your Shoulder
Warren G
(G-Funk Music/Def Jam)
 ドクター・ドレの兄弟ってことで逆に損してるのかなぁ。ドレとかスヌープのような大物として扱われることが少ないような気がするウォーレン・Gですが。
ドクター・ドレの兄弟ってことで逆に損してるのかなぁ。ドレとかスヌープのような大物として扱われることが少ないような気がするウォーレン・Gですが。
でも、この人もかなりの才能。ごきげんな新作だ。大ヒットした「レギュレイト」あたりに比べるとちょっとインナーな印象もあるので、その辺がどう受け止められるかで本作に対する評価も変わってきそうだけど。充実度はこっちのほうが上だと思う。御大ロナルド・アイズリーを迎え、アイズリー・ブラザーズの「クーリング・ミー・アウト」のメロディを織り込みながら展開する「スモーキング・ミー・アウト」とか、最高の出来。
シングル・ヒット中の「アイ・ショット・ザ・シェリフ」も含め、この人の曲は歌もののフックを持ったやつばっかなので、日本人でも盛り上がれるね(笑)。プロデューサーとして、ラッパーとして、シンガーとして、底力を発揮した一枚。
Chocolate Supa Highway
Spearhead
(Capitol)
 スーパー・ハイウェイ……なんてタイトル通り、インターネッターにはおなじみのモデムの接続音からスタートする新作。中心メンバー、マイケル・フランティは“ギル・スコット・ヘロンの後継者”とか言われてるんだって? なるほど。ヒップホップやレゲエというストリート・カルチャーを知性的にアダプトしつつ、しかしポップ・ミュージックとしてのダイナミズムを失わない感じってのは、確かにギル・スコット・ヘロンにも通じる。
スーパー・ハイウェイ……なんてタイトル通り、インターネッターにはおなじみのモデムの接続音からスタートする新作。中心メンバー、マイケル・フランティは“ギル・スコット・ヘロンの後継者”とか言われてるんだって? なるほど。ヒップホップやレゲエというストリート・カルチャーを知性的にアダプトしつつ、しかしポップ・ミュージックとしてのダイナミズムを失わない感じってのは、確かにギル・スコット・ヘロンにも通じる。
往年のカーティス・メイフィールドを思わせるクールな「U Can't Sing R Song」って曲がごきげん。ボブ・マーリーの息子、スティーヴン・マーリーとのデュエットによる「Rebel Music」も深い仕上がり。ジョーン・オズボーンが、なんとカントリー・ゴスペルみたいな歌声を聞かせる「Wayfarin' Stranger」もいい。前作以上に幅広いルーツ・ミュージックへとアクセスした一枚って感じだ。冒頭のモデム音には、そういう意味もあるのかな。
ノってたころのアレステッド・デヴェロップメントにも通じる手応えがある。
Baduizm
Erykah Badu
(Kedar Entertainment/Universal)

(for Music Magazine, May 1997)
映画『ハイ・スクール・ハイ』のサントラ盤でディアンジェロと「ユア・プレシャス・ラヴ」をデュエットしていたダラス出身の女性シンガーのデビュー・アルバム。つまり、ディアンジェロをマーヴィン・ゲイとすれば、タミー・テレルにあたる立場の女性なわけだけど。ヘタすりゃ資質はディアンジェロ以上かも。かなり歌える人だ。“ビリー・ホリデイの再来”という評もあちこちで目にした。確かに節回しとか、かなりそれっぽいところもあるが、まあ、ダイアナ・ロス経由のビリー・ホリデイってところか。すでに全米で大ヒットしたボブ・パワーズのプロデュース曲2をはじめ、天性のジャズっぽいスウィング感を見事ヒップホップ・ソウルの手触りと融合してみせてくれる粒ぞろいの楽曲がずらり並んでいる。
とはいうものの、彼女のメンタリティは間違いなくヒップホップ寄り。そこがいいのだ。トランペットとエレクトリック・ピアノによる渋いプレイをバックにフリースタイルで綴られた「Afro」など、もろジャズ・ブルースなのだが、彼女はいきなり“ベイビー、ウータンを見に連れてってくれるって言ったじゃない”とか歌い出すし。ロン・カーターをベースに迎えた「Drama」ではレイシズムも含め、マーヴィン・ゲイの「ホワッツ・ゴーイン・オン」にも通じる問題意識を投げかけてくるし。やはりミュートをつけたトランペットがいい味を出している「Otherside Of The Game」でも、ドラッグがらみなのか何なのか、やばい商売してる男との関係で苦悶する心理のようなものが歌われているみたいだし。聞き終えたあとの感触はまぎれもなくヒップホップ・アルバム。“現在のジャズ”としてのヒップホップって感じ。
そうしたアプローチにかけては彼女の先輩格にあたるザ・ルーツもプロデュースに参加。実に豊かなグルーヴをプレゼントしている。ぼくは不勉強でどういう人だかまったく知らないのだけれど、マダクウ・チンワー(って読むのかな。Madakwu Chinwah)ってやつがなかなかいいサウンド作りをしているのも印象に残った。音のほうはどの曲もクールでヒップ、かつスムースな仕上がり。が、前述した3曲も含め、歌詞はけっこうきわどい側面にも踏み込んでいる。ウッド・ベースがいい味のビートを繰り出す「Certainly」では身勝手に恋人を“所有”しようとする恋人にすっくと立ち向かい、ムーディなミディアム・グルーヴ「Next Lifetime」では不倫も匂わせ…。先行ヒット・シングル「On And On」ともども、自分をけっして見失わない自覚的な女性像のようなものにアルバム全体が貫かれていることも、彼女のグレードをワンランク・アップさせているのだろう。ぼくの英語力じゃ太刀打ちできない難解なレトリックも多いんだけどさぁ。アトランティック・スターのルイス兄弟作による「4 Leaf Clover」もいい味。
|