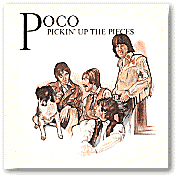
The unreleased liner notes of
Pickin' Up The Pieces
Poco
(Epic/Legacy)

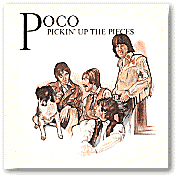
The unreleased liner notes of
Pickin' Up The Pieces
Poco
(Epic/Legacy)
|
実際のところ、CSN&Yはバンドというより、むしろセッション・ユニット的な性格が強い存在だった。メンバーひとりひとりがそれぞれの個性を発揮したソロ・アーティストの集合体とでもいうべきか。メンバー間にただようぴりぴりとした緊張感もおよそ従来の“ポップ・バンド”というイメージとはかけ離れて見えたものだ。対してポコはきっちり、従来の“バンド”としての美学をまっとうしながらスタートをきった。元バッファロー・スプリングフィールドのメンバーだった二人が結成した注目の新人グループとして、前途は洋々だったはずだ。当時の日本の音楽雑誌などでも、まさに期待のホープとして紹介されていた。本デビュー・アルバムがはじめて日本でリリースされたときの邦題は『カントリー・ロックの貴公子、ポコ誕生!』という、なんとも勇ましいものだった。
が、ポコはいい。最高だ。発表当時の時代性の呪縛から解き放たれたこの90年代に聞けば、きっとそんな事実がより客観的に味わえるはずだ。メンバー的に言っても最良の形でレコーディングされた本ファースト・アルバムがCD化されたことは、だからとてもうれしい。心底、感動だ。エピック・レコード在籍時のポコの場合、セールス的にも71年のライヴ・アルバム『ライブ・ポコ(Deliverin')』が最高傑作とされていたりするが、個人的には本ファースト・アルバム『ピッキン・アップ・ザ・ピーシズ』こそがもっともポコらしい輝きに満ちた一枚だと思っている。
が、『ラスト・タイム…』をレコーディングするころには、メンバー間の意見の食い違いなどからすでにバッファローの解散が決まっており、二人は次の動きを模索し始めていた。そして『ラスト・タイム…』の収録曲である「カインド・ウーマン」のセッションのときゲスト・プレイヤーとしてスタジオに招いたペダル・スティール奏者のラスティ・ヤングを誘って、ニュー・グループを結成することにした。ヤングは1946年2月生まれ。出身地については本盤のオリジナル・ジャケットを見るとコロラド州デンヴァーと書かれているが、カリフォルニア州ロングビーチ出身でのちにコロラドに移住したとする説もある。7歳のころからスティール・ギターをプレイし、14歳のときすでにプロのミュージシャンとして活動を開始したという。大学時代に、ボーンジー・クリーク(Boenzee Cryque)なるカントリー・ロック・バンドに参加。大学をやめてバンドでロサンゼルスに向かった。バッファローのレコーディングにセッション・ミュージシャンとして招かれたのは、このころだ。こうしてフューレイ、メッシーナ、ヤングという中心メンバーが勢ぞろい。ヤングはちょうど同じころ、やはりロサンゼルスをベースに活動していたフライング・ブリトー・ブラザーズからも誘いを受けていたらしいが、結局はポコを選択。残りのメンバーはオーディションで決めようということになった。
このニュー・バンド、もともとはマンガのタイトルから取った“ポゴ(Pogo)”という名前を名乗っていたが、これはマンガの作者からクレームがつき、ボツ。仕方なく“ポコ”と改名したのだとか。そして本格的な活動を開始したが、ひと月ほどでいきなりランディ・マイズナーが脱退。理由に関しては、申し訳ないが勉強不足でわからない。その後、彼はリッキー・ネルソンのバック・バンドであるザ・ストーン・キャニオン・バンドを経て、ご存じイーグルスにオリジナル・メンバーとして参加することになるのだが、歌もベースも絶妙にこなす男だけに、様々なバンドからの誘いがかかっていたのかもしれない。が、正式メンバーとしてはラインアップからはずれたマイズナーだが、脱退後もしばらくはポコに関わっていた。本デビュー・アルバムでもベースとコーラスでほぼ全面的に参加している。いきなり結論めいた話になるが、ポコの音楽性を考えると、ぼくはのちのティモシー・シュミットではなく、あくまでもランディ・マイズナーこそがベーシストとして最適任者だったと今でも信じている。指弾きのシュミットに比べてピックを使うマイズナーのベースはどこかスカッと抜けた味わいを持っている。この感じがポコにぴったりなのだ。このあたりの話に関しては、バッファロー・スプリングフィールドからポコにかけて、リッチー・フューレイを追い続けた大滝詠一師匠の受け売りっぽくなってしまうのだが。とにかく。その後のポコの歩みも視野に入れて語るとすれば、彼らの歴史の中で本デビュー・アルバムがもっとも明るい仕上がりになっている。彼らは何度もメンバー・チェンジを繰り返しながら徐々に重くパワーのあるサウンドを志向していくことになるのだが、少なくともぼくにとってのポコ・サウンドとは、あくまでも本盤で聞くことができるような、カラッと抜けたカントリー・ロック・サウンド。そういう意味では、とにかくマイズナー。彼がメンバーにいたことが本盤をより味わい深いものにしている。
その後のポコは、マイズナーの代わりとしてティモシー・シュミットが70年に加入。相前後してメッシーナがロギンス&メッシーナを結成するために脱退し、ポール・コットンが加入。しばらくはこの新編成で活動していたが、やがて73年、フューレイも脱退し、サウザー・ヒルマン・フューレイ・バンドへと移籍してしまった。言い出しっぺでもあるメッシーナとフューレイが脱退した時点で、ポコはもう結成当時のコンセプトを失った別のバンドになってしまったと思ったほうがいいだろう。彼らのポップなコンセプトを受け入れてくれる時代ではなかったことが今にして思えば悲しいが。ともあれ、そんなことを考え合わせても、間違いなくポコがもっともポコらしく輝いていたのが、このデビュー・アルバムだった。
|