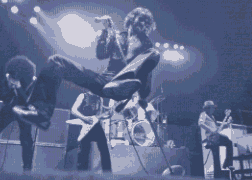
The J. Geils Band
For Record Collectors Magazine
(Nov. 1990)
永遠のB級バンド。と、そんな感じ。けっしてケナしているのではなく。愛と敬意をたっぷりこめた最上級の賛辞として、この言葉をJ・ガイルズ・バンドに送りたい。
結成以来およそ15年、メンバー・チェンジもなく、大好きなR&Bやブルースを熱く愛し続けた男たち。そのスタートは1960年代半ばにさかのぼる。バンド名からもわかる通り、グループのリーダーはギタリストのジェローム・ガイルズ。が、実質的なバンドの“顔”的な存在は、ほぼ全てのオリジナル曲の作詞とリード・ヴォーカルを担当していたピーター・ウルフことピーター・ブランクフィールドだ。ブロンクスのストリート・コーナーで多くの黒人音楽を浴びるように聞いて育った彼は、奨学金を得て美術学校に通うためボストンへと移住した。1965年か66年ごろ、ドゥ・ワップ・レコードのコレクター仲間だったボストン出身のスティーヴン・ジョー・ブラッドとともに“ザ・ハリュシネイションズ”という地元のバントに参加。ウルフはヴォーカル、ブラッドはドラムを担当した。 レパートリーはジョン・リー・フッカーからミラクルズまで。ブルースやR&B、50年代ロックンロールのカヴァーを続けていたそうだ。が、67年に解散。二人は当時やはりボストンで活躍していたアコースティック・ブルース・トリオ、“ザ・J・ガイルズ・ブルース・バンド”に加入することになった。そこで出会ったのが、ニューヨーク出身のギタリスト、ジェローム・ガイルズと、コネチカット出身のハーモニカ・プレイヤー、マジック・ディック、そしてニューヨーク出身のベーシスト、ダニー・クレインの3人。ウルフとブラッドの加入を機に、楽器をエレクトリックに持ち換え、サウンドをグレードアップした。当時、多くのバンドが時代の流行を取り入れサウンド的にもファッション的にもどんどんサイケデリック色を濃くしていったのに対し、彼らは相変わらず髪をグリースでかため、頑固にソリッドなR&Bやブルース・サウンドを追求していた。
レパートリーはジョン・リー・フッカーからミラクルズまで。ブルースやR&B、50年代ロックンロールのカヴァーを続けていたそうだ。が、67年に解散。二人は当時やはりボストンで活躍していたアコースティック・ブルース・トリオ、“ザ・J・ガイルズ・ブルース・バンド”に加入することになった。そこで出会ったのが、ニューヨーク出身のギタリスト、ジェローム・ガイルズと、コネチカット出身のハーモニカ・プレイヤー、マジック・ディック、そしてニューヨーク出身のベーシスト、ダニー・クレインの3人。ウルフとブラッドの加入を機に、楽器をエレクトリックに持ち換え、サウンドをグレードアップした。当時、多くのバンドが時代の流行を取り入れサウンド的にもファッション的にもどんどんサイケデリック色を濃くしていったのに対し、彼らは相変わらず髪をグリースでかため、頑固にソリッドなR&Bやブルース・サウンドを追求していた。
ちなみに、当時ピーター・ウルフは、WBCNというボストンのFM局でDJをつとめたりもしていた。“ウーファ・グーファ”と名乗って、のちにJ・ガイルズ・バンドのステージでの名物にもなる早口のラップ調マシンガン・トークを聞かせていたのだとか。そうこうするうちに、1968年、ボストン大学に通うためにアトランティック・シティからやってきたキーボード・プレイヤー、セス・ジャストマンがメンバーに加入し、屈強の6人のラインアップが完成。バンド名も“ザ・J・ガイルズ・バンド”とシンプルに変更し、本格的な活動を開始した。
翌69年にはジェリー・ウェクスラーとジョン・ランドーの後押しを得てアトランティック・レコードと契約。彼らは精力的にクラブ・ツアーを続け、ライヴ・バンドとしての実力を磨いていった。フリートウッド・マック、トラフィック、ジェフ・ベックらのオープニング・アクトもつとめていたという。ウッドストック・フェスティヴァルへの出演依頼も受けたそうだが、彼らはこれを蹴っている。黒人音楽に憧れていた彼らにとってステージはフォーマルなもの。ビシッとキメたい場。ウッドストックのように、野外で3日間、泥にまみれてライヴをするのはその美学に反するということだったらしい。なんともJ・ガイルズっぽいエピソードだ。
そして71年、アトランティック・レコードからいよいよファースト・アルバム『デビュー!』をリリースした(全米アルバムズ・チャート、最高195位)。ジェリー・ウェクスラーの薦めで、ジョー・テックスやウィルソン・ピケットらと仕事していたブラッド・シャピロ&デイヴ・クロフォードがプロデュースを担当。当時、ウェクスラーはシャピロ&クロフォードをアトランティックのギャンブル&ハフ的存在に育てようとしていたらしく、それに応えて、シャピロたちはJ・ガイルズ・バンドのデビュー・シングルとしてドリフターズの名曲「オン・ブロードウェイ」のカヴァーを用意していた。が、壮麗なストリングスをともなったそのアレンジに不満を抱いたJ・ガイルズ・バンドの面々はこれを拒否。“ハーモニカ・プレイヤーがいるんだからジミー・リードのカヴァーはどうだ?”という代案も拒否。困ったシャピロとクロフォードはバンドをスタジオに入れ、いつもクラブではどんな曲をやっているのか、全てのレパートリーを演奏させたという。 その結果、アルバム用に選曲されたのがオーティス・ラッシュ、ジョン・リー・フッカー、アルバート・コリンズ、ミラクルズといったブルース/R&Bアーティストのカヴァー6曲と、メンバーによるオリジナル5曲。ライヴで鍛え上げた曲ばかりだったため、全11曲をたったの18時間で録り終えてしまったそうだ。今振り返ってみると、このファースト・アルバムが最もJ・ガイルズ・バンドらしい1枚かもしれない。マジック・ディックの強力なブルース・ハープ、J・ガイルズの荒っぽいけれど歌心に満ちたギター、ピーター・ウルフの渋さと鋭さを併せ持ったしゃがれ声……。テクニック的にはうまくないが、バンドが一丸となって憧れの黒人音楽めがけて突進を続けている、そんな勢いがやけに爽快だ。
その結果、アルバム用に選曲されたのがオーティス・ラッシュ、ジョン・リー・フッカー、アルバート・コリンズ、ミラクルズといったブルース/R&Bアーティストのカヴァー6曲と、メンバーによるオリジナル5曲。ライヴで鍛え上げた曲ばかりだったため、全11曲をたったの18時間で録り終えてしまったそうだ。今振り返ってみると、このファースト・アルバムが最もJ・ガイルズ・バンドらしい1枚かもしれない。マジック・ディックの強力なブルース・ハープ、J・ガイルズの荒っぽいけれど歌心に満ちたギター、ピーター・ウルフの渋さと鋭さを併せ持ったしゃがれ声……。テクニック的にはうまくないが、バンドが一丸となって憧れの黒人音楽めがけて突進を続けている、そんな勢いがやけに爽快だ。
71年6月にはフィルモア・ウエスト最後のコンサートにビーチボーイズ、マウンテン、オールマン・ブラザーズ・バンドらとともに出演。バターフィールド・ブルース・バンド以来、最高の白人ブルース・バンドとして注目を集めた。同年、プロデューサーをビル・シムジクに変えてリリースされたセカンド・アルバム『モーニング・アフター』(64位)によって、ローリング・ストーン誌の71年度最優秀新人バンドに選ばれたり。このアルバムからシングル・カットされたヴァレンティノズのカヴァー・チューン「ルッキン・フォー・ラヴ」が全米チャート最高39位まで上昇するヒットも記録したり。が、この2枚のスタジオ録音アルバムは、彼らがライヴで見せつける強力なパワーを再現できてはいなかった。そこで、72年、早くもリリースされたのが、デトロイトのシンデレラ・ボールルームで収録されたライヴ・アルバム『フル・ハウス』(54位)。ライヴ・バンドとしての本領を発揮した1枚だった。と、このあたりまでが第1期。ブルースやR&Bに真正面からイキイキと情熱をぶつけていた若きJ・ガイルズ・バンド時代だ。
ところで。個人的な話になるけれど、ぼくが彼らの音にはじめて接したのは、昔、誕生間もないワーナー・パイオニア社から980円という破格の値段で発売された2枚組アルバム『ホット・メニュー』で。ワーナー/リプリーズ系に所属するアーティストを日本でお披露目するために、1アーティスト1曲ずつ、盛りだくさんに詰め込んだ徳用盤。その中にJ・ガイルズ・バンドも収録されていた。確か『フル・ハウス』からの曲だったと思う。荒っぽいけれども、バンドならではのタイトさと、鋭角的な手触りをもったリズムの切れ味とをたたえた演奏ぶりにぶっとんだ。そして、さっそく彼らのオリジナル・アルバムを購入。1973年にリリースされた『ブラッドショット』(10位)だった。タイトル通り、まず真っ赤なカラー・ヴィニールが印象的なアルバム。冒頭に入っていたショーストッパーズのカヴァー曲「ハウス・パーティ」のスピード感、B面アタマのオリジナル曲「サウスサイド・シャッフル」の豪放なジャンプ感。レゲエっぽいビートを取り入れ、全米最高30位に達したシングル「ギヴ・イット・トゥ・ミー」のチンピラっぽさ。もうバカにかっこよくて。一発でまいった。これも余談だが、ちょうどそのころ、彼らの動く姿にもはじめて触れることができた。日本では確か夜の11時くらいからオンエアされていた『ミッドナイト・スペシャル』とか何とかいうアメリカの音楽番組。その番組に彼らが出てきて2曲、生演奏した。マイク・スタンドを棒高跳びのポールのように駆使してジャンプを繰り返すサングラス姿のピーター・ウルフがむちゃくちゃかっこよく映った。
 ただ、今、デビュー直後に連発した3枚のアルバムに接したあとで改めて『ブラッドショット』を聞くと、様々な迷いも見受けられる。デビュー当時のゴリ押し的手触りが影をひそめ、こぢんまりとまとまりだしたような。その迷いは、やはり73年リリースの『招かれた貴婦人』(51位)にも引き継がれている。ライヴの面ではマジソン・スクエア・ガーデンでヘッドライナーをつとめたり、プライヴェート面ではピーター・ウルフが女優のフェイ・ダナウェイと結婚したり、何かと話題を巻いていた時期だが、レコードに関しては今いち。全米12位まで上昇したシングル「傷だらけの愛」を含む74年のアルバム『悪魔とビニール・ジャングル』(26位)は、不敵でファンキーな味をうまくすくいあげていたものの、続く75年の『ホットライン』(36位)もまた中途半端な仕上がりだった。
ただ、今、デビュー直後に連発した3枚のアルバムに接したあとで改めて『ブラッドショット』を聞くと、様々な迷いも見受けられる。デビュー当時のゴリ押し的手触りが影をひそめ、こぢんまりとまとまりだしたような。その迷いは、やはり73年リリースの『招かれた貴婦人』(51位)にも引き継がれている。ライヴの面ではマジソン・スクエア・ガーデンでヘッドライナーをつとめたり、プライヴェート面ではピーター・ウルフが女優のフェイ・ダナウェイと結婚したり、何かと話題を巻いていた時期だが、レコードに関しては今いち。全米12位まで上昇したシングル「傷だらけの愛」を含む74年のアルバム『悪魔とビニール・ジャングル』(26位)は、不敵でファンキーな味をうまくすくいあげていたものの、続く75年の『ホットライン』(36位)もまた中途半端な仕上がりだった。
この迷いの時期を吹っ切ったのは、結局、地元ボストンとデトロイトで収録され76年にリリースされた2枚組ライヴ・アルバム『狼から一撃!』(40位)。オリジナル、カヴァー取り混ぜて、バンドのスケール感を思い知らせてくれる、ファンにとってはたまらない作品だった。しかし、やはりライヴに頼らなければならない彼らの“弱さ”を逆説的に証明している作品でもあった。アルバムを出しては7〜8カ月のツアーに出て、またアルバムを作ってはツアー。アルバム・セールス的に満足な結果が得られないために落ち着くこともできず、ライヴを繰り返し、その結果、ライヴ・バンドとしての実力はぐんぐん付いていくものの、反面、じっくりとアルバム作りをすることもできず……。良くも悪くも彼らが“永遠のB級バンド”にとどまった原因はこの辺にありそうだ。
 77年、グループ名を一瞬シンプルに“ガイルズ”と改めて、アルバム『モンキー・アイランド』(51位)を発表。バンド自らがはじめてプロデュースを手掛け、曲作り、音作りの面でぐっと成熟したところを見せたこのアルバムがアトランティックからの最後のリリースとなった。ここまでが第2期だ。
77年、グループ名を一瞬シンプルに“ガイルズ”と改めて、アルバム『モンキー・アイランド』(51位)を発表。バンド自らがはじめてプロデュースを手掛け、曲作り、音作りの面でぐっと成熟したところを見せたこのアルバムがアトランティックからの最後のリリースとなった。ここまでが第2期だ。
そして、79年。バンド名を再びJ・ガイルズ・バンドに戻してEMIアメリカに移籍。アルバム『サンクチュアリ(禁猟区)』(49位)をリリースした。タートルズやジャニス・イアン、ボズ・スキャッグスらとの仕事で知られるジョー・ウィザートがプロデュースを担当。全曲、ウルフ&ジャストマンのペンによるオリジナルで固められていたのが、何と言っても最大の変化だろう。アトランティックという黒人音楽の名門に籍を置いて、憧れのR&B/ブルースめがけて様々な試行錯誤を続けたのが第1期、第2期の活動。そんな時期を経て、よりポップなフォーマットの中で、黒人音楽からの影響をもう一度自分たちなりに再構築してみせたのがEMIアメリカ時代、第3期のJ・ガイルズ・バンドだ。ワイルドさと洗練とがいい形で融合しはじめた。「ワン・ラスト・キッス」「テイク・イット・バック」というシングル・ヒットも生まれ、本格的な人気爆発への第一歩となった。80年には、「ラヴ・スティンクス」「カム・バック」「ジャスト・キャント・ウェイト」の3枚のヒット・シングルを生んだ傑作アルバム『ラヴ・スティンクス』(18位)をリリース。このアルバムからセス・ジャストマンが単独でプロデュース&アレンジを手掛けるようになった。かなり大胆にシンセサイザーが取り入れられ、より幅広いサウンドを聞かせるようになった。
 80年6月には、待ちに待った初来日公演。レコードを通して間接的にしか接することができなかった彼らのライヴ・バンドとしての底力を存分に思い知らされた。ライヴ本編はほぼ1時間程度で終了。そのあと、何度も何度もアンコールで出てきて、全長2時間半くらい。当時サラリーマンをしていたぼくは、さっさと定時に退社して、確か4回ほど行なわれた東京公演全てに通いつめてしまったけど。いちばん多いときでアンコールに9回応えてくれた記憶がある。8回目のアンコールが終わって、まさか出てこないよな……と思いつつも声援を送っていたら、まさかの9回目。“一晩じゅう演るって言っただろ!”と不敵な笑いを浮かべてMCしたピーター・ウルフが忘れられない。ハード・ロック的な風貌のくせして、ぐいんぐいんとソウルフルなハモンド・オルガンをうならせるセス・ジャストマンも、フル・ステージ軽々とハーモニカを吹き続けるマジック・ディックもすごかった。デビュー・アルバムの収録曲から最新のものまで、まんべんなく網羅された選曲も、そしてバンド一丸となってハシったりモタったりする独特のテンポ感も痛快だった。
80年6月には、待ちに待った初来日公演。レコードを通して間接的にしか接することができなかった彼らのライヴ・バンドとしての底力を存分に思い知らされた。ライヴ本編はほぼ1時間程度で終了。そのあと、何度も何度もアンコールで出てきて、全長2時間半くらい。当時サラリーマンをしていたぼくは、さっさと定時に退社して、確か4回ほど行なわれた東京公演全てに通いつめてしまったけど。いちばん多いときでアンコールに9回応えてくれた記憶がある。8回目のアンコールが終わって、まさか出てこないよな……と思いつつも声援を送っていたら、まさかの9回目。“一晩じゅう演るって言っただろ!”と不敵な笑いを浮かべてMCしたピーター・ウルフが忘れられない。ハード・ロック的な風貌のくせして、ぐいんぐいんとソウルフルなハモンド・オルガンをうならせるセス・ジャストマンも、フル・ステージ軽々とハーモニカを吹き続けるマジック・ディックもすごかった。デビュー・アルバムの収録曲から最新のものまで、まんべんなく網羅された選曲も、そしてバンド一丸となってハシったりモタったりする独特のテンポ感も痛快だった。
と、そんな来日公演を経て、81年。ついに本格的なピークがやってくる。彼らにとって初の全米ナンバーワン・アルバム『フリーズ・フレイム』の登場だ。ここからカットされ、やはり全米1位に達したシングル「堕ちた天使」をはじめ、「フリーズ・フレイム」、「エンジェル・イン・ブルー」などヒットも連発。ニュー・ウェイヴ的なノウハウもちりばめた斬新な音作りで、彼らは結成以来15年の長い苦労を一気に実らせたわけだ。黒人音楽への愛情と敬意を下敷きに、彼らならではの独自のサウンドをつかみとった、躍動感みなぎる1枚だった。81年から82年にかけて行なわれたローリング・ストーンズのワールド・ツアーのサポートもつとめている。
 が、82年にリリースされた3枚目のライヴ・アルバム『ショー・タイム』を最後に、バンドの看板だったピーター・ウルフがなんと脱退を発表。この瞬間、実質的にはJ・ガイルズ・バンドの歴史は終わった。ウルフは84年にEMIアメリカからソロ第1弾アルバム『ライツ・アウト』を、87年に『カム・アズ・ユー・アー』を、そして90年、MCAに移籍して『アップ・トゥ・ノー・グッド』をリリース。相変わらずソウルフルでごきげんなロックンロール・ヴォーカルを聞かせ続けてくれている。が、やはり曲作りのパートナーとしてのセス・ジャストマンを失った穴は大きい。一方のJ・ガイルズ・バンドも、84年にウルフ抜きのラインアップでアルバム『ヒップ・アート』を、85年に映画『フライトナイト』のテーマ曲をリリースしているが、看板抜きになってしまったこちらの穴はさらにでかい。一時、ピーター・ウルフがJ・ガイルズ・バンドに復帰するという噂がまことしやかに流れたこともあったが、どうやらデマだったようだ。しかし、こんな噂が出るのもまたこの両者が別々に活動することの不自然さを誰もが感じているからこそだろう。栄光の絶頂をつかんだ瞬間に空中分解してしまったJ・ガイルズ・バンド。しつこく繰り返させてもらう。こんな割り切れない歴史の閉じ方も含めて、彼らは本当に素晴らしい、最上のB級バンドだった。
が、82年にリリースされた3枚目のライヴ・アルバム『ショー・タイム』を最後に、バンドの看板だったピーター・ウルフがなんと脱退を発表。この瞬間、実質的にはJ・ガイルズ・バンドの歴史は終わった。ウルフは84年にEMIアメリカからソロ第1弾アルバム『ライツ・アウト』を、87年に『カム・アズ・ユー・アー』を、そして90年、MCAに移籍して『アップ・トゥ・ノー・グッド』をリリース。相変わらずソウルフルでごきげんなロックンロール・ヴォーカルを聞かせ続けてくれている。が、やはり曲作りのパートナーとしてのセス・ジャストマンを失った穴は大きい。一方のJ・ガイルズ・バンドも、84年にウルフ抜きのラインアップでアルバム『ヒップ・アート』を、85年に映画『フライトナイト』のテーマ曲をリリースしているが、看板抜きになってしまったこちらの穴はさらにでかい。一時、ピーター・ウルフがJ・ガイルズ・バンドに復帰するという噂がまことしやかに流れたこともあったが、どうやらデマだったようだ。しかし、こんな噂が出るのもまたこの両者が別々に活動することの不自然さを誰もが感じているからこそだろう。栄光の絶頂をつかんだ瞬間に空中分解してしまったJ・ガイルズ・バンド。しつこく繰り返させてもらう。こんな割り切れない歴史の閉じ方も含めて、彼らは本当に素晴らしい、最上のB級バンドだった。